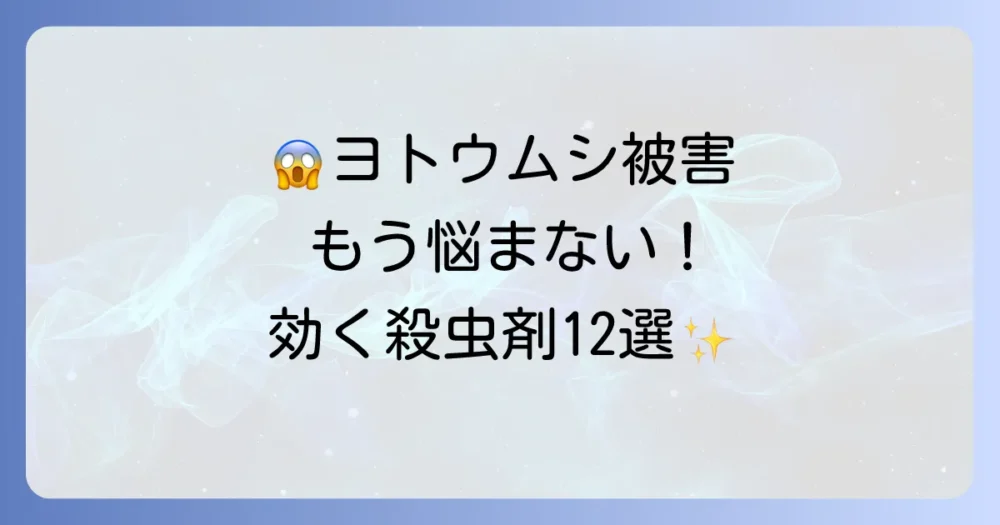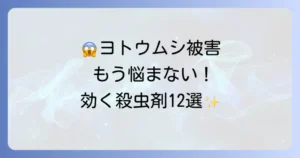大切に育てている野菜や花が、ある日突然、何者かに食べられていたら…ショックですよね。葉がレースのように透けていたり、新芽がボロボロになっていたりしたら、それは「ヨトウムシ」の仕業かもしれません。夜の間に活動するため姿が見えず、気づいた時には被害が拡大していることも多い厄介な害虫です。本記事では、そんなヨトウムシに頭を悩ませているあなたのために、効果的な殺虫剤の選び方から、おすすめの商品、正しい使い方、そして殺虫剤を使わない対策まで、詳しく解説していきます。
【早見表】ヨトウムシに効く殺虫剤はどれ?タイプ別おすすめ一覧
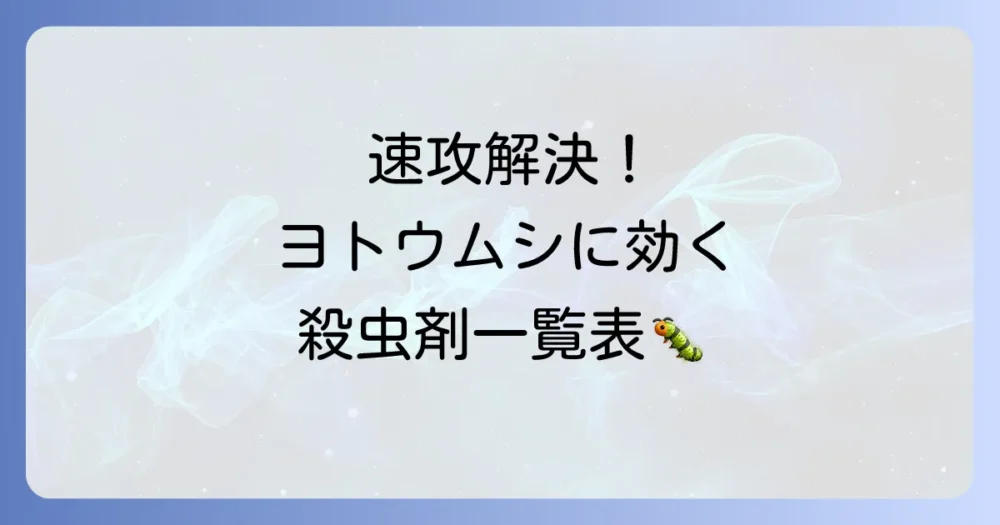
まずは「すぐにでも対策したい!」という方のために、ヨトウムシに効果的な殺虫剤をタイプ別にまとめました。ご自身の状況に合わせて、最適な殺虫剤を見つける参考にしてください。
| タイプ | 特徴 | こんな人におすすめ | 代表的な商品 |
|---|---|---|---|
| スプレータイプ | 即効性が高く、見つけたヨトウムシをすぐに駆除できる。 | 被害を発見し、今すぐ対処したい方。 | ベニカXネクストスプレー、アースガーデン 葉を食べる虫退治 |
| 粒剤タイプ | 株元にまくだけで効果が持続。浸透移行性で植物全体を守る。 | 予防的に使いたい方、手間をかけずに長期間対策したい方。 | GFオルトラン粒剤 |
| ベイト剤(誘殺剤) | ヨトウムシをおびき寄せて食べさせて駆除。土の中に隠れている幼虫に効果的。 | 日中姿が見えないヨトウムシを確実に駆除したい方。 | サンケイデナポン5%ベイト |
| 天然由来・食品成分 | 化学農薬に頼りたくない方向け。野菜の収穫前日まで使えるものも多い。 | オーガニック栽培をしている方、小さなお子様やペットがいるご家庭。 | STゼンターリ顆粒水和剤、プレバソンフロアブル5 |
ヨトウムシに効く殺虫剤の選び方|3つのポイント
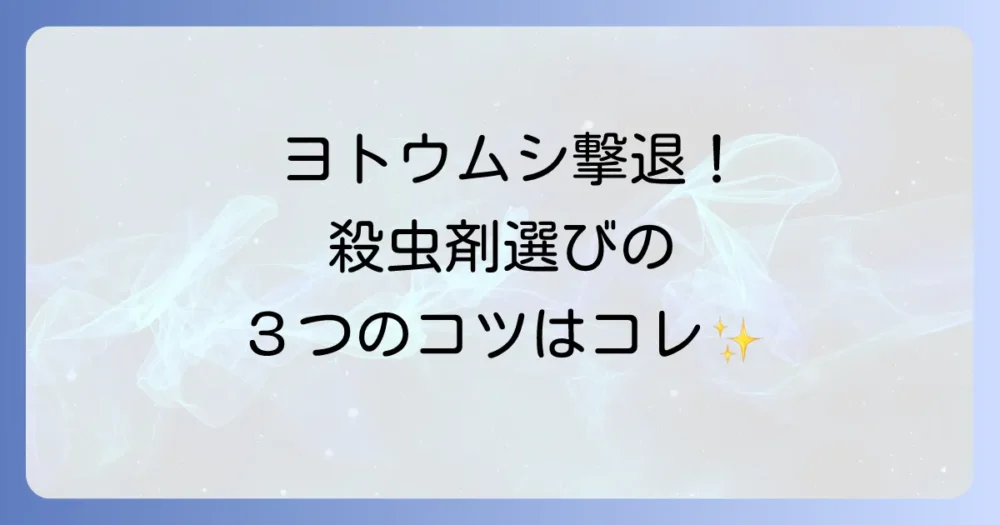
ヨトウムシ用の殺虫剤は数多く販売されており、どれを選べば良いか迷ってしまいますよね。そこで、ご自身の状況に合った殺虫剤を選ぶための3つのポイントをご紹介します。
この章で解説する選び方のポイントは以下の通りです。
- ①殺虫剤のタイプで選ぶ(スプレー・粒剤・ベイト剤)
- ②育てる植物で選ぶ(野菜・花・果樹)
- ③成分で選ぶ(化学農薬・天然由来)
①殺虫剤のタイプで選ぶ(スプレー・粒剤・ベイト剤)
殺虫剤には、それぞれ特徴の異なるタイプがあります。被害の状況や使い方に合わせて選びましょう。
スプレータイプ(エアゾール剤・液剤)
スプレータイプは、見つけたヨトウムシに直接噴射して駆除できる即効性が魅力です。希釈する手間がなく、すぐに使える商品が多いのも便利な点です。葉の裏など、虫が潜んでいる場所にピンポイントで散布しやすいでしょう。ただし、効果の持続期間は粒剤に比べて短い傾向があります。
粒剤タイプ
粒剤は、植物の株元にまくことで、有効成分が根から吸収され、植物全体に行き渡る(浸透移行性)のが特徴です。 効果が長期間持続するため、予防的な使用にも適しています。 葉の裏に隠れている害虫や、新しく出てきた葉にも効果が期待できるのが大きなメリットです。
ベイト剤(誘殺剤)
ベイト剤は、ヨトウムシが好む成分で誘い込み、殺虫成分を含んだエサを食べさせて駆除するタイプの薬剤です。 夜行性で日中は土の中に隠れているヨトウムシの習性を利用したもので、姿が見えない害虫にも効果を発揮します。 株元にパラパラとまくだけなので、手軽に使用できます。
②育てる植物で選ぶ(野菜・花・果樹)
殺虫剤を選ぶ上で非常に重要なのが、「育てている植物に使えるかどうか」を確認することです。農薬は「農薬取締法」に基づき、作物ごとに登録されています。パッケージや説明書に記載されている「適用作物」を必ず確認しましょう。
特に野菜や果樹など、口に入れる植物に使う場合は注意が必要です。収穫前日まで使えるものや、使用回数に制限があるものなど、製品によってルールが異なります。 安全に美味しくいただくためにも、用法・用量を必ず守ってください。例えば、住友化学園芸の「STゼンターリ顆粒水和剤」は天然成分でできており、多くの野菜で収穫前日まで使用可能です。
③成分で選ぶ(化学農薬・天然由来)
殺虫剤の成分は、大きく「化学合成農薬」と「天然由来成分の農薬」に分けられます。
化学合成農薬
化学的に合成された成分を主原料とする農薬です。有機リン系、ピレスロイド系、ネオニコチノイド系、ジアミド系など様々な種類があり、速効性や持続性に優れた製品が多いのが特徴です。 代表的な製品に「オルトラン」や「プレバソン」などがあります。 幅広い害虫に効果がある一方で、使用できる作物や時期、回数が厳密に定められています。
天然由来・食品成分の農薬
微生物(BT菌など)や植物抽出物、食品などを原料とした農薬です。化学農薬の使用に抵抗がある方や、有機JAS規格の栽培を目指す方におすすめです。 住友化学園芸の「STゼンターリ顆粒水和剤」はBT菌を利用したもので、チョウ目害虫であるヨトウムシに効果的です。 また、同社の「ピュアベニカ」は食品成分100%でできており、食べる直前まで使える手軽さが魅力です。
ただし、天然由来だからといってどんな植物にも無制限に使えるわけではありません。こちらも必ず適用作物や使用方法を確認してから使いましょう。
【タイプ別】ヨトウムシに効く!おすすめ殺虫剤12選
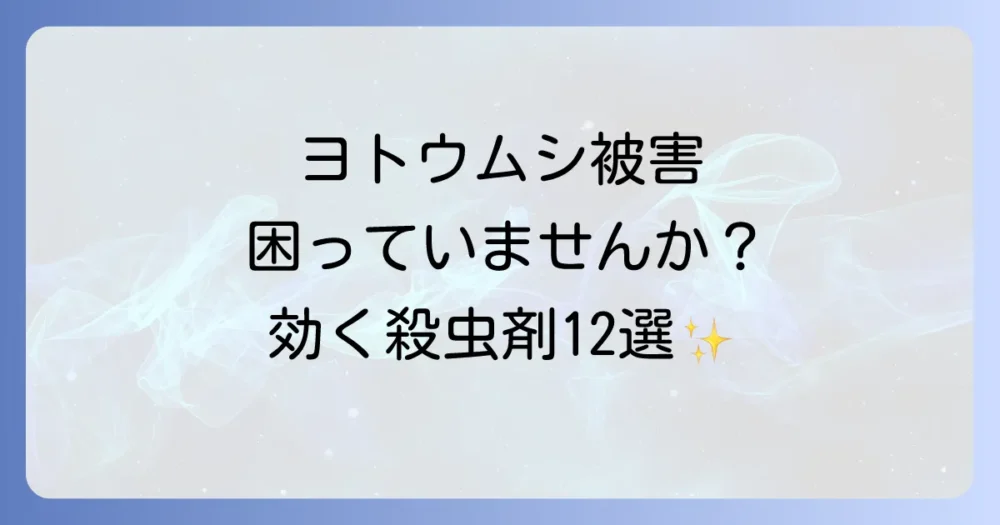
ここからは、選び方のポイントを踏まえて、ヨトウムシ駆除におすすめの殺虫剤をタイプ別にご紹介します。それぞれの特徴を比較して、あなたのガーデニングスタイルにぴったりの一本を見つけてください。
【即効性重視】スプレータイプのおすすめ殺虫剤
見つけたヨトウムシをすぐに退治したい!という方には、即効性の高いスプレータイプがおすすめです。
住友化学園芸 ベニカXネクストスプレー
5種類の有効成分を配合し、ヨトウムシはもちろん、アブラムシやハダニ、うどんこ病や黒星病などの病気にも効果を発揮する殺虫殺菌スプレーです。 幅広い植物に利用でき、害虫と病気を同時に防除できるため、一本持っておくと非常に便利です。予防効果も期待できるため、定期的な散布もおすすめです。
アース製薬 アースガーデン 葉を食べる虫退治
商品名の通り、葉を食べる害虫に特化した殺虫剤です。ヨトウムシやアオムシなど、チョウ目の幼虫に速効性と持続性を兼ね備えています。 逆さまでもスプレーできるため、葉の裏に隠れているヨトウムシにも散布しやすいのが嬉しいポイントです。
フマキラー カダンセーフ
食品由来成分「ソルビタン脂肪酸エステル」が有効成分で、野菜やハーブなど、食べる植物にも安心して使えるのが最大の特徴です。 ヨトウムシだけでなく、アブラムシやハダニなどにも効果があり、収穫前日まで何度でも使用できます。化学農薬を使いたくないけれど、手軽にスプレーで対策したいという方に最適です。
【効果が持続】粒剤タイプのおすすめ殺虫剤
予防的に使いたい、できるだけ手間をかけたくないという方には、効果が長持ちする粒剤タイプがぴったりです。
住友化学園芸 GFオルトラン粒剤
言わずと知れた家庭園芸用殺虫剤の定番です。株元にまくだけで、有効成分アセフェートが根から吸収されて植物全体に行き渡り、ヨトウムシをはじめとする食害性害虫やアブラムシなどの吸汁性害虫を同時に防除します。 効果の持続期間が長く、害虫予防に非常に効果的です。
日本曹達 モスピラン粒剤
有効成分ジノテフランが優れた浸透移行性を持ち、幅広い害虫に効果を発揮します。特にカメムシ類やアブラムシ類に高い効果を示しつつ、ヨトウムシにも有効です。 野菜や花き類など、多くの作物に登録があり、使いやすい殺虫剤の一つです。
【土に潜む幼虫に】ベイト剤(誘殺剤)のおすすめ
夜行性でなかなか姿を見せないヨトウムシには、おびき寄せて退治するベイト剤が効果的です。
住友化学園芸 サンケイデナポン5%ベイト
ヨトウムシやネキリムシが好む誘引成分を配合し、食べさせて駆除するタイプの殺虫剤です。 昼間は土の中に隠れているヨトウムシを効率的に退治できます。使い方は、夕方に株元や畝間にパラパラとまくだけ。薬剤が直接植物にかからないため、安心して使用できます。
【野菜やオーガニック栽培に】天然由来・効果の高いおすすめ殺虫剤
安全性にこだわりたい方や、より専門的な対策をしたい方におすすめの殺虫剤です。野菜作りを楽しむ方にも人気があります。
住友化学園芸 STゼンターリ顆粒水和剤
天然の微生物であるBT菌が有効成分の殺虫剤です。 この菌が作るタンパク質が、チョウ目害虫の消化管に作用して効果を発揮します。人間や他の益虫には影響が少なく、有機JAS規格の農産物栽培でも使用できる安全性の高い薬剤です。 野菜や果樹のヨトウムシ対策に最適です。
FMC/丸和バイオケミカル プレバソンフロアブル5
新規の有効成分「クロラントラニリプロール」を含み、従来の殺虫剤に抵抗性がついたヨトウムシ(ハスモンヨトウなど)にも高い効果を発揮します。 害虫の摂食活動を速やかに停止させるため、被害の拡大をすぐに食い止められるのが強みです。 残効性も長く、約2週間の効果が期待できます。
日産化学 グレーシア乳剤
こちらも新しい有効成分「フルキサメタミド」を配合した殺虫剤です。 チョウ目害虫に速効的な効果を示し、アザミウマ類など幅広い害虫にも有効です。 天敵や有用昆虫への影響が少ないのも特徴で、総合的な害虫管理を目指す方におすすめです。
シンジェンタジャパン アファーム乳剤
天然物由来の有効成分で、ヨトウムシやコナガなどのチョウ目害虫に高い活性を示します。 速やかに害虫の動きを止め、食害を抑制します。 多くの野菜や果樹に登録があり、プロの農家からも信頼されている薬剤の一つです。
三井化学クロップ&ライフソリューション トレボン乳剤
速効性と持続性に優れた合成ピレスロイド系の殺虫剤です。 ヨトウムシをはじめ、樹木のケムシなど、非常に幅広い害虫に効果があります。 人や動物への毒性が低く、公園の樹木管理などにも使用される安全性の高い薬剤です。
殺虫剤の効果を最大化する!正しい使い方とタイミング
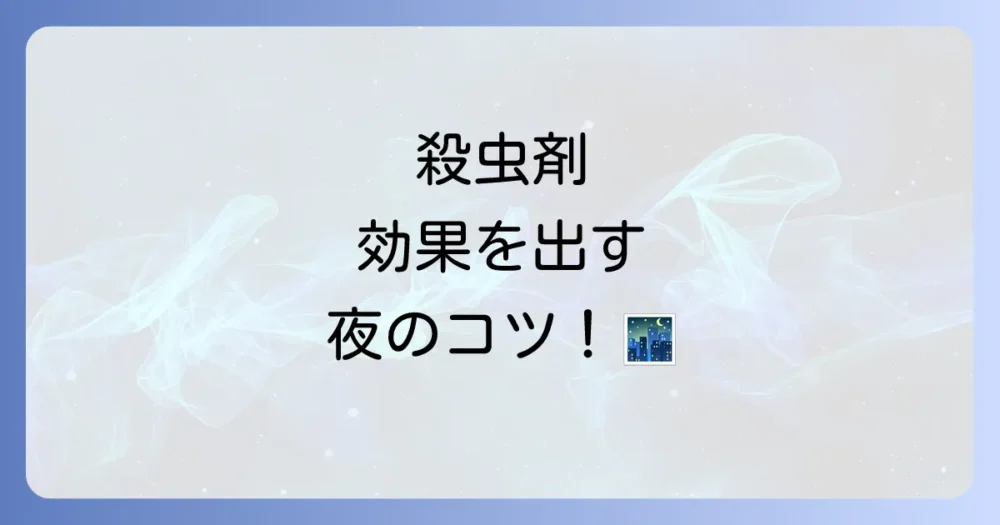
せっかく殺虫剤を使うなら、その効果を最大限に引き出したいですよね。ちょっとしたコツを押さえるだけで、駆除効果は格段にアップします。ここでは、殺虫剤の正しい使い方と効果的なタイミングについて解説します。
散布はヨトウムシが活動する「夜」が効果的
ヨトウムシは、その名の通り「夜盗虫」と呼ばれる夜行性の害虫です。 昼間は土の中や株の根元に隠れており、夜になると這い出してきて葉や新芽を食い荒らします。 そのため、殺虫剤を散布するなら、彼らが活動を始める夕方から夜にかけてが最も効果的です。 活動中のヨトウムシに直接薬剤がかかり、駆除しやすくなります。
葉の裏までしっかり散布する
ヨトウムシの親であるヨトウガは、葉の裏に卵をびっしりと産み付けます。 孵化したばかりの小さな幼虫(若齢幼虫)は、集団で葉の裏から食害を始めます。 そのため、殺虫剤を散布する際は、葉の表面だけでなく、葉を一枚一枚めくりながら、葉の裏側にも薬剤がしっかりかかるように丁寧に散布することが重要です。 これにより、孵化したての幼虫をまとめて駆除でき、被害の拡大を防ぐことができます。
若齢幼虫のうちに駆除するのがコツ
ヨトウムシは、成長して大きくなる(老齢幼虫になる)と、薬剤が効きにくくなる傾向があります。 また、食害量も格段に増えるため、被害が一気に深刻化します。そのため、葉が白く透けて見えるような食害痕(若齢幼虫のサイン)を見つけたら、すぐに殺虫剤で対処するのが駆除成功のコツです。 早期発見・早期駆除を心がけましょう。
使用回数や希釈倍率を守る
農薬には、作物ごとに使用できる回数や、水で薄める際の希釈倍率が定められています。 これは、作物を安全に食べるため、そして環境への影響を最小限に抑えるために非常に重要です。また、同じ殺虫剤を連続して使用していると、薬剤に抵抗性を持つヨトウムシが出現し、効果が薄れてしまうことがあります。 作用性の異なる複数の殺虫剤を順番に使う「ローテーション散布」を行うことで、抵抗性の発達を防ぎ、長く効果的に薬剤を使い続けることができます。
そもそもヨトウムシとは?生態を知って対策しよう
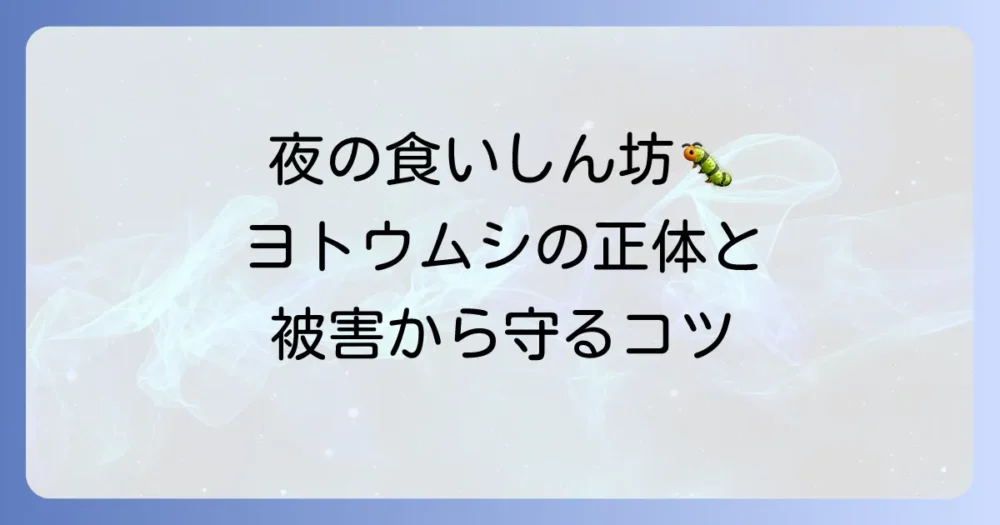
効果的な対策を行うためには、まず敵を知ることが大切です。ヨトウムシとは一体どんな虫なのか、その生態を理解することで、より的確な予防や駆除が可能になります。
この章では、ヨトウムシの正体や生態について詳しく解説します。
- ヨトウムシ(夜盗虫)の正体は「ガの幼虫」
- 発生時期と活動サイクル
- ヨトウムシが好む植物
- 被害の特徴(葉がレース状になる)
ヨトウムシ(夜盗虫)の正体は「ガの幼虫」
「ヨトウムシ」とは、特定の虫の名前ではなく、夜に活動して農作物を食害するヤガ科のガの幼虫の総称です。 主な種類として「ヨトウガ」「ハスモンヨトウ」「シロイチモジヨトウ」などが知られています。 体長は大きいもので4〜5cmにもなり、体色は緑色や褐色、黒っぽいものまで様々です。 昼間は土の中や葉の陰に隠れ、夜になると活動を始めることから「夜盗虫」と呼ばれています。
発生時期と活動サイクル
ヨトウムシの発生時期は種類によって多少異なりますが、一般的に春から秋にかけて、年に2回以上発生します。 特に、4月〜6月と9月〜10月が発生のピークです。 暖地では年に数世代発生することもあります。冬は土の中でサナギの状態で越冬し、春に羽化して成虫(ヨトウガ)になります。 成虫は葉の裏に数百個の卵を塊で産み付け、そこから孵化した幼虫が植物を食い荒らすのです。
ヨトウムシが好む植物
ヨトウムシは非常に食欲旺盛で、雑食性です。 そのため、被害は多くの植物に及びます。
特に被害に遭いやすいのは、キャベツ、ハクサイ、レタスなどの葉物野菜、ナス、トマト、イチゴなどの果菜類、ダイコン、ニンジンなどの根菜類です。 また、野菜だけでなく、キクやバラ、パンジーといった花き類、さらには果樹まで、柔らかい葉や新芽、花びらを好んで食べます。 家庭菜園やガーデニングで育てられるほとんどの植物がターゲットになると考えてよいでしょう。
被害の特徴(葉がレース状になる)
ヨトウムシの被害で最も特徴的なのは、孵化したばかりの若齢幼虫による食害です。 彼らは葉の裏に集団で潜み、葉の表面の薄皮を残して葉肉だけを食べるため、被害を受けた葉は白っぽく透けて、まるでレースのような見た目になります。 これがヨトウムシ発生の初期サインです。成長した老齢幼虫は食欲がさらに旺盛になり、葉脈を残して葉全体を食べ尽くしたり、新芽や実を食い荒らしたりして、植物の生育に深刻なダメージを与えます。
殺虫剤を使わない!ヨトウムシの予防と駆除方法
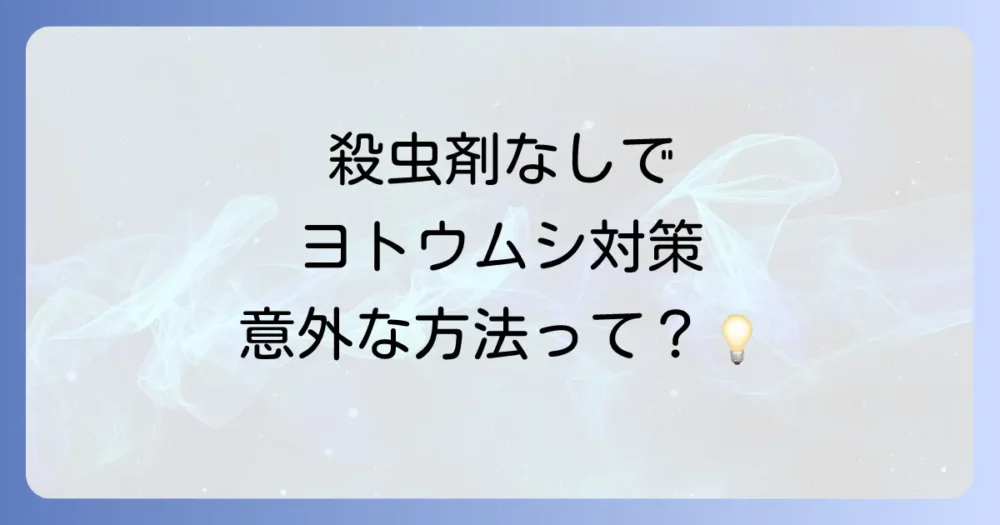
「できるだけ殺虫剤は使いたくない」という方も多いでしょう。幸い、ヨトウムシは化学農薬に頼らなくても、日々の管理や工夫で被害を減らすことが可能です。ここでは、薬剤を使わない予防策と駆除方法をご紹介します。
【予防策】成虫を寄せ付けない環境づくり
ヨトウムシの被害を防ぐには、そもそも親であるヨトウガに卵を産み付けさせないことが最も重要です。物理的な方法で、産卵場所をなくしましょう。
防虫ネット・寒冷紗をかける
最も確実な予防法の一つが、プランターや畝全体を防虫ネットや寒冷紗で覆うことです。 網目の細かいネット(1mm目合い以下がおすすめ)で物理的にガの侵入を防ぎ、産卵を阻止します。トンネル支柱などを使って、ネットが植物の葉に直接触れないように空間を確保するのがポイントです。
雑草をこまめに抜く
畑や庭の周りに雑草が生い茂っていると、ヨトウガの隠れ家や産卵場所、さらには冬越しの場所になってしまいます。 こまめに除草を行い、風通しを良くしておくことで、害虫が発生しにくい環境を維持できます。
作付け前に土を耕す
ヨトウムシは土の中でサナギの状態で越冬します。 そのため、野菜を植え付ける前や収穫後に畑を深く耕すことで、土の中に潜んでいるサナギを地表に露出し、鳥に食べさせたり、寒さで死滅させたりする効果が期待できます。 見つけたサナギは、その場で駆除しましょう。
【駆除方法】見つけ次第、捕殺!
被害が発生してしまった場合でも、薬剤を使わずに駆除する方法はあります。根気は必要ですが、確実な方法です。
夜間に懐中電灯で探して捕殺
原始的ですが、最も確実な方法です。ヨトウムシが活動する夜間に、懐中電灯を持って畑やプランターを見回り、葉を食べている幼虫を割り箸などで捕まえて駆除します。 昼間は株元や土の中に隠れていることが多いので、少し土を掘り返してみると見つかることもあります。
米ぬかトラップでおびき寄せる
ヨトウムシは米ぬかが大好物です。 この習性を利用して、米ぬかを水で練って団子状にしたものや、容器に入れた米ぬかを株元に置いておくと、夜間にヨトウムシが集まってきます。 翌朝、集まってきたヨトウムシをまとめて駆除するという方法です。殺虫剤を混ぜて毒餌にする方法もありますが、米ぬかだけでも十分に誘引効果があります。
卵が産み付けられた葉ごと処分する
葉の裏をこまめにチェックし、卵の塊を見つけたら、その葉ごと切り取って処分しましょう。 数百匹の幼虫が孵化するのを未然に防ぐことができるため、非常に効果的な駆除方法です。処分する際は、ビニール袋に入れて口を固く縛るなどして、卵が孵化しないように確実に処理してください。
よくある質問
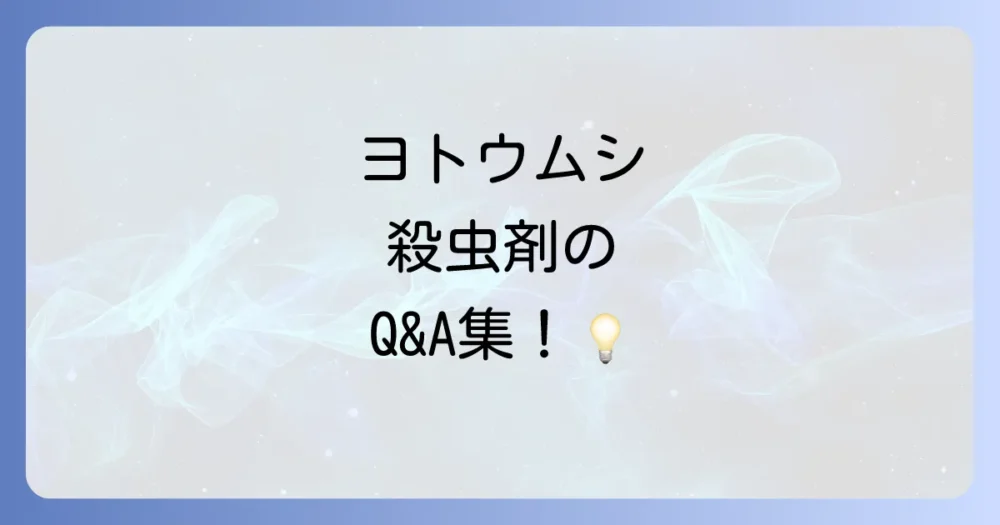
ここでは、ヨトウムシの殺虫剤に関するよくある質問にお答えします。
ヨトウムシの殺虫剤が効かない原因は何ですか?
殺虫剤が効かない場合、いくつかの原因が考えられます。一つは、幼虫が大きく成長しすぎている(老齢幼虫)ことです。 老齢幼虫は薬剤への抵抗力が強くなります。また、同じ系統の殺虫剤を使い続けることで、その薬剤に抵抗性を持つ個体が出現している可能性もあります。 この場合は、作用性の異なる別の殺虫剤(例:有機リン系のオルトランからジアミド系のプレバソンへ変更)を試してみてください。その他、散布量が不足していたり、葉の裏など虫がいる場所に薬剤がかかっていなかったりすることも原因として考えられます。
野菜の収穫間際に使える殺虫剤はありますか?
はい、あります。天然成分や食品由来成分を使用した殺虫剤の中には、野菜の収穫前日まで、あるいは収穫当日まで使用できるものがあります。 例えば、住友化学園芸の「STゼンターリ顆粒水和剤」や「カダンセーフ」などが該当します。 商品のラベルに記載されている「使用時期」を必ず確認し、収穫までの日数(収穫前日数)を守って使用してください。
オルトランはヨトウムシに効きますか?
はい、「オルトラン粒剤」や「オルトラン水和剤」はヨトウムシに効果があります。 オルトランは浸透移行性の殺虫剤で、有効成分が植物全体に行き渡るため、葉を食べるヨトウムシを防除できます。 特に粒剤は、株元にまくだけで効果が持続するため、予防的に使用するのに非常に便利です。
プレバソンはヨトウムシに効きますか?
はい、「プレバソンフロアブル5」はヨトウムシ、特に抵抗性がつきやすいハスモンヨトウなどに高い効果を発揮します。 新規の有効成分を含んでおり、害虫の食害を速やかに止める効果があります。 従来の殺虫剤が効きにくくなったと感じる場合におすすめの薬剤です。
コーヒーかすや木酢液はヨトウムシに効果がありますか?
コーヒーかすや木酢液は、ヨトウムシに対する忌避(きひ)効果、つまり虫を寄せ付けにくくする効果が期待できると言われています。 コーヒーかすを土に混ぜたり、薄めた木酢液を散布したりすることで、ヨトウガが産卵のために近寄りにくくなる可能性があります。ただし、これらは殺虫剤ではないため、すでに発生してしまったヨトウムシを直接駆除する効果は限定的です。あくまで予防策の一つとして試してみるのが良いでしょう。
まとめ
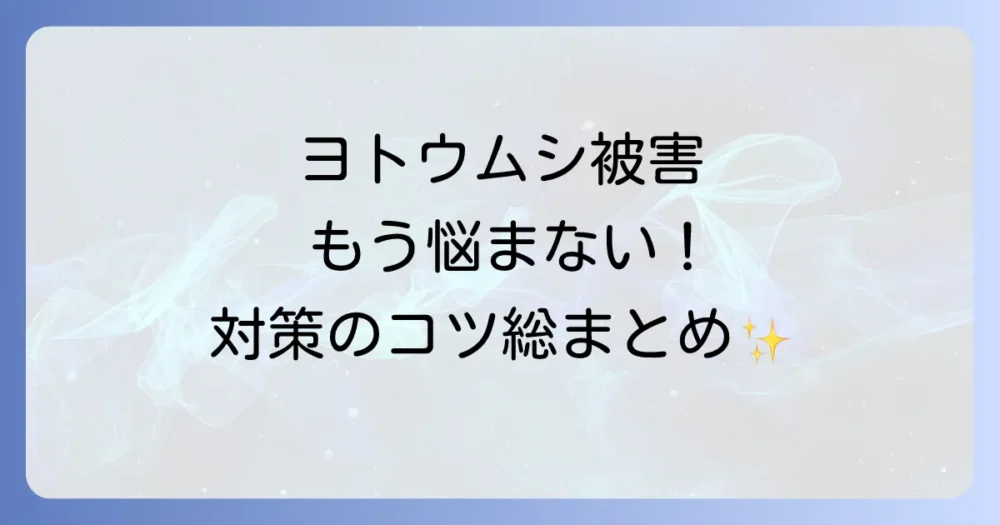
- ヨトウムシは夜行性で、気づかぬうちに葉や新芽を食害する。
- 殺虫剤は「スプレー」「粒剤」「ベイト剤」などタイプで選ぶ。
- 野菜に使う際は「適用作物」と「使用時期」を必ず確認する。
- 即効性ならスプレー、持続性なら粒剤がおすすめ。
- 土に潜む幼虫にはベイト剤(誘殺剤)が効果的。
- 化学農薬に抵抗がある場合は天然由来の殺虫剤を選ぶ。
- 「オルトラン」は予防に、「プレバソン」は抵抗性対策に有効。
- 殺虫剤の散布は、ヨトウムシが活動する夜間が最も効果的。
- 葉の裏に卵を産むため、葉裏への散布が重要。
- 被害を広げないためには、若齢幼虫のうちに駆除することが大切。
- 同じ殺虫剤の連用は避け、ローテーション散布を心がける。
- 防虫ネットは物理的な予防策として非常に効果が高い。
- 雑草の管理や作付け前の耕うんで発生源を減らす。
- 夜間の捕殺や米ぬかトラップなど、薬剤を使わない駆除方法もある。
- 卵を見つけたら葉ごと処分し、孵化を未然に防ぐ。
新着記事