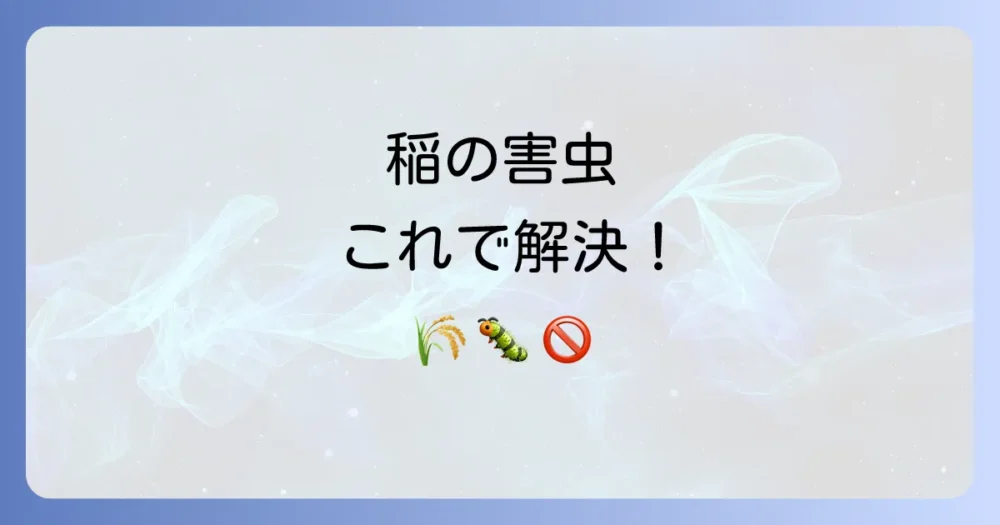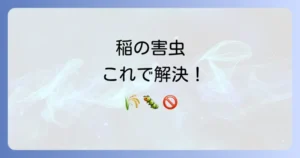丹精込めて育てている稲が、害虫の被害に遭ってしまうのは本当に辛いですよね。収穫量が減ってしまうだけでなく、お米の品質が落ちてしまうこともあります。しかし、がっかりする必要はありません。稲につく害虫の種類や生態を知り、適切な時期に正しい対策を行えば、被害を最小限に抑えることが可能です。本記事では、稲作で特に注意すべき害虫の種類から、具体的な被害のサイン、そして農薬だけに頼らない予防策まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説していきます。
【要注意】稲に大きな被害をもたらす主要害虫
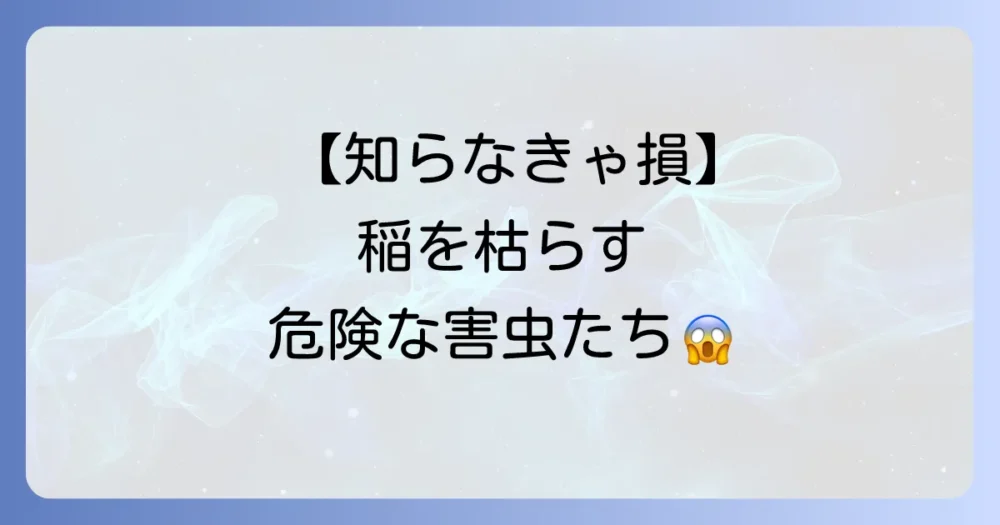
まず、稲作において特に警戒すべき代表的な害虫を知ることが対策の第一歩です。ここでは、特に被害が大きくなりやすい害虫を5種類ピックアップして、その特徴と被害の様子を解説します。ご自身の田んぼで似たような虫や被害を見かけないか、チェックしてみてください。
- ウンカ類(トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ)
- カメムシ類(斑点米の原因)
- ニカメイガ(ニカメイチュウ)
- イネドロオイムシ
- イネミズゾウムシ
ウンカ類(トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ)
ウンカは稲の害虫として古くから知られ、甚大な被害をもたらすことがあります。 体長は5mm程度の小さな虫ですが、稲の茎や葉にストロー状の口を刺して汁を吸い、稲を弱らせてしまいます。 それだけでなく、ウイルス病を媒介することもあり、一度発生するとあっという間に被害が広がるのが特徴です。
主なウンカは、セジロウンカ、トビイロウンカ、ヒメトビウンカの3種類です。 セジロウンカやトビイロウンカは、毎年梅雨の時期に中国大陸から気流に乗って飛来します。 特にトビイロウンカが大量に発生すると、稲が集団で枯れてしまう「坪枯れ」という深刻な被害を引き起こすことがあります。 近年では、従来の農薬が効きにくい「抵抗性ウンカ」も問題となっており、防除がより難しくなっています。
カメムシ類(斑点米の原因)
お米の品質を著しく低下させる原因となるのがカメムシ類です。カメムシは出穂後の稲穂に飛来し、まだ柔らかいお米の汁を吸います。 汁を吸われたお米は、その部分が黒や茶色に変色した「斑点米」となり、お米の等級を落とす直接的な原因となります。 ひどい場合には、お米が実らない不稔籾(ふねんもみ)になることもあり、収量にも大きく影響します。
カメムシは稲だけでなく、田んぼの周りの畦畔(あぜ)や休耕田のイネ科雑草で繁殖します。 そのため、田んぼの中だけでなく、周辺の環境管理が非常に重要な対策となります。出穂直前に草刈りをすると、かえってカメムシを田んぼに追い込んでしまうため、草刈りのタイミングには注意が必要です。
ニカメイガ(ニカメイチュウ)
ニカメイガは、その幼虫が稲の茎の中に侵入して内部から食害する厄介な害虫です。 茎の中を食べられると、稲は栄養や水分を送れなくなり、芯が枯れてしまったり(心枯れ)、出穂しても穂が白く枯れてしまう「白穂(しらほ)」になったりします。 被害を受けた茎を触ると、中が空っぽになっていることで気づくこともあります。
ニカメイガは年に2回発生することが多く、第1世代は分げつ期の稲に、第2世代は出穂期以降の稲に被害を与えます。 幼虫は収穫後の稲わらや刈り株の中で越冬するため、収穫後の田んぼの管理が翌年の発生を抑える鍵となります。
イネドロオイムシ
イネドロオイムシは、成虫も幼虫も稲の葉を食べる害虫です。特に幼虫は、自分のフンを背負って泥のように見えることからこの名前がついています。 葉の表面をかすり状に食害し、被害が進むと葉が白っぽくなります。 多発すると田んぼ全体が白く見えるほどになり、光合成が妨げられて生育が悪くなり、収量の減少につながります。
特に冷涼な地域や、田植えが早い場合に発生が多い傾向があります。 幼虫は乾燥に弱いため、5月〜6月にかけて低温で雨が多いと発生しやすくなるので、天候にも注意が必要です。
イネミズゾウムシ
イネミズゾウムシは、田植え直後の若い苗に被害を与える初期害虫の代表格です。 成虫は稲の葉を線状に食害し、白い筋のような跡を残します。 しかし、より深刻なのは幼虫による根の被害です。 幼虫は土の中で根を食べてしまうため、ひどい場合には稲が水面に浮いてしまったり、枯れてしまったりすることもあります。
成虫は田んぼの周りの山林などで越冬し、田植えが始まると水田に侵入してきます。 そのため、田んぼの畦畔際から被害が広がることが多いのが特徴です。 苗が小さいうちに被害を受けると回復が難しくなるため、移植初期の防除が非常に重要になります。
【時期別】稲の生育ステージで注意すべき害虫カレンダー
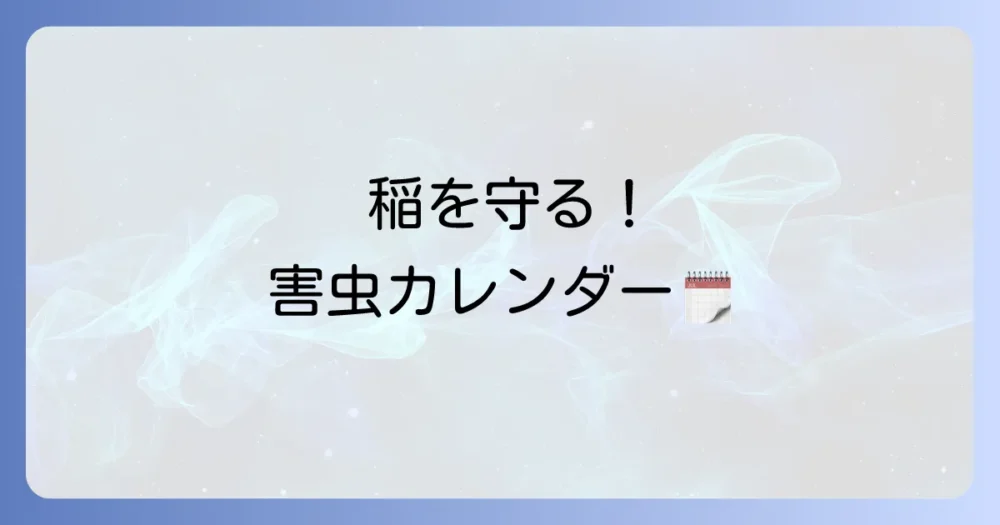
害虫対策を効果的に行うためには、「いつ」「どの害虫が」発生しやすいのかを知っておくことが大切です。稲の生育ステージごとに、特に注意が必要な害虫をまとめました。ご自身の田んぼの状況と照らし合わせながら、防除計画の参考にしてください。
- 田植え前後(初期)に発生しやすい害虫
- 生育期(中期)に発生しやすい害虫
- 出穂期以降(後期)に発生しやすい害虫
田植え前後(初期)に発生しやすい害虫
田植えから稲が根付くまでの初期段階は、苗がまだ弱々しく、害虫の被害を受けやすい非常にデリケートな時期です。この時期の被害は、その後の生育に大きく影響を及ぼします。
特に注意したいのがイネミズゾウムシとイネドロオイムシです。 イネミズゾウムシは成虫が葉を食べ、幼虫が根を食害します。 根が被害を受けると、養分をうまく吸収できなくなり、最悪の場合枯れてしまいます。 イネドロオイムシも成虫・幼虫ともに葉を食害し、多発すると田んぼ一面が白くなるほどの被害が出ることがあります。 また、地域によってはスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)が柔らかい苗を食べてしまう被害も深刻です。 この時期は、育苗箱への薬剤処理(箱施薬)で、これらの初期害虫をまとめて防除するのが一般的で効果的な方法です。
生育期(中期)に発生しやすい害虫
稲が順調に分げつし、青々と茂ってくる生育期(中期)には、海外から飛来してくる害虫への警戒が必要になります。この時期の主役は、なんといってもウンカ類です。
セジロウンカやトビイロウンカは、梅雨の時期に中国大陸から飛来し、水田で世代を繰り返しながら増殖します。 7月下旬から8月中旬にかけて密度が高くなる傾向があり、吸汁による直接的な被害のほか、ウイルス病を媒介するリスクもあります。 また、コブノメイガの幼虫もこの時期に発生し、稲の葉を巻いて内側から食害します。 葉を食べられると光合成の能力が落ち、お米の登熟に影響が出ます。 窒素肥料が多いと稲が軟弱になり、これらの害虫の被害を受けやすくなるため、適切な施肥管理も重要な対策の一つです。
出穂期以降(後期)に発生しやすい害虫
稲が穂を出し、お米が実り始める後期は、収量と品質を決定づける最も重要な時期です。この時期に被害を受けると、一年間の努力が水の泡になりかねません。
最大の敵は、お米の品質を直接的に落とすカメムシ類です。 出穂期から乳熟期にかけて田んぼに飛来し、柔らかい籾を吸汁して斑点米を発生させます。 また、夏に増殖したトビイロウンカが9月から10月にかけて大発生し、稲を根元から枯らす「坪枯れ」を引き起こす危険性も高まります。 この時期の防除は、穂揃い期(ほ場の8〜9割が出穂した時期)の薬剤散布が基本となりますが、発生が多い場合は追加の防除も必要です。 周辺の草刈りなど、カメムシの発生源対策と薬剤防除を組み合わせることが、高品質米を収穫するための鍵となります。
稲の害虫対策の基本!今日からできる予防と駆除の方法
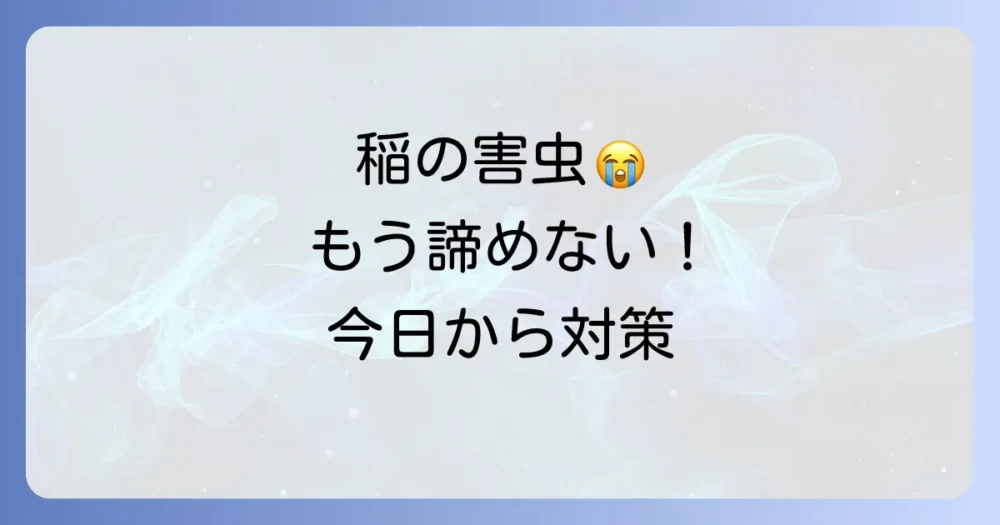
害虫被害を防ぐためには、発生してからの駆除だけでなく、日頃からの予防が何よりも重要です。ここでは、農薬だけに頼らない「耕種的防除」、効果的な「薬剤防除」、そして自然の力を借りる「生物的防除」の3つの側面から、具体的な対策方法を解説します。
- 耕種的防除|農薬に頼らない予防の第一歩
- 薬剤(農薬)による防除|効果的な使い方と注意点
- 生物的防除|天敵を味方につける方法
耕種的防除|農薬に頼らない予防の第一歩
耕種的防除とは、栽培管理の方法を工夫することで、害虫が発生しにくい環境を作る取り組みのことです。農薬の使用を減らすことにもつながる、環境にやさしい基本的な対策です。
畦畔・周辺の草刈り
斑点米カメムシ類は、田んぼの周りの雑草地で増殖し、稲が出穂するタイミングで水田に侵入してきます。 そのため、畦畔や休耕地の草刈りは非常に有効な対策です。 ただし、タイミングが重要で、出穂の10日〜15日前に一度行い、その後雑草が再び穂をつける前にもう一度行うのが理想的です。 逆に出穂直前に草刈りをすると、雑草にいたカメムシを田んぼに追い込んでしまうことになるので絶対に避けてください。
稲わらの適切な処理と耕起
ニカメイガの幼虫は、収穫後の稲わらや刈り株で越冬します。 そのため、被害が多かった田んぼでは、収穫後にできるだけ早く稲わらをすき込み、土の中で腐熟させることが翌年の発生源を減らすのに効果的です。 秋のうちに深く耕起し、さらに冬の間に田んぼに水を張る「冬季湛水」を行うと、越冬する幼虫の生存率を劇的に下げることができます。 福井県の試験では、耕起と冬季湛水によって越冬幼虫を88%死滅させ、翌年の被害を半減させる効果が報告されています。
適切な施肥管理
窒素肥料の与えすぎは、稲の茎葉を軟弱にし、病害虫の被害を受けやすくする原因となります。 特にコブノメイガやイネドロオイムシは、窒素過多で葉色が濃い稲を好む傾向があります。 肥料を控えめにすることで、稲自体が丈夫になり、害虫の発生を抑制することができます。 また、ケイ酸質肥料を施用すると稲の組織が硬くなり、ニカメイガの幼虫が食入しにくくなるという効果も報告されています。
抵抗性品種の選択
害虫の被害を受けにくい「抵抗性品種」を選ぶことも、有効な対策の一つです。 例えば、海外から飛来するトビイロウンカに対して抵抗性を持つ品種が開発されています。 また、斑点米カメムシ類の中でも、内外の頴(もみがら)の隙間から吸汁するタイプのカメムシに対しては、割れ籾が発生しにくい品種を選ぶことで被害を軽減できる場合があります。 ご自身の地域で発生しやすい害虫の種類に合わせて、品種選びを検討するのも良いでしょう。
薬剤(農薬)による防除|効果的な使い方と注意点
害虫が多発した場合や、耕種的防除だけでは被害を防ぎきれない場合には、薬剤による防除が必要になります。農薬は正しく使えば非常に効果的ですが、使い方を誤ると効果がなかったり、環境に影響を与えたりすることもあるため、注意が必要です。
育苗箱施用剤での初期防除
田植えと同時に、長期間効果が持続する殺虫剤を苗箱に施用する方法です。 この方法は、田植え後の薬剤散布の手間を省きつつ、イネミズゾウムシやイネドロオイムシ、初期のウンカ類など、移植初期に発生する害虫をまとめて防除できるため、現在広く普及しています。 薬剤の成分が稲に吸収され、稲を食べる害虫を退治する仕組みです。 どの害虫をターゲットにするかによって選ぶ薬剤が変わってくるので、自分の地域で問題となる害虫に合った薬剤を選びましょう。
本田散布剤での追加防除
育苗箱施用剤の効果が切れてくる生育中期以降や、カメムシ類のように出穂期以降に発生する害虫に対しては、田んぼ全体に薬剤を散布する「本田散布」を行います。 特に斑点米カメムシ対策では、穂揃い期(圃場の約8〜9割が出穂した時期)の防除が重要です。 ウンカやカメムシの発生が多い年には、さらに7〜10日後に追加で散布することで、より高い効果が期待できます。 近年では、ラジコンヘリやドローンによる散布も普及しており、効率的な防除が可能になっています。
農薬使用時の注意点
農薬を使用する際は、必ずラベルをよく読み、記載されている使用量、使用時期、使用回数などの決まりを厳守してください。 対象となる作物や害虫以外には使用できません。また、同じ系統の薬剤を連続して使用すると、その薬剤が効かない「抵抗性」を持つ害虫が現れる原因となります。 作用の異なる系統の薬剤を順番に使う「ローテーション散布」を心がけることが、薬剤の効果を長持ちさせる上で重要です。
生物的防除|天敵を味方につける方法
田んぼには、害虫を食べてくれる「益虫」もたくさん生息しています。これらの天敵の力を借りて害虫を抑制するのが生物的防除です。農薬の使用を減らし、田んぼの生態系を豊かに保つことにも繋がります。
クモやトンボなどの益虫を活用する
田んぼで見かけるクモは、ウンカなどの害虫を捕食してくれる非常に重要な天敵です。 水面を徘徊するタイプや、稲の株間に巣を張るタイプなど、様々な種類のクモが立体的に害虫を捕らえてくれます。 しかし、クモは農薬に弱いものが多いため、薬剤散布によって天敵であるクモが減ってしまい、結果的に害虫が増えてしまうという皮肉な結果を招くこともあります。 害虫だけに効果があり、天敵への影響が少ない薬剤を選ぶなど、天敵を保護する視点も大切です。アキアカネなどのトンボも、ウンカなどを捕食してくれる心強い味方です。
アイガモ農法について
有機農法などで知られるアイガモ農法も、生物的防除の代表的な例です。 田んぼに放たれたアイガモは、雑草だけでなく、水面に落ちたウンカなどの害虫も食べてくれます。 アイガモが水中を泳ぎ回ることで水を濁らせ、雑草の発生を抑える効果もあります。また、翌年のジャンボタニシの密度を大幅に減らす効果も報告されており、害虫と雑草の両方を抑えることができる一石二鳥の方法と言えるでしょう。
【農薬を使わない】自然農法・有機栽培向けの害虫対策
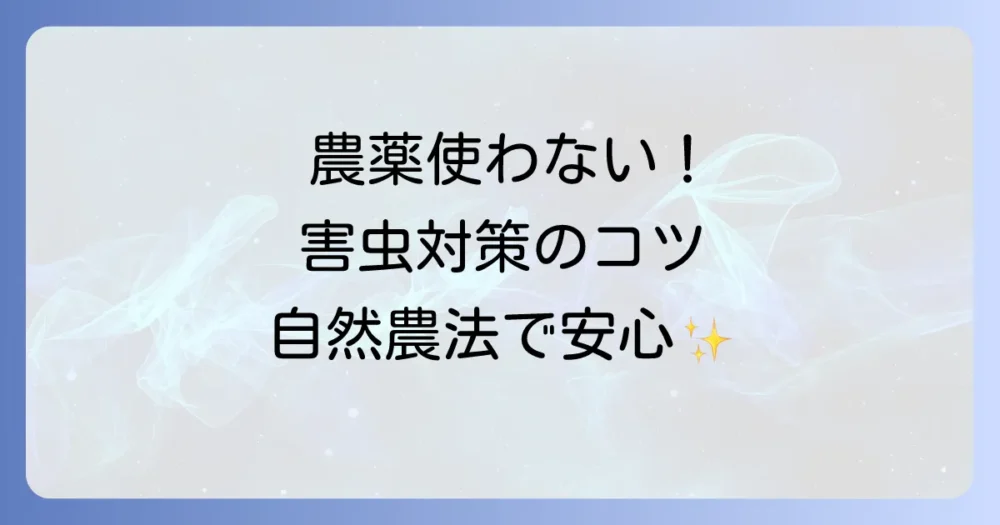
「できるだけ農薬は使いたくない」と考える方も多いでしょう。ここでは、有機栽培や自然農法に取り組む方向けに、農薬を使わない害虫対策をいくつかご紹介します。手間はかかりますが、環境への負荷が少ない持続可能な方法です。
性フェロモントラップの活用(ニカメイガ対策)
ニカメイガのメスがオスを誘い出すために出す匂い(性フェロモン)を利用した防除方法があります。 この性フェロモン剤を田んぼに設置すると、田んぼ中がメスの匂いで満たされます。すると、交尾相手を探すオスが混乱して本物のメスを見つけられなくなり、結果的に交尾・産卵を妨害することができます。 これにより、次世代のニカメイガの数を減らし、被害を抑制します。
ケイ酸資材で稲を硬くする
稲にケイ酸を吸収させると、植物の細胞壁が強化され、稲自体が物理的に硬くなります。 稲の茎が硬くなることで、ニカメイガの幼虫が茎の中に潜り込みにくくなり、食害を減らす効果が期待できます。 これは、稲が本来持っている防御力を高めてあげるという考え方に基づく対策です。
物理的防除(畦畔板の設置など)
害虫の侵入を物理的に防ぐ方法もあります。例えば、イネミズゾウムシは主に畦畔から歩いて水田に侵入してくるため、田植え直後に畦畔際に畦畔板(波板など)を設置することで、侵入を抑制する効果があります。 畦畔板は水面から10〜15cm程度の高さになるように設置します。 侵入経路を断つという、非常に直接的で分かりやすい対策です。
冬季湛水による害虫抑制
収穫後から冬にかけて田んぼに水を張っておく「冬季湛水」は、土の中で越冬するニカメイガの幼虫や、イナゴの卵などを水没させて死滅させる効果があります。 また、雑草の発生を抑える効果や、冬の間も田んぼに多様な生き物が生息する環境を作る効果も期待でき、総合的な田んぼの地力向上にもつながる方法です。
よくある質問
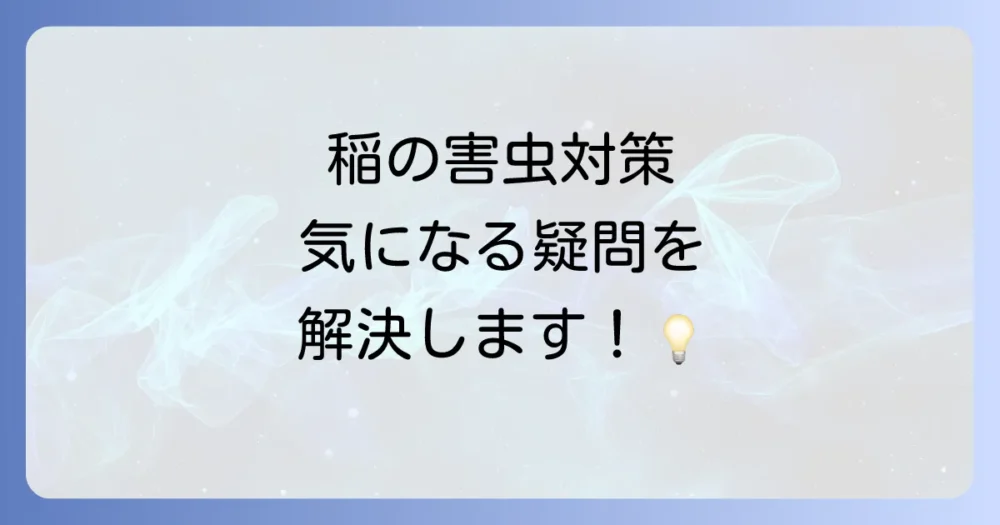
稲の害虫対策に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。
稲の害虫はどこから来るの?
害虫の発生源は様々です。ウンカ類(トビイロウンカ、セジロウンカ)のように、毎年梅雨時期に中国大陸など海外から気流に乗って長距離を飛んでくる「飛来性害虫」がいます。 一方で、ニカメイガのように収穫後の稲わらや株で越冬したり、イネミズゾウムシのように田んぼ周辺の山林などで越冬したりして、翌年また田んぼに現れる害虫もいます。 カメムシ類は、近くの雑草地が発生源となります。
害虫に強い稲の品種はありますか?
はい、あります。研究機関によって、特定の害虫に対する「抵抗性品種」が開発されています。 例えば、トビイロウンカの増殖を抑える抵抗性を持つ品種や、斑点米の原因となるカメムシの吸汁を受けにくい(割れ籾になりにくい)品種などがあります。 地域のJAや農業指導機関に相談し、ご自身の地域で問題となっている害虫に合わせた品種を選ぶのがおすすめです。
農薬はいつ撒くのが効果的ですか?
農薬を撒くタイミングは、対象とする害虫と農薬の種類によって大きく異なります。初期害虫対策であれば田植え時の育苗箱施用が効果的です。 カメムシ対策であれば、稲の穂が出揃う「穂揃い期」が重要な防除時期です。 害虫の発生状況をよく観察し、「これ以上増えると被害が大きくなる」というタイミングで散布するのが基本です。 各地域の病害虫防除所が発表する発生予察情報などを参考に、適切な時期に防除を行いましょう。
斑点米カメムシに効く薬は?
斑点米カメムシ類に効果のある農薬は多数販売されています。成分名で言うと、ジノテフラン(商品名:スタークル、アルバリンなど)やクロチアニジン(商品名:ダントツなど)といったネオニコチノイド系の薬剤や、エトフェンプロックス(商品名:トレボンなど)などが広く使われています。 粒剤を水田に散布するタイプや、液剤・粉剤を穂に直接散布するタイプなどがありますので、使いやすいものを選びましょう。
ウンカが大量発生する原因は何ですか?
ウンカの大量発生にはいくつかの要因が絡んでいます。まず、海外の発生源(中国南部やベトナムなど)でウンカが増えやすい稲の品種が作付けされると、日本への飛来数が増える傾向にあります。 また、飛来後の気象条件(高温・多湿)も増殖に影響します。近年では、特定の殺虫剤が効きにくい「抵抗性ウンカ」が増えていることも、防除を難しくし、結果として大発生につながる一因となっています。
まとめ
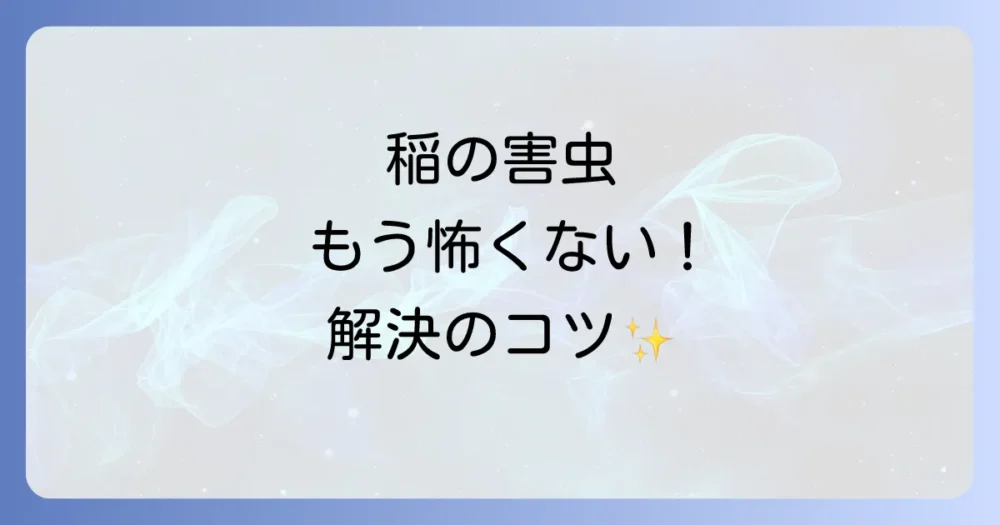
- 稲の主要害虫はウンカ、カメムシ、ニカメイガなど。
- ウンカは吸汁やウイルス媒介で甚大な被害をもたらす。
- カメムシは米の品質を落とす斑点米の直接的な原因。
- ニカメイガは幼虫が茎に侵入し、稲を内側から枯らす。
- イネミズゾウムシやイネドロオイムシは田植え初期に要注意。
- 害虫対策は発生時期に合わせた防除計画が重要。
- 田植え初期は育苗箱施用剤での予防が効果的。
- 出穂期はカメムシ対策の薬剤散布が必須。
- 農薬に頼らない耕種的防除が基本となる。
- 畦畔の草刈りはカメムシの発生源対策に有効。
- 収穫後の耕起や冬季湛水は越冬害虫を減らす。
- 窒素肥料のやりすぎは害虫の発生を助長する。
- 農薬はラベルを確認し、適正使用を徹底する。
- クモなどの天敵を保護することも大切な対策。
- 害虫の生態を理解し、総合的な対策を心がけることが重要。
新着記事