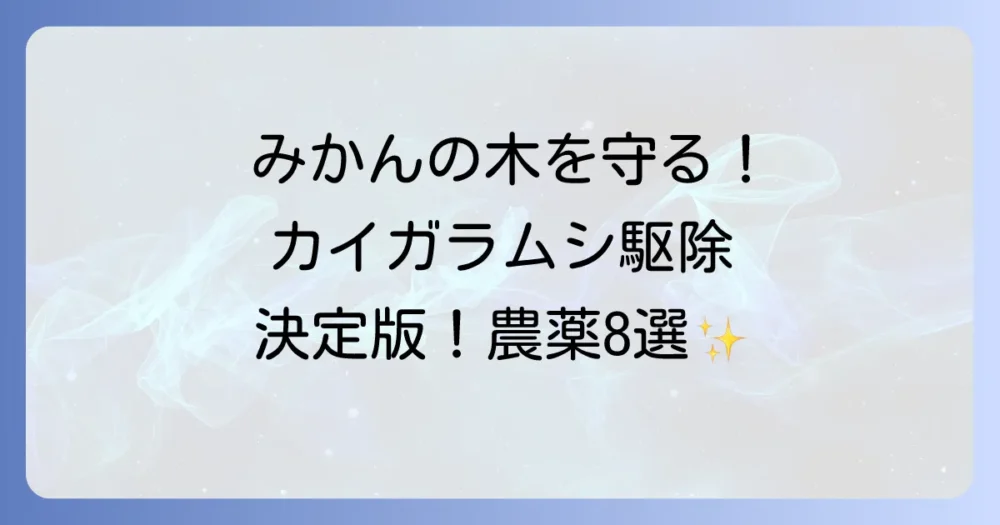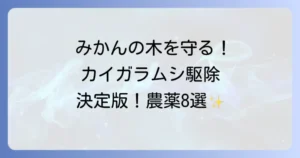大切に育てているみかんの木に、白い綿のようなものや、茶色い貝殻のようなものがビッシリ…。その正体は、みかんの大敵「カイガラムシ」かもしれません。カイガラムシは見た目が不快なだけでなく、みかんの生育を妨げ、最悪の場合、木を枯らしてしまうこともある厄介な害虫です。この記事を読んでいるあなたは、「どうにかしてこのカイガラムシを駆除したい!」と強く思っていることでしょう。ご安心ください。本記事では、みかんのカイガラムシに効果的な薬剤の選び方から、正しい使い方、駆除の最適な時期まで、あなたの悩みを解決するための情報を余すところなく解説します。
みかんの天敵!カイガラムシの正体と被害
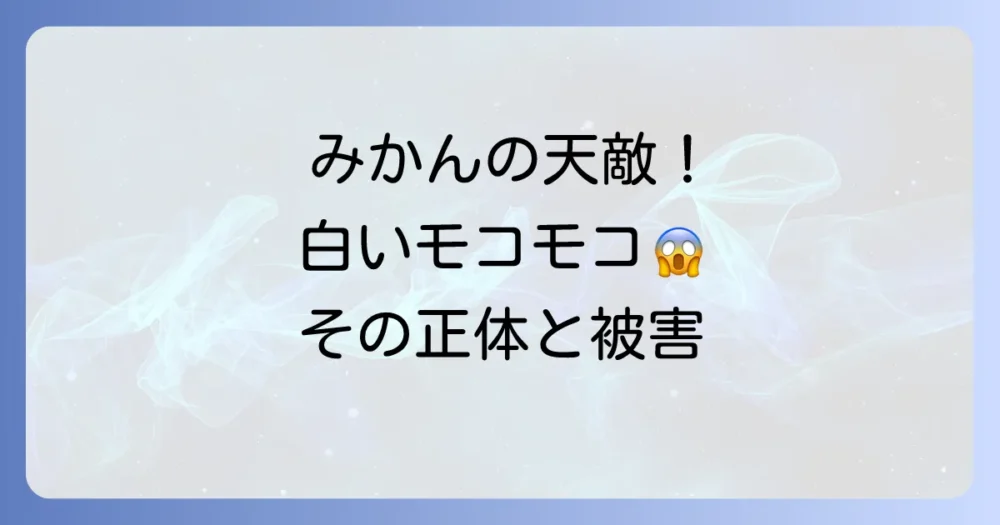
まずは敵を知ることから始めましょう。カイガラムシは非常に種類が多く、見た目も様々ですが、みかんに寄生する主な種類と、それらが引き起こす被害について解説します。カイガラムシの被害を知ることで、早期発見と対策の重要性がより理解できるはずです。
本章では、以下の内容について詳しく見ていきます。
- カイガラムシの生態とみかんに発生しやすい種類
- 放置は危険!カイガラムシが引き起こす2つの重大な被害
カイガラムシの生態とみかんに発生しやすい種類
カイガラムシは、カメムシやアブラムシの仲間に分類される昆虫です。その名の通り、成虫になると硬い殻(カイガラ)を被る種類が多いのが特徴。体長は2mmから10mm程度と小さいですが、繁殖力が非常に強く、あっという間に増えてしまいます。 みかんの木に寄生し、枝や葉、果実から樹液を吸って栄養を奪います。
みかんに特に発生しやすいのは、「ヤノネカイガラムシ」や「ミカンコナカイガラムシ」などです。 ヤノネカイガラムシは矢じりのような形をした茶色い殻を持ち、ミカンコナカイガラムシは白い粉で覆われているのが特徴です。これらのカイガラムシは、一度発生すると薬剤が効きにくく、非常に厄介な存在として知られています。
放置は危険!カイガラムシが引き起こす2つの重大な被害
カイガラムシの被害は、単に樹液を吸われるだけではありません。放置すると、より深刻な二次被害を引き起こす可能性があります。
- すす病の誘発
カイガラムシは、甘い排泄物を出します。この排泄物を栄養源として「すす病菌」というカビが繁殖し、葉や果実が黒いすすで覆われたようになってしまうのです。 これが「すす病」です。すす病になると、光合成が妨げられてみかんの生育が悪くなるだけでなく、果実の見た目も悪くなり商品価値が大きく下がってしまいます。 - こうやく病の誘発
もう一つの深刻な病気が「こうやく病」です。 これは、カイガラムシが特定のカビと共生することで引き起こされ、枝や幹に灰色や茶褐色のフェルト状のカビが広がります。見た目が膏薬(こうやく)を貼ったように見えることからこの名が付きました。こうやく病が進行すると、枝が衰弱し、最終的には枯れてしまうこともあります。
このように、カイガラムシはみかんの木にとってまさに天敵。見つけたらすぐに対処することが何よりも重要です。
【最重要】カイガラムシ駆除は散布時期がすべて!
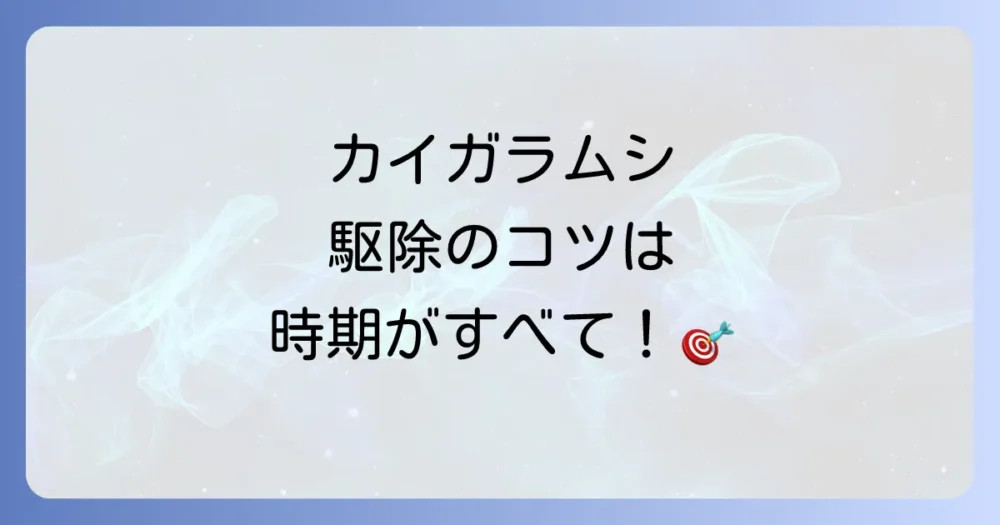
カイガラムシの駆除で最も大切なことは、薬剤を散布するタイミングです。なぜなら、カイガラムシは成長段階によって薬剤の効き目が全く異なるからです。この章を読んで、最大の効果を得られる散布時期をしっかりと押さえましょう。
本章のポイントは以下の通りです。
- 薬剤が効きやすい幼虫の発生時期を狙う
- 越冬する成虫を叩く冬期防除の重要性
薬剤が効きやすい幼虫の発生時期を狙う(5月~8月)
カイガラムシの成虫は、硬い殻やロウ物質で体を覆っているため、多くの薬剤が効きにくい状態になっています。 そのため、駆除の最大のチャンスは、殻を被る前の幼虫の時期です。幼虫はまだ体が柔らかく、薬剤に対する抵抗力も弱いため、この時期に散布することで効率的に駆除できます。
みかんに付くヤノネカイガラムシの場合、幼虫は年に2〜3回発生します。主な発生時期は以下の通りです。
- 第1世代:5月上旬~7月下旬(ピークは6月上旬~中旬)
- 第2世代:7月中旬~10月上旬(ピークは8月中旬~下旬)
特に、第1世代の発生ピークである6月中旬頃は、防除の最も重要な時期と言えるでしょう。このタイミングを逃さずに薬剤を散布することが、年間の発生数を抑える鍵となります。
越冬する成虫を叩く冬期防除の重要性(12月~1月)
幼虫時期の駆除と並行して、もう一つ非常に重要なのが冬の防除です。カイガラムシの多くは成虫の姿で越冬します。 この越冬している成虫を駆除することで、春先の発生源を大幅に減らすことができます。
冬期防除には、「マシン油乳剤」という薬剤が非常に効果的です。 マシン油乳剤は、カイガラムシの体を油膜で覆い、呼吸をできなくさせて窒息死させるという物理的な作用で効果を発揮します。 そのため、薬剤抵抗性がつきにくいという大きなメリットがあります。
散布の適期は、みかんの木が休眠期に入る12月下旬から1月上旬頃です。 厳寒期を避け、天気の良い暖かい日中に散布するのがコツです。 この冬のひと手間が、春以降のカイガラムシの発生を劇的に抑えてくれます。
みかんのカイガラムシに効く!タイプ別おすすめ薬剤8選
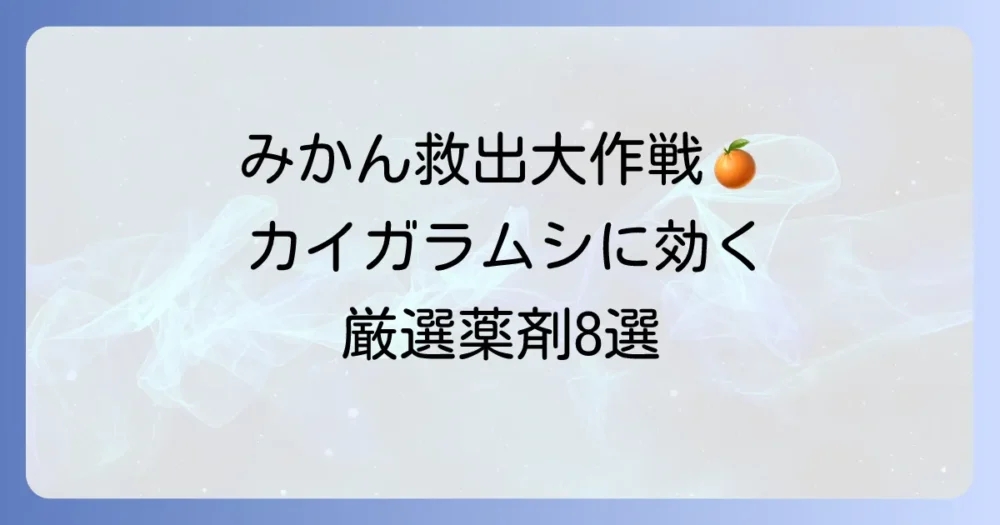
「散布時期は分かったけど、具体的にどの薬剤を使えばいいの?」という疑問にお答えします。ここでは、ホームセンターなどで比較的手に入りやすく、効果の高い薬剤をタイプ別に8種類厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合った薬剤を選んでください。
ご紹介する薬剤は以下の通りです。
- 【基本の薬剤】マシン油乳剤
- 【手軽さNo.1】カイガラムシエアゾール
- 【浸透して効く】GFオルトラン水和剤・粒剤
- 【プロも使う】スタークル顆粒水溶剤
- 【ローテーションに】スミチオン乳剤
- 【雨に強い】トランスフォームフロアブル
- 【有機JAS適合】石灰硫黄合剤
- 【予防にも使える】アプロード水和剤
【基本の薬剤】マシン油乳剤
冬期防除の主役であり、カイガラムシ対策の基本となる薬剤です。 石油から精製された油を主成分とし、害虫を油膜で覆って窒息させます。 物理的に作用するため、薬剤抵抗性が発達しにくいのが最大の強みです。 有機JAS適合の製品もあり、環境に配慮したい方にもおすすめです。
使い方とポイント
主に冬期(12月~1月)に使用します。 希釈倍率は製品によって異なりますが、95%製剤なら30~45倍程度が一般的です。 樹全体がしっかり濡れるように、枝の裏や幹まで丁寧に散布するのがコツです。 ただし、気温が低い日や樹勢が弱っている時の使用は薬害の原因になるため避けましょう。
- 主な商品名: マシン油乳剤95(クミアイ化学)、キング95マシン(住友化学園芸)
- 有効成分: マシン油
- 剤型: 乳剤
【手軽さNo.1】カイガラムシエアゾール
「希釈したり噴霧器を用意したりするのは面倒…」という方には、スプレータイプのエアゾール剤がおすすめです。住友化学園芸から販売されている「カイガラムシエアゾール」は、見つけたカイガラムシに直接噴射するだけで手軽に駆除できます。 2つの有効成分が配合されており、殺虫効果が約1ヶ月持続するのも嬉しいポイントです(ルビーロウムシの場合)。 ジェット噴射で高い枝にも薬剤が届きます。
使い方とポイント
カイガラムシが発生している枝や幹に、直接スプレーします。夏場の幼虫はもちろん、冬の越冬成虫にも効果があります。 ただし、広範囲に散布するには不向きなので、発生初期や部分的な駆除に適しています。葉にかけすぎると薬害の恐れがあるので注意が必要です。
- 主な商品名: カイガラムシエアゾール (住友化学園芸)
- 有効成分: クロチアニジン、フェンプロパトリン
- 剤型: エアゾール剤
【浸透して効く】GFオルトラン水和剤・粒剤
オルトランは「浸透移行性」という特徴を持つ殺虫剤です。薬剤が葉や根から吸収されて植物全体に行き渡り、樹液を吸ったカイガラムシを内側から退治します。 そのため、薬剤が直接かかりにくい葉の裏や枝の隙間に隠れている害虫にも効果を発揮します。水で薄めて散布する水和剤と、株元に撒くだけの粒剤があります。
使い方とポイント
水和剤は幼虫の発生時期に散布します。粒剤は植え付け時や生育期に株元に散布することで、予防的な効果も期待できます。 幅広い害虫に効果がありますが、同じ薬剤を使い続けると抵抗性がつく可能性があるので、他の薬剤とのローテーション散布がおすすめです。
- 主な商品名: GFオルトラン水和剤、GFオルトラン粒剤 (住友化学園芸)
- 有効成分: アセフェート
- 剤型: 水和剤、粒剤
【プロも使う】スタークル顆粒水溶剤
スタークルは、プロの農家も使用する浸透移行性の殺虫剤です。 有効成分のジノテフランは、カイガラムシだけでなくアブラムシなど幅広い害虫に高い効果を示します。速効性があり、散布後すぐに効果が現れ始めるのが特徴です。残効性にも優れています。
使い方とポイント
幼虫の発生時期(6月や8月)に、水で希釈して散布します。 浸透移行性なので、葉の表から散布しても裏にいる害虫に効果があります。みかんでは収穫前日まで使用できるため、収穫期に近い時期の防除にも活用できます(使用回数には注意)。
- 主な商品名: スタークル顆粒水溶剤 (三井化学アグロ)、アルバリン顆粒水溶剤 (日本農薬)
- 有効成分: ジノテフラン
- 剤型: 顆粒水和剤
【ローテーションに】スミチオン乳剤
スミチオンは、有機リン系の殺虫剤で、非常に古くから使われている定番の農薬です。 幅広い害虫に効果があり、速効性に優れています。カイガラムシの幼虫にも有効で、薬剤ローテーションの一角として重宝します。ホームセンターなどでも入手しやすく、価格が比較的安価なのも魅力です。
使い方とポイント
幼虫の発生時期に水で希釈して散布します。独特の匂いがあるため、散布する際は近隣への配慮が必要です。また、同じ有機リン系の薬剤(例:マラソン、エルサン)を連続して使用すると抵抗性がつきやすくなるため、系統の異なる薬剤と組み合わせて使いましょう。
- 主な商品名: スミチオン乳剤 (住友化学園芸)
- 有効成分: MEP(フェニトロチオン)
- 剤型: 乳剤
【雨に強い】トランスフォームフロアブル
比較的新しいタイプの殺虫剤で、雨に強く、効果の持続性(残効性)が高いのが大きな特徴です。 薬剤が葉の内部に浸透するため、散布後に雨が降っても効果が落ちにくいです。カイガラムシの発生期間が長期化する傾向にある近年、頼りになる薬剤の一つです。
使い方とポイント
第1世代幼虫の発生時期(6月頃)に散布するのが基本です。 散布後、速やかに葉内に浸透するため、梅雨時期の防除にも適しています。効果が長持ちするため、散布回数を減らせる可能性もあります。
- 主な商品名: トランスフォームフロアブル (コルテバ・アグリサイエンス)
- 有効成分: スルホキサフロル
- 剤型: フロアブル剤
【有機JAS適合】石灰硫黄合剤
マシン油乳剤と同様に、古くから使われている農薬で、殺虫・殺菌の両方の効果があります。 有機JAS栽培でも使用が認められているため、オーガニック栽培を目指す方には重要な選択肢となります。 カイガラムシの越冬対策として、休眠期に使用されます。
使い方とポイント
みかんの木が完全に葉を落とした後の休眠期(1月~2月頃)に使用します。 強いアルカリ性で薬害が出やすいため、使用時期や希釈倍率は厳守する必要があります。また、独特の強い硫黄臭があり、噴霧器などの金属を腐食させる性質があるため、取り扱いには十分な注意が必要です。
- 主な商品名: 石灰硫黄合剤
- 有効成分: 多硫化カルシウム
- 剤型: 液剤
【予防にも使える】アプロード水和剤
アプロードは、昆虫の脱皮を阻害して死に至らせる「昆虫成長制御剤(IGR剤)」というタイプの薬剤です。 速効性はありませんが、次の世代の発生を抑える予防的な効果が期待できます。カイガラムシの幼虫が脱皮するのを妨げることで、成虫になるのを防ぎます。
使い方とポイント
幼虫の発生初期に散布するのが最も効果的です。すでにいる成虫には効果がありませんが、幼虫に対しては長期間効果が持続します。 殺虫作用が異なるため、他の殺虫剤とのローテーションに組み込むことで、薬剤抵抗性の発達を抑える効果も期待できます。
- 主な商品名: アプロード水和剤 (日本農薬)
- 有効成分: ブプロフェジン
- 剤型: 水和剤
なぜ?カイガラムシに薬剤が効かない原因と対策
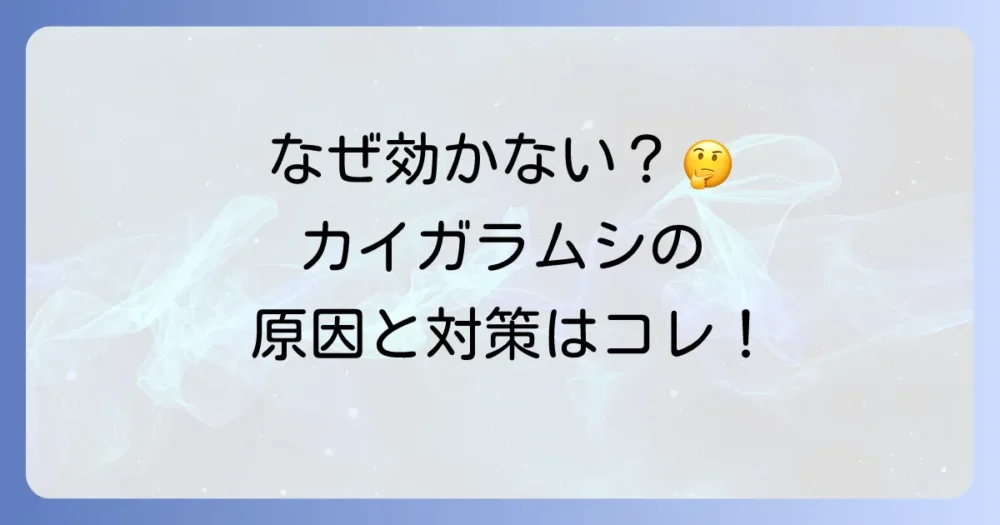
「薬剤を散布したのに、カイガラムシが全然減らない…」そんな経験はありませんか?カイガラムシは防除が難しい害虫であり、ただ薬剤を撒くだけでは効果が出ないことがあります。ここでは、薬剤が効かない主な原因と、その対策について解説します。
考えられる原因は以下の3つです。
- 原因1:成虫には薬剤が効きにくい
- 原因2:散布時期や方法が間違っている
- 原因3:薬剤抵抗性がついている
原因1:成虫には薬剤が効きにくい
最も多い原因が、駆除の対象が成虫であることです。前述の通り、カイガラムシの成虫は硬い殻やロウ状の物質で体をガードしています。 このバリアが薬剤の浸透を妨げるため、多くの殺虫剤が効果を発揮できません。 卵も同様に殻に守られており、薬剤はほとんど効きません。
対策:
対策はシンプルです。薬剤が効きやすい幼虫の時期(5月~8月)を狙って散布すること。これが鉄則です。 成虫に対しては、後述する歯ブラシなどでこすり落とす物理的な駆除が有効です。冬期であれば、マシン油乳剤で窒息させる方法が効果的です。
原因2:散布時期や方法が間違っている
せっかく効果的な薬剤を選んでも、散布のタイミングや方法が不適切では効果が半減してしまいます。例えば、幼虫の発生ピークを過ぎてから散布しても、多くが成虫になってしまっていて手遅れです。 また、葉の表面だけに散布して、カイガラムシが密集している枝や葉の裏に薬剤がかかっていないケースもよくあります。
対策:
地域の病害虫発生予察情報などを参考に、正確な幼虫の発生時期を把握しましょう。散布する際は、カイガラムシが潜んでいる枝の付け根や幹、葉の裏側まで、ムラなく丁寧に薬剤がかかるように心がけてください。 マシン油乳剤などは特に、虫体への付着が効果を左右するため、十分な量を散布することが重要です。
原因3:薬剤抵抗性がついている
毎年同じ系統の薬剤を使い続けていると、その薬剤が効きにくい「薬剤抵抗性」を持ったカイガラムシが現れることがあります。 これは、特定の殺虫成分に対して耐性を持ってしまった個体だけが生き残り、子孫を増やすことで起こります。特に世代交代が早い害虫では問題になりやすいです。
対策:
薬剤抵抗性を防ぐためには、作用性の異なる複数の薬剤を順番に使う「ローテーション散布」が非常に有効です。 例えば、「有機リン系(スミチオンなど)→ネオニコチノイド系(スタークルなど)→IGR剤(アプロードなど)」というように、系統の違う薬剤を組み合わせます。また、物理的に作用するマシン油乳剤は抵抗性がつかないため、ローテーションの軸として活用するのがおすすめです。
農薬を使いたくない方へ!薬剤以外の駆除・予防法
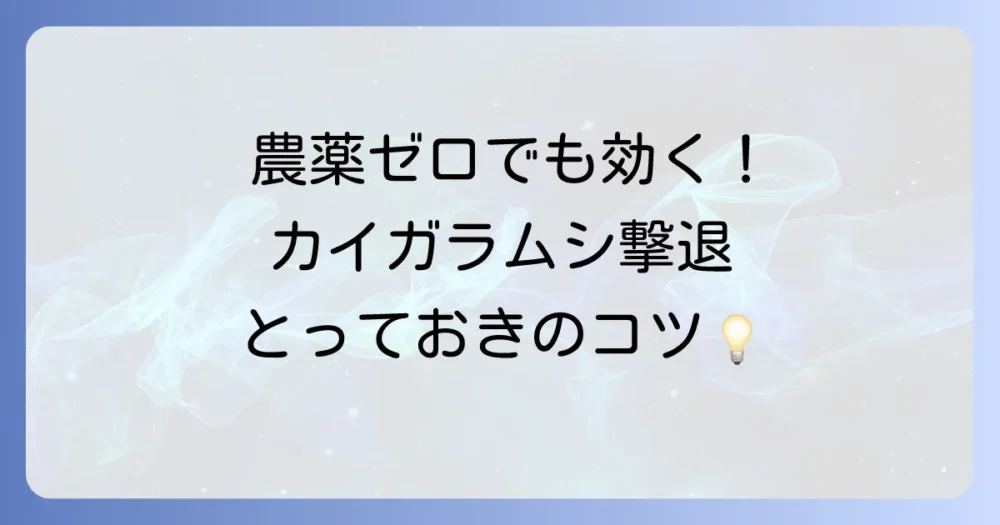
「家庭菜園なので、できるだけ農薬は使いたくない」という方もいらっしゃるでしょう。カイガラムシは薬剤を使わなくても、ある程度は駆除・予防することが可能です。ここでは、薬剤以外の方法をいくつかご紹介します。ただし、大量に発生してしまった場合は、これらの方法だけでは追いつかないこともありますので、状況に応じて薬剤との併用も検討してください。
主な方法は以下の通りです。
- 歯ブラシやヘラでこすり落とす(物理的駆除)
- 剪定で風通しを良くして予防する
- 天敵(テントウムシなど)の力を借りる
歯ブラシやヘラでこすり落とす(物理的駆除)
最も原始的ですが、確実な方法です。カイガラムシは固着しているものが多いため、使い古しの歯ブラシや竹べら、柔らかい布などを使って物理的にこすり落とします。 この方法は、薬剤が効きにくい成虫に対して特に有効です。木を傷つけないように、優しく丁寧に行うのがコツです。
こすり落としたカイガラムシは、地面に放置すると再び木に登ったり、卵が孵化したりする可能性があるため、ビニール袋などに入れて確実に処分しましょう。 発生数が少ないうちなら、この方法だけで十分に駆除できます。
剪定で風通しを良くして予防する
カイガラムシは、日当たりや風通しの悪い、湿気の多い場所を好んで発生します。 枝が混み合って薄暗くなっている場所は、カイガラムシにとって絶好の住処です。そこで重要になるのが「剪定」です。
不要な枝や混み合った枝を適切に剪定し、樹の内部まで日光が当たり、風が通り抜けるようにしてあげましょう。これにより、カイガラムシが好む環境をなくし、発生しにくい状態を保つことができます。また、風通しが良くなることで、薬剤を散布する際に薬液が樹の隅々まで届きやすくなるというメリットもあります。
天敵(テントウムシなど)の力を借りる
自然界には、カイガラムシを食べてくれる頼もしい天敵が存在します。代表的なのが、テントウムシの仲間です。特にアカホシテントウやヒメアカホシテントウの幼虫は、カイガラムシを好んで捕食します。また、ヤノネカイガラムシにはヤノネキイロコバチといった寄生蜂も有効な天敵として知られています。
これらの天敵を活かすためには、むやみに殺虫剤を散布しないことが大切です。幅広い害虫に効く殺虫剤は、天敵にも影響を与えてしまうことがあります。天敵の活動を妨げないマシン油乳剤や、特定の害虫にしか効かない選択性の高い薬剤を選ぶなど、薬剤の使用を計画的に行うことで、天敵による生物的防除の効果を高めることができます。
よくある質問
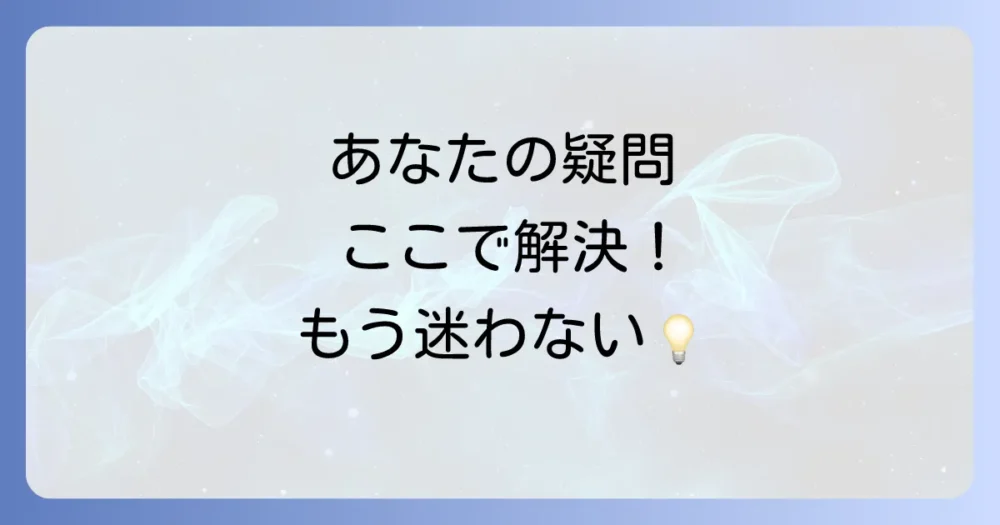
ここでは、みかんのカイガラムシ対策に関して、皆さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
カイガラムシ用の薬剤はホームセンターで買えますか?
はい、購入できます。 本記事で紹介した「マシン油乳剤」「カイガラムシエアゾール」「GFオルトラン水和剤・粒剤」「スミチオン乳剤」などは、多くのホームセンターや園芸店で取り扱っています。 ただし、「スタークル顆粒水溶剤」や「トランスフォームフロアブル」など、より専門的な薬剤は農協(JA)や農業資材専門店でないと手に入らない場合があります。
牛乳スプレーはカイガラムシに効果がありますか?
牛乳を水で薄めてスプレーする方法が紹介されることがありますが、カイガラムシに対する確実な効果は期待できません。 牛乳が乾く際の膜でアブラムシなどを窒息させる効果を狙ったものですが、殻を持つカイガラムシには効果が薄いとされています。また、牛乳が腐敗して悪臭を放ったり、カビの原因になったりする可能性もあるため、積極的にはおすすめできません。
薬剤散布の際の注意点は何ですか?
薬剤を使用する際は、必ず商品のラベルに記載されている使用方法、希釈倍率、使用回数、収穫前日数などの注意事項を厳守してください。 安全のため、散布時は農薬用マスク、ゴーグル、手袋、長袖・長ズボンの作業着を着用し、薬剤を吸い込んだり皮膚に付着したりしないようにしましょう。 風の強い日や雨の日の散布は避け、早朝や夕方の涼しい時間帯に行うのが基本です。散布後は、器具をよく洗浄し、残った薬液は適切に処理してください。
有機JAS適合の薬剤にはどのようなものがありますか?
有機JAS規格で使用が認められているカイガラムシ対策の薬剤としては、「マシン油乳剤」と「石灰硫黄合剤」が代表的です。 これらの薬剤は、化学合成農薬を使わずに栽培したい場合に中心となります。ただし、使用できる時期や方法に制限があるため、それぞれの特性をよく理解して使うことが重要です。
まとめ
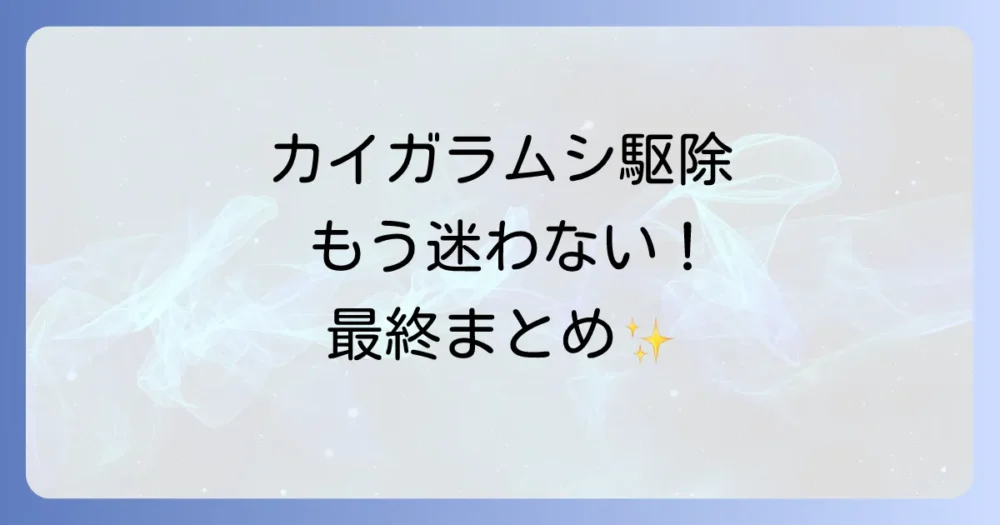
- みかんのカイガラムシは放置するとすす病などを引き起こす。
- 駆除の最大のチャンスは殻を被る前の幼虫の時期である。
- 幼虫の発生時期は主に5月~8月、特に6月が重要。
- 冬の越冬成虫対策にはマシン油乳剤の散布が非常に効果的。
- マシン油乳剤は物理的に効くため薬剤抵抗性がつきにくい。
- 手軽に使うならスプレータイプのカイガラムシエアゾールが便利。
- オルトランなど浸透移行性の薬剤は隠れた害虫にも効く。
- プロも使うスタークルは速効性と残効性に優れている。
- スミチオンは定番の薬剤でローテーションの一角を担う。
- 薬剤が効かない原因は散布時期や対象(成虫)の間違いが多い。
- 同じ薬剤の連続使用は薬剤抵抗性の原因になる。
- 作用性の異なる薬剤を順番に使うローテーション散布が有効。
- 農薬を使わない場合は歯ブラシなどで物理的にこすり落とす。
- 剪定で風通しを良くすることがカイガラムシの予防につながる。
- 薬剤を使用する際は必ずラベルを確認し、安全対策を徹底する。
新着記事