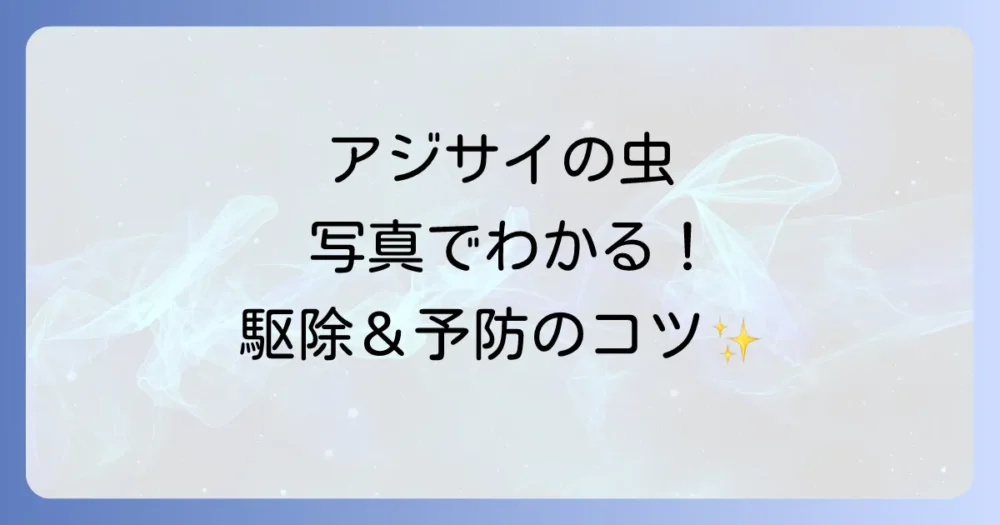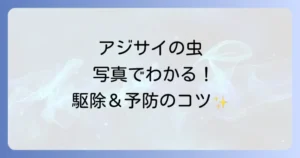梅雨の時期を彩る美しいアジサイ。大切に育てているアジサイに虫がついているのを見つけると、がっかりしてしまいますよね。「この虫は何だろう?」「どうやって駆除すればいいの?」そんなお悩みを抱えていませんか?本記事では、アジサイにつきやすい害虫の種類から、具体的な駆除方法、そして来年に向けた予防策まで、写真付きで詳しく解説します。この記事を読めば、あなたの大切なアジサイを害虫から守る方法がきっと見つかります。
【写真でチェック】アジサイによくつく害虫10選と被害症状
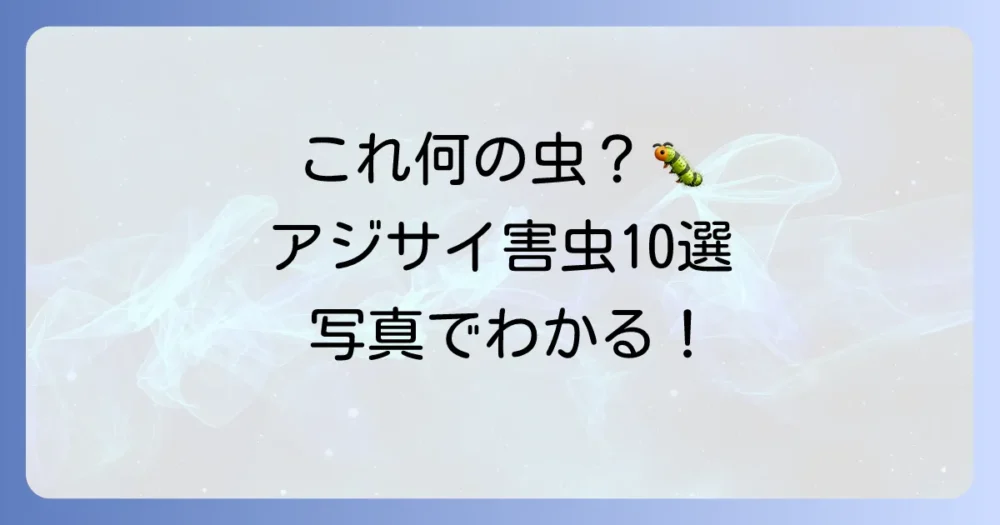
まずは、あなたのアジサイについている虫が何なのかを特定しましょう。ここでは、アジサイによく発生する代表的な害虫10種類を、被害の症状と合わせて写真付きでご紹介します。
- アブラムシ
- ハダニ
- カイガラムシ
- アジサイハバチ
- ヨトウムシ
- コガネムシ
- アオバハゴロモ
- カミキリムシ
- チャノキイロアザミウマ
- ナメクジ・カタツムリ
アブラムシ

アブラムシは、新芽や若い茎、葉の裏などに群がって発生する小さな虫です。 体長は1~3mmほどで、緑色や黒っぽい色をしています。 アブラムシは植物の汁を吸って加害し、大量に発生するとアジサイの生育が悪くなったり、新芽が萎縮して花が咲かなくなったりします。 また、アブラムシの排泄物は「すす病」という病気を誘発し、葉が黒くなる原因にもなります。 アリがアジサイの周りをうろついている場合は、アブラムシが発生しているサインかもしれません。
ハダニ

ハダニは0.5mmほどの非常に小さな虫で、肉眼では確認しにくい害虫です。 主に葉の裏に寄生して汁を吸います。 ハダニの被害にあうと、葉の表面に針で刺したような白い小斑点が現れ、次第にかすり状に白っぽく見えます。 被害が進行すると葉全体の色が悪くなり、やがて落葉して枯れてしまうこともあります。 高温で乾燥した環境を好むため、梅雨明けから9月頃にかけて特に発生しやすくなります。
カイガラムシ

カイガラムシは、その名の通り貝殻のような硬い殻や、白い綿のようなものに覆われている虫です。 枝や幹、葉の裏などに固着して吸汁し、アジサイの生育を妨げます。 成虫になるとほとんど動かなくなるため、見つけにくいのが特徴です。 カイガラムシの排泄物もすす病の原因となり、見た目を損なうだけでなく光合成を妨げます。 アナベルなどにつくアジサイワタカイガラムシは、白い綿状の分泌物に覆われているのが特徴です。
アジサイハバチ

アジサイハバチは、アジサイだけを食害するハチの仲間です。 5月頃に成虫が飛来して葉に卵を産み付け、6月頃から幼虫が発生します。 幼虫はイモムシのような見た目で、葉脈を残して葉をレース状に食べてしまうほどの旺盛な食欲を持っています。 大量に発生すると、あっという間に葉がボロボロにされてしまいます。
ヨトウムシ

ヨトウムシは「夜盗虫」と書くように、夜間に活動して葉を食べる蛾の幼虫です。 日中は土の中に隠れているため、姿を見つけるのが難しい害虫です。 朝、アジサイの葉に穴が開いていたり、葉が大きく食べられていたりしたら、ヨトウムシの仕業かもしれません。 食欲が旺盛で、一晩で葉の大部分を食べ尽くしてしまうこともあります。
コガネムシ

コガネムシの成虫は、光沢のある美しい見た目とは裏腹に、アジサイの葉や花を食い荒らす害虫です。 特に、バラ科の植物を好みますが、アジサイも被害にあうことがあります。 幼虫は土の中で根を食害するため、株全体の生育が悪くなる原因にもなります。成虫が集団で葉を食べているのを見かけることもあります。
アオバハゴロモ

アオバハゴロモの幼虫は、白い綿のような分泌物で体を覆っているのが特徴です。 新梢や枝に発生し、吸汁してアジサイを弱らせます。 大量に発生すると生育が悪くなるほか、分泌物が枝に残って見た目を損ないます。 風通しの悪い場所に発生しやすい傾向があります。
カミキリムシ

カミキリムシの幼虫(テッポウムシ)は、アジサイの幹や太い枝の内部に侵入し、食い荒らします。被害が進むと、株が弱ってしまい、最悪の場合枯れてしまうこともあります。幹におがくずのようなものが出ていたら、カミキリムシの幼虫がいるサインかもしれません。
チャノキイロアザミウマ

チャノキイロアザミウマは、体長1mmほどの黄色い小さな虫です。 新芽に産卵し、葉を食害します。 被害を受けた葉は褐色に変色し、縮れてしまいます。 お茶の木や柑橘類にもよく発生する害虫です。
ナメクジ・カタツムリ

ナメクジやカタツムリは、夜間に活動し、アジサイの葉や花びらを食べます。食べた跡が這ったようにテカテカ光っているのが特徴です。湿気の多い場所を好むため、梅雨の時期は特に活動が活発になります。アジサイの葉には毒性成分が含まれていると言われていますが、これらの虫には影響がないようです。
【今すぐできる!】アジサイの害虫駆除方法
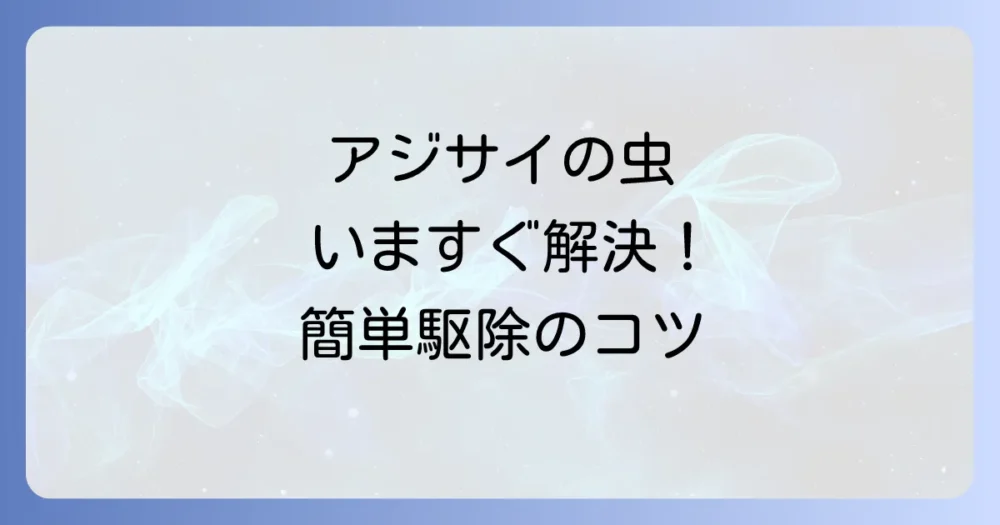
害虫を見つけたら、被害が広がる前にすぐに対処することが大切です。ここでは、ご家庭でできる駆除方法を「手作業」と「薬剤」に分けてご紹介します。
- 手で取り除く・水で洗い流す
- 薬剤(殺虫剤)を使う
手で取り除く・水で洗い流す
アブラムシやハダニ、ヨトウムシなど、数が少ない初期段階であれば、手で取り除くのが最も手軽で確実な方法です。
アブラムシは粘着テープにくっつけて捕殺したり、指で潰したりします。 ハダニは水に弱い性質があるため、ホースの水圧で葉の裏から勢いよく洗い流すだけでも効果があります。 ヨトウムシやアジサイハバチの幼虫は、割り箸などでつまんで捕殺しましょう。 カイガラムシは成虫になると薬剤が効きにくくなるため、歯ブラシなどでこすり落とすのが有効です。
ただし、虫が苦手な方や、大量に発生してしまった場合は、次の薬剤を使った方法をおすすめします。
薬剤(殺虫剤)を使う
害虫が大量に発生してしまった場合や、手作業での駆除が難しい場合は、殺虫剤を使用するのが効果的です。 ホームセンターや園芸店で、アジサイに使える殺虫剤が多数販売されています。
代表的な薬剤
- ベニカXファインスプレー(住友化学園芸): 害虫と病気に同時に効果があり、予防効果も期待できます。
- オルトラン粒剤(住友化学園芸): 土にまくタイプの薬剤で、根から成分が吸収され、植物全体に効果が広がります。
- やさお酢(アース製薬): 食品成分であるお酢から作られており、薬剤に抵抗がある方にもおすすめです。
- カダンセーフ(フマキラー): 食品由来成分で、病害虫を包み込んで退治します。
薬剤を使用する際は、必ず商品の説明書をよく読み、対象となる害虫や使用方法、注意事項を確認してください。 特に、葉の裏など害虫が隠れている場所にもしっかりと散布することがポイントです。
【来年はもう悩まない】アジサイの害虫予防策
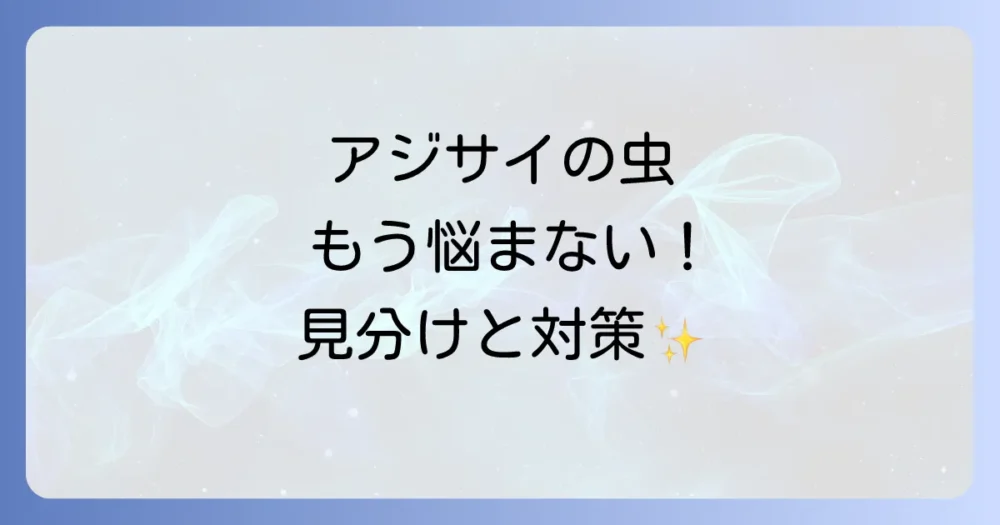
害虫の被害を最小限に抑えるためには、日頃からの予防が何よりも重要です。ちょっとした心がけで、害虫が発生しにくい環境を作ることができます。
- 風通しを良くする(剪定)
- 葉の裏にも水をかける
- 予防効果のある薬剤をまく
- 天敵を利用する
風通しを良くする(剪定)
多くの害虫や病気は、湿気が多く風通しの悪い場所を好みます。 花が終わった後、適切な時期に剪定を行い、枝や葉が混み合っている場所をなくしましょう。 これにより、株全体の風通しと日当たりが良くなり、害虫が住みつきにくい環境になります。
葉の裏にも水をかける
特に乾燥を好むハダニは、水に弱いという性質があります。 水やりの際には、株元だけでなく、葉の裏側にもしっかりと水をかけるようにしましょう。 これだけで、ハダニの発生をかなり抑えることができます。
予防効果のある薬剤をまく
害虫が発生しやすい春先(3月~4月頃)から、予防的に薬剤を散布しておくのも非常に効果的です。 土にまくタイプの粒剤(オルトラン粒剤など)は、効果が長持ちし、手間もかからないのでおすすめです。 また、「やさお酢」などの食品成分由来のスプレーを定期的に散布することも、アブラムシなどの予防につながります。
天敵を利用する
アブラムシの天敵であるテントウムシやヒラタアブなどを味方につけるのも一つの方法です。これらの益虫が活動しやすい環境を整えることで、自然に害虫の数をコントロールすることができます。殺虫剤を使いすぎると、こうした益虫もいなくなってしまうので注意が必要です。
【薬剤を使いたくない人向け】自然由来の虫除け対策
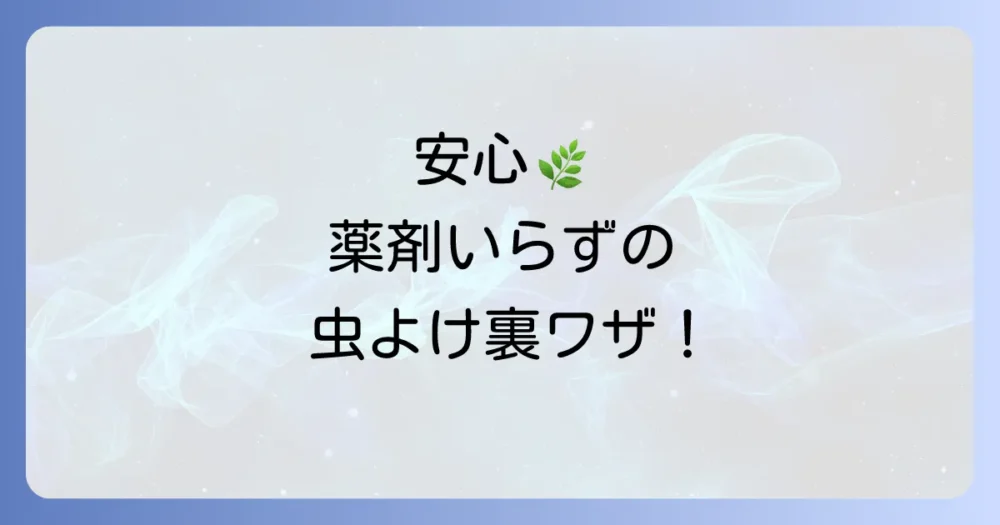
「化学薬品はできるだけ使いたくない」という方も多いでしょう。ここでは、身近なものを使った自然由来の虫除け対策をご紹介します。ただし、効果は薬剤に比べて穏やかなので、こまめな散布が必要です。
- 木酢液・竹酢液
- 牛乳スプレー
- コンパニオンプランツ
木酢液・竹酢液
木酢液や竹酢液は、木炭や竹炭を作る際に出る煙を冷却して液体にしたものです。これを水で薄めて散布すると、独特の香りで害虫を寄せ付けにくくする効果があると言われています。また、土壌改良の効果も期待できます。
牛乳スプレー
牛乳を水で薄めてスプレーし、乾かすと膜ができてアブラムシなどを窒息させる効果があると言われています。ただし、散布後に牛乳の匂いが残ったり、腐敗してカビの原因になったりすることもあるため、散布後は水で洗い流すなどの注意が必要です。
コンパニオンプランツ
アジサイの近くに、害虫が嫌う香りを持つハーブ類(ミント、ローズマリー、ラベンダーなど)や、天敵を呼び寄せる植物(マリーゴールドなど)を植える「コンパニオンプランツ」という方法もあります。景観を楽しみながら、自然に害虫を遠ざけることができます。
よくある質問
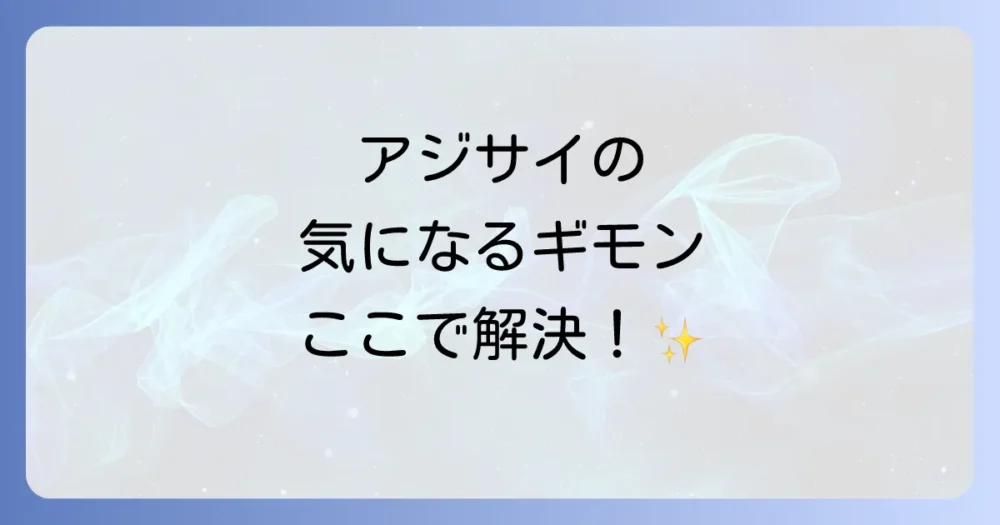
アジサイの葉に毒はありますか?虫は食べても大丈夫?
アジサイの葉には「青酸配糖体」などの有毒成分が含まれているとされ、人間やペットが食べると食中毒を起こす可能性があります。 料理の飾りなどに使われていても、絶対に食べないでください。 しかし、アジサイハバチやコガネムシなど、一部の昆虫はアジサイの葉を問題なく食べることができます。
アジサイの枝についている白い綿のようなものは何ですか?
アジサイの枝や新梢に白い綿のようなものが付着している場合、アオバハゴロモの幼虫か、アジサイワタカイガラムシの可能性があります。 どちらも吸汁性の害虫ですので、見つけ次第、歯ブラシでこすり落とすか、薬剤で駆除することをおすすめします。
アジサイの新芽にいる小さい虫の対策を教えてください。
新芽にびっしりとついているゴマのような小さな虫は、アブラムシの可能性が高いです。 放置すると急速に増殖し、アジサイの生育を著しく阻害します。 数が少ないうちはテープなどで取り除き、多い場合は薬剤を散布して早めに駆除しましょう。
アジサイの葉が黒っぽいですが、病気でしょうか?
葉が黒いすすで覆われたようになっている場合、「すす病」という病気の可能性があります。 これは、アブラムシやカイガラムシの排泄物を栄養源としてカビが繁殖したものです。 すす病自体が直接アジサイを枯らすわけではありませんが、光合成を妨げて生育を悪くします。原因となっている害虫を駆除することが根本的な対策となります。
まとめ
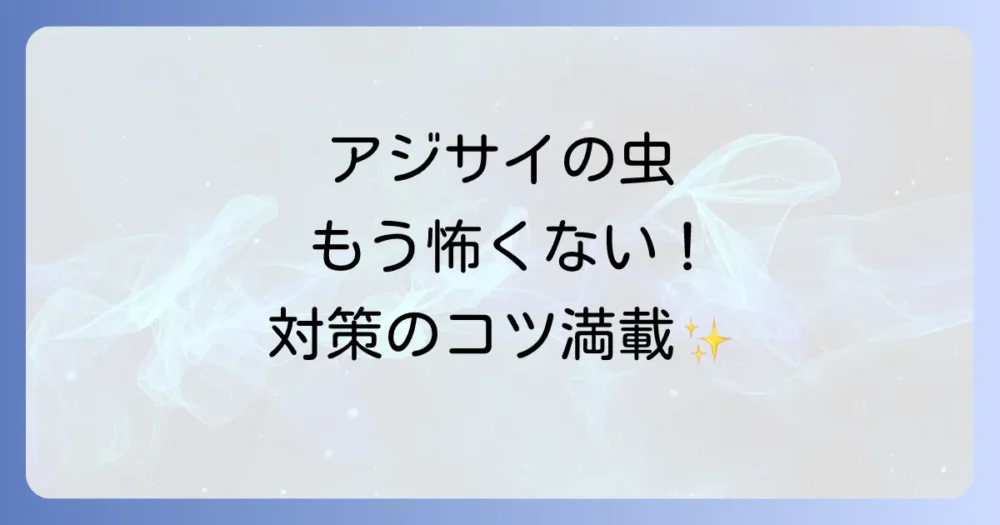
- アジサイにはアブラムシやハダニなど多様な虫がつく。
- 害虫は葉や茎の汁を吸ったり、葉を食べたりする。
- 害虫の特定には、被害の症状や虫の見た目を確認する。
- 初期段階の駆除は手作業や水で洗い流すのが有効。
- 大量発生時はアジサイに使える殺虫剤を使用する。
- 薬剤は説明書をよく読み、正しく使用することが重要。
- 予防の基本は、剪定による風通しの確保。
- ハダニ予防には葉裏への水やりが効果的。
- 春先に予防的な薬剤散布を行うと被害を抑えられる。
- 薬剤を使わない自然な虫除け方法もある。
- アブラムシやカイガラムシはすす病を誘発する。
- アジサイハバチは葉をレース状に食い荒らす。
- ヨトウムシは夜間に葉を食べるので注意が必要。
- 白い綿のような虫はアオバハゴロモやカイガラムシ。
- アジサイの葉には毒性があり、人間は食べてはいけない。