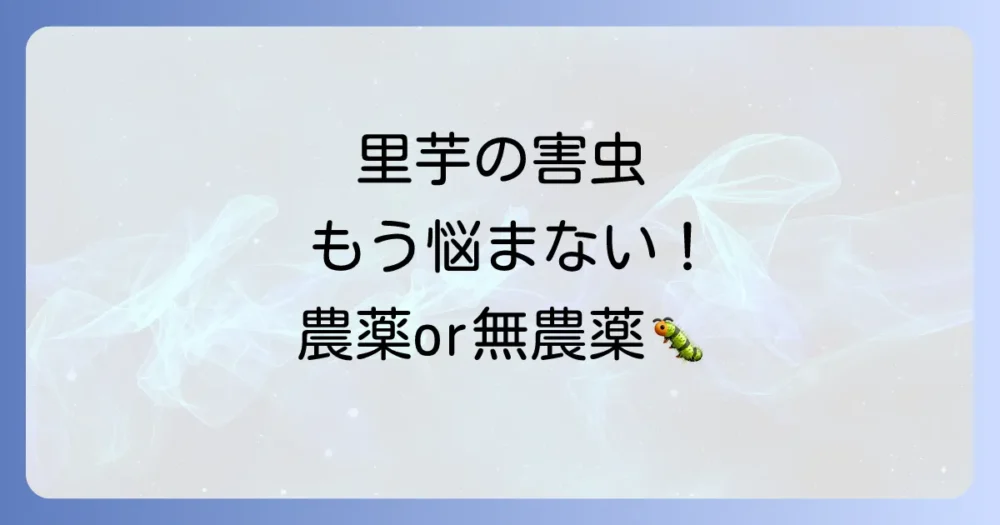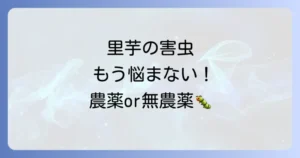大切に育てている里芋の葉が、何者かに食べられていたり、小さな虫がびっしり付いていたりすると、本当にがっかりしますよね。「どうすればこの害虫を駆除できるの?」「できれば農薬は使いたくないけど、効果的な方法はあるの?」そんなお悩みを抱えていませんか。本記事では、里芋に発生しやすい害虫の種類から、効果的な農薬の選び方、そして農薬を使わない自然にやさしい対策まで、詳しく解説していきます。この記事を読めば、あなたに合った害虫対策がきっと見つかります。
里芋に発生しやすい主要な害虫と被害の症状
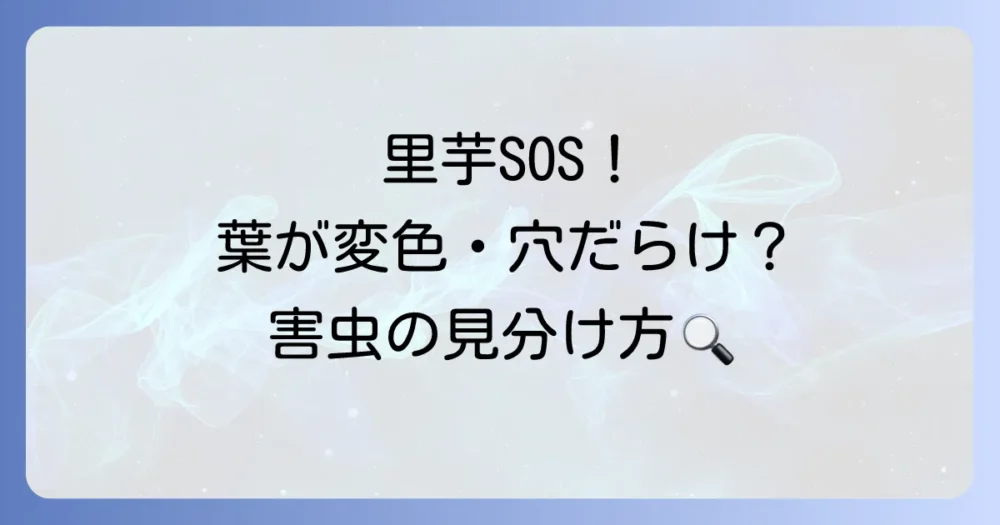
里芋を元気に育てるためには、まず敵を知ることが重要です。里芋には特有の害虫が発生しやすく、それぞれ被害の出方が異なります。ここでは、特に注意したい主要な害虫とその被害症状について解説します。早期発見・早期対応が、被害を最小限に食い止める鍵となります。
本章では、以下の害虫について詳しく見ていきましょう。
- アブラムシ類(ワタアブラムシなど)
- 食葉性害虫(セスジスズメ、ハスモンヨトウ)
- 土中の害虫(コガネムシの幼虫など)
アブラムシ類(ワタアブラムシなど)
里芋に発生するアブラムシのほとんどは「ワタアブラムシ」です。 体長0.5mmから3mm程度の非常に小さな虫で、黄色や黒っぽい色をしています。 主に葉の裏や新しい芽にびっしりと群生し、植物の汁を吸って加害します。
被害が進むと、葉が黄色く変色したり、縮れたりして生育が悪くなります。 さらに、アブラムシの排泄物(甘露)が原因で、葉がすすで汚れたように黒くなる「すす病」を誘発することもあります。しかし、最も警戒すべきは、ウイルス病(モザイク病)を媒介することです。 モザイク病にかかると葉にモザイク状の模様が現れ、治療法がないため、株ごと抜き取って処分するしかありません。そのため、アブラムシは見つけ次第、早急に駆除することが非常に重要です。
食葉性害虫(セスジスズメ、ハスモンヨトウ)
里芋の大きな葉を旺盛な食欲で食い荒らすのが、セスジスズメやハスモンヨトウといったイモムシ系の害虫です。
セスジスズメの幼虫は、体長8cmほどにもなる大型のイモムシで、黒色や緑色の体に目玉のような模様があるのが特徴です。 お尻に一本のツノ(尾角)があります。 葉の裏に1つずつ卵が産み付けられ、ふ化した幼虫は硬い葉脈を残して葉をどんどん食べてしまいます。 食欲が非常に旺盛で、数匹いるだけで葉が丸坊主にされてしまうことも珍しくありません。
一方、ハスモンヨトウは「夜盗虫」の名の通り、夜間に活動して葉を食害します。 若い幼虫は葉の裏に集団で発生し、葉の表面の皮を残して食べるため、葉が白っぽく見えるのが特徴です。 成長すると分散し、昼間は土の中や株元に隠れています。被害が拡大すると、葉に大きな穴が開けられ、収穫量の減少に直結します。
土中の害虫(コガネムシの幼虫など)
地上部だけでなく、土の中に潜む害虫にも注意が必要です。代表的なのがコガネムシの幼虫です。
コガネムシの幼虫は、白くて丸まったいわゆる「ネキリムシ」や「ブイブイ」と呼ばれる姿をしています。土の中で里芋の根や、肥大してきた芋そのものを食害します。 地上部の葉は元気に見えても、土の中で被害が進行しているケースがあり、気づいた時には芋がスカスカになっていたということも。特に、畑に未熟な堆肥を入れると、それを目当てにコガネムシが産卵しやすくなるため注意が必要です。収穫後の貯蔵中にも芋を食害し続けることがあるため、最後まで油断できません。
【害虫別】里芋に使えるおすすめの農薬と使い方
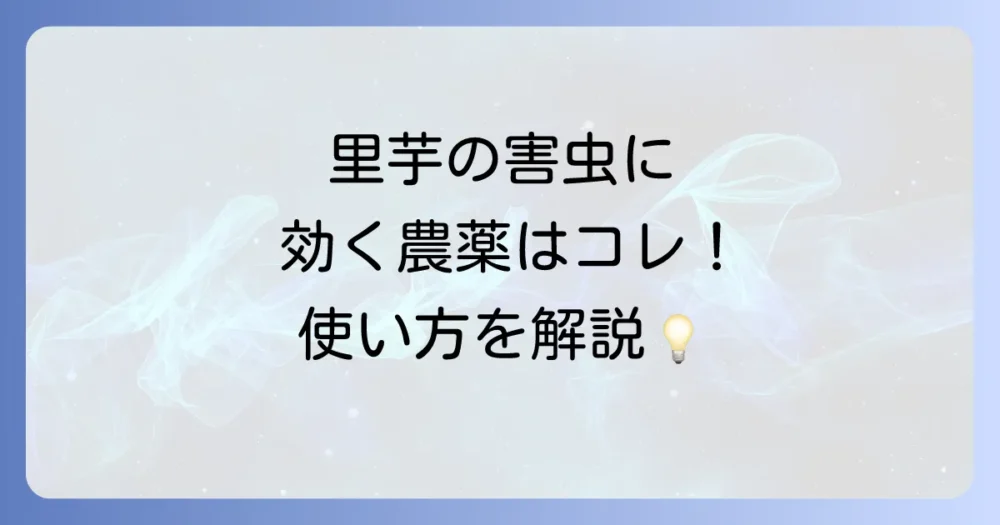
害虫の発生が多く、手作業での駆除が追いつかない場合には、農薬の使用が効果的です。しかし、農薬は種類が多く、どの害虫に何を使えば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、害虫の種類別に、里芋に登録のあるおすすめの農薬と、その効果的な使い方を解説します。
本章でご紹介する内容は以下の通りです。
- アブラムシ類に効果的な農薬
- セスジスズメ・ハスモンヨトウに効果的な農薬
- コガネムシの幼虫に効果的な農薬
- 農薬を使用する際の注意点
アブラムシ類に効果的な農薬
アブラムシはウイルス病を媒介するため、徹底的に防除したい害虫です。アブラムシに効果のある農薬には、モスピランやアドマイヤー、ウララDFなどがあります。 これらは浸透移行性といって、薬剤が植物に吸収され、その汁を吸ったアブラムシを退治するタイプの農薬です。葉の裏に隠れているアブラムシにも効果を発揮しやすいのが利点です。
植え付け時にアドマイヤー1粒剤を土に混ぜておくと、長期間アブラムシの発生を抑えることができます。 生育期に発生した場合は、モスピランやウララDFを散布します。
ここで重要なのが「RACコード」です。これは農薬の作用性を分類したコードで、同じコードの農薬を連続して使用すると、害虫に抵抗性がついて効きにくくなることがあります。 例えば、モスピランとアドマイヤーは同じ「4A」グループです。そのため、異なるRACコードの農薬を順番に使う「ローテーション散布」を心がけましょう。ウララDFは「29」なので、ローテーションの一角として有効です。
セスジスズメ・ハスモンヨトウに効果的な農薬
葉を食べるイモムシ類には、食害を素早く止める効果のある農薬が適しています。ハスモンヨトウにはトレボン乳剤やフェニックス顆粒水和剤、コテツフロアブルなどが登録されています。 セスジスズメには直接の登録がない農薬もありますが、ハスモンヨトウなど他のチョウ目害虫に効果のある薬剤で同時に防除できることが多いです。
例えば、トルネードエースDFは、大型のチョウ目幼虫にも高い効果が期待できるとされています。 また、プレバソンフロアブル5も幅広いチョウ目害虫に効果があります。
これらの害虫は、幼虫が小さいうち(若齢幼虫)の方が農薬が効きやすいという特徴があります。 発生を見つけたら、なるべく早く散布することが駆除のコツです。ハスモンヨトウは薬剤抵抗性が発達しやすい害虫としても知られているため、こちらもアブラムシ同様、作用性の異なる薬剤のローテーション散布が重要になります。
コガネムシの幼虫に効果的な農薬
土の中にいるコガネムシの幼虫には、粒剤タイプの土壌混和剤が有効です。代表的な農薬としてダイアジノン粒剤やオンコル粒剤5があります。
これらの農薬は、里芋を植え付ける前の土壌全面、あるいは植え付け時の植え溝に混ぜ込むことで効果を発揮します。 薬剤が土壌中に広がり、孵化してくる幼虫や土の中の幼虫を退治します。成虫が産卵する前、つまり春から初夏にかけて処理を済ませておくのが最も効果的です。生育の途中で株元に散布して土寄せする方法もありますが、使用時期や回数には制限があるため、必ずラベルを確認してください。
農薬を使用する際の注意点
農薬は正しく使ってこそ、その効果を最大限に発揮し、安全性も確保できます。使用する際は、以下の点に必ず注意してください。
- ラベルを必ず確認する: 対象作物(さといも)、対象害虫、希釈倍率、使用時期、使用回数が記載されています。これらを厳守することが大前提です。
- 使用時期と回数を守る: 「収穫〇日前まで」「本剤の使用回数〇回以内」といった基準は、残留農薬の観点から非常に重要です。特に葉柄も食べる場合は、葉柄の登録内容を確認する必要があります。
- 展着剤を使用する: 里芋の葉は水をはじきやすいため、農薬がうまく付着しません。 展着剤を混ぜることで薬液が葉に広がり、効果を高めることができます。
- 散布は風のない涼しい時間帯に: 早朝や夕方の涼しい時間帯に、風のない日を選んで散布しましょう。高温時の散布は薬害の原因になったり、風が強いと近隣に飛散したりする恐れがあります。
- 防除器具を身につける: 農薬を吸い込んだり、皮膚に付着したりしないよう、マスク、ゴーグル、手袋、長袖長ズボンの作業着を着用しましょう。
農薬を使いたくない方へ!無農薬・減農薬での害虫対策
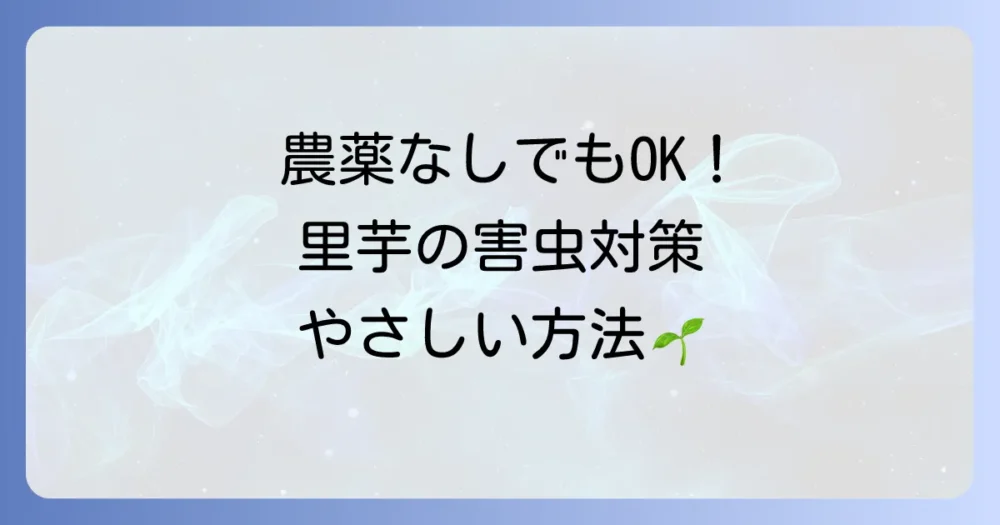
「家庭菜園だから、できるだけ農薬は使いたくない」と考える方も多いでしょう。無農薬や減農薬で里芋を育てることは十分に可能です。ここでは、化学合成農薬に頼らない害虫対策をご紹介します。予防的な対策と、発生してしまった後の対処法を組み合わせることが成功のコツです。
この章では、以下の対策について解説します。
- 予防が肝心!害虫を寄せ付けないための工夫
- 発生してしまった害虫への対処法
- 有機JAS栽培で使える農薬(生物農薬など)
予防が肝心!害虫を寄せ付けないための工夫
害虫対策の基本は、そもそも害虫を畑に寄せ付けない環境を作ることです。
まず、最も物理的で効果的なのが防虫ネットの利用です。アブラムシやセスジスズメの成虫(ガ)の飛来と産卵を防ぐことができます。 里芋の植え付け後、早めにトンネル状にネットをかけておくと良いでしょう。
次に、雑草管理も重要です。畑の周りに雑草が生い茂っていると、そこが害虫の隠れ家や発生源になります。 特にセスジスズメはヤブガラシなどの雑草でも発生するため、こまめに草取りをすることが大切です。
また、コンパニオンプランツを活用する方法もあります。里芋の近くにマリーゴールドを植えると、その根から出る分泌物が土の中のセンチュウを抑制する効果が期待できます。
発生してしまった害虫への対処法
予防策を講じても、害虫が発生してしまうことはあります。その場合は、早期発見と迅速な対応が鍵となります。
セスジスズメのような大型のイモムシは、数が少ないうちは手で捕まえて駆除する(テデトール)のが最も確実です。 見つけ次第、割り箸などでつまんで取り除きましょう。
アブラムシが少数発生している場合は、粘着テープで貼り付けたり、牛乳や石鹸水を薄めたものをスプレーで吹きかけ、窒息させて駆除する方法があります。 油と石鹸を混ぜた「油石鹸水」も効果的ですが、散布後しばらくしたら水で洗い流す必要があります。
ハスモンヨトウは米ぬかが好きという習性を利用し、米ぬかを少量入れた穴を畑に作っておびき寄せ、一網打尽にするという方法もあります。 また、ミントや唐辛子を漬け込んだスプレーを散布して、害虫を忌避する効果を狙うのも一つの手です。
有機JAS栽培で使える農薬(生物農薬など)
「化学合成農薬は使いたくないけれど、手作業だけでは限界…」という場合には、有機JAS規格で認められている農薬を利用する選択肢があります。
代表的なものにBT剤があります。これは「バチルス・チューリンゲンシス」という自然界に存在する細菌を利用した生物農薬で、チョウ目(イモムシ類)の害虫に選択的に効果を発揮します。 商品名としては「ゼンターリ顆粒水和剤」などがあります。この薬剤は、害虫の天敵であるハチなどには影響が少ないという利点もあります。
また、アブラムシの天敵であるテントウムシやヒラタアブなどを畑に放す「天敵製剤」を利用する方法もあります。 これらは化学的な成分を含まないため、環境への負荷が少なく、安心して使用できます。ただし、効果が現れるまでに時間がかかる場合があるため、予防的な観点での使用がおすすめです。
よくある質問
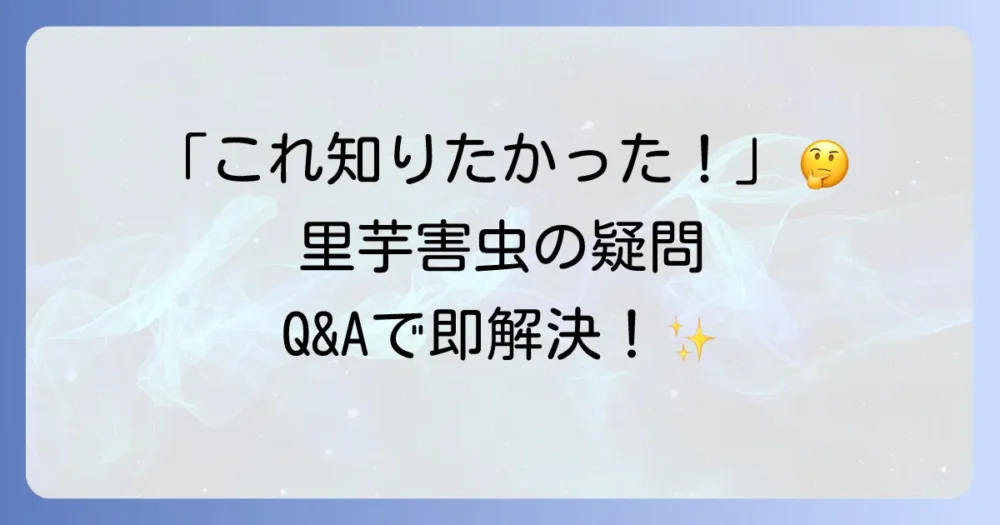
里芋の葉が食べられているのですが、犯人は何ですか?
里芋の葉を食べる主な害虫は、セスジスズメやハスモンヨトウの幼虫(イモムシ)である可能性が高いです。 セスジスズメは黒や緑色で目玉模様のある大きなイモムシで、昼間も葉の上で食事をします。ハスモンヨトウは夜行性で、若い頃は集団で葉の裏を白く食害し、大きくなると葉に穴を開けます。 糞が落ちていないか、葉の裏に虫がいないか確認してみてください。
農薬はいつ散布するのが効果的ですか?
農薬を散布するタイミングは、害虫の種類や農薬の特性によって異なります。一般的には、害虫が発生し始めた初期段階、特に幼虫が小さいうちに散布するのが最も効果的です。 時間帯としては、日中の高温時を避け、風のない早朝や夕方の涼しい時間帯が適しています。 雨が降ると薬剤が流れてしまうため、天候も考慮しましょう。
農薬を使わずにアブラムシを駆除する方法はありますか?
はい、いくつか方法があります。発生がごく初期であれば、粘着テープで貼り取ったり、歯ブラシなどでこすり落とすことができます。範囲が広い場合は、牛乳や石鹸水を薄めてスプレーで吹きかけると、アブラムシが窒息して駆除できます。 また、テントウムシなどの天敵を放つのも有効な手段です。
セスジスズメの幼虫は手で取っても大丈夫ですか?
はい、セスジスズメの幼虫に毒はありませんので、手で捕まえても問題ありません。見た目が苦手な方は、割り箸や手袋を使うと良いでしょう。 非常に食欲旺盛な害虫なので、見つけ次第、捕殺するのが最も手軽で確実な駆除方法です。
収穫間近でも使える農薬はありますか?
はい、収穫前日まで使用できる農薬もあります。例えば、ハスモンヨトウに対して「フェニックス顆粒水和剤」や、ハダニ類に対して「コロマイト乳剤」は収穫前日まで使用可能です。 ただし、農薬ごとに「収穫前日数」が厳密に定められていますので、使用前には必ず農薬のラベルを確認し、記載されている使用基準を厳守してください。
まとめ
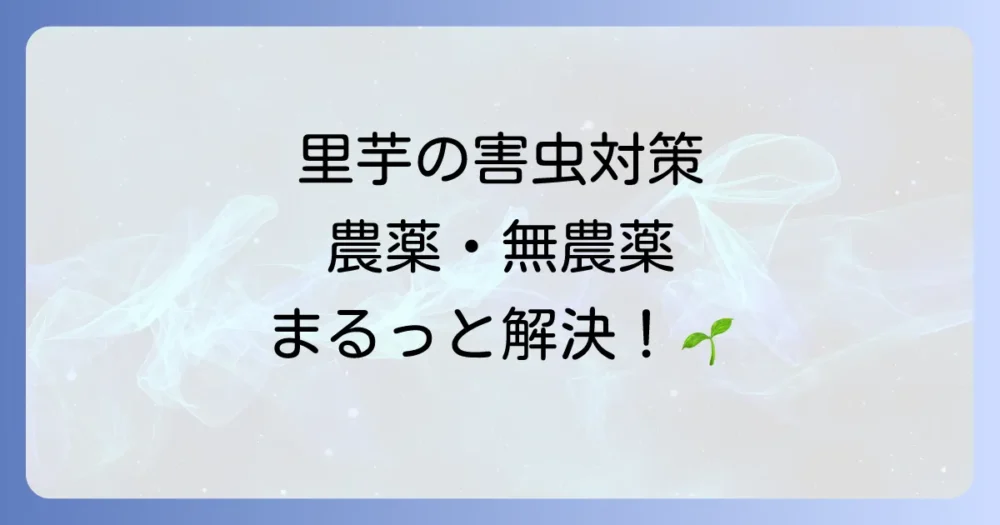
- 里芋の主な害虫はアブラムシ、セスジスズメ、ハスモンヨトウ、コガネムシ幼虫です。
- アブラムシは吸汁被害に加え、ウイルス病を媒介するため特に注意が必要です。
- セスジスズメやハスモンヨトウは葉を食害し、収量低下の原因となります。
- コガネムシの幼虫は土中で根や芋を食害します。
- 害虫対策には、まず種類を特定することが重要です。
- 農薬を使用する場合は、対象害虫に登録のある薬剤を選びましょう。
- アブラムシにはモスピランやアドマイヤー、ウララDFなどが有効です。
- イモムシ類にはトレボン乳剤やプレバソンフロアブルなどが効果的です。
- コガネムシ幼虫にはダイアジノン粒剤などの土壌混和剤を使用します。
- 農薬は抵抗性回避のため、作用性の異なる薬剤のローテーション散布が推奨されます。
- 農薬使用時はラベルをよく読み、使用時期や回数、希釈倍率を必ず守ってください。
- 無農薬対策として、防虫ネットの設置は物理的に害虫の侵入を防ぎ効果的です。
- 雑草管理を徹底し、害虫の発生源を減らすことも大切です。
- 手で捕殺する、木酢液や石鹸水を利用するなど、化学農薬に頼らない駆除方法もあります。
- 有機JASで認められたBT剤などの生物農薬も有効な選択肢の一つです。