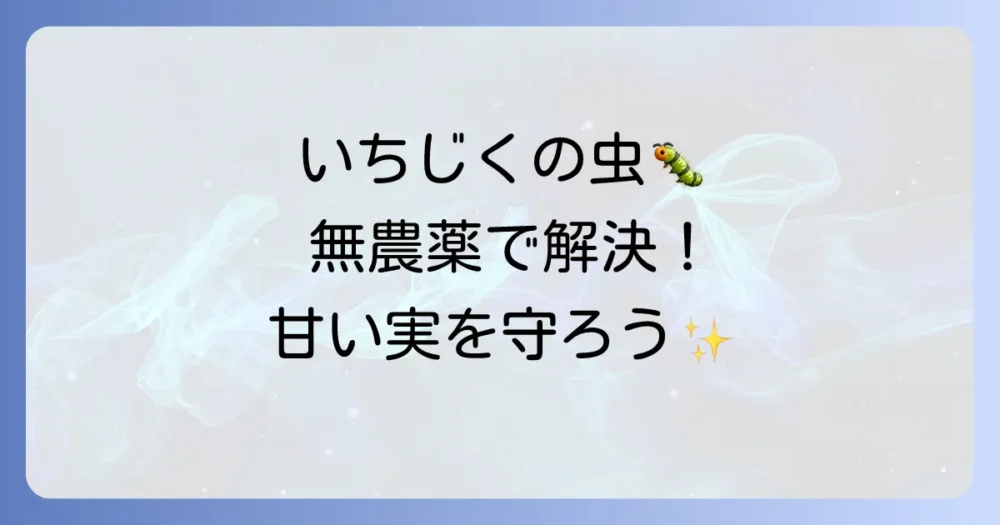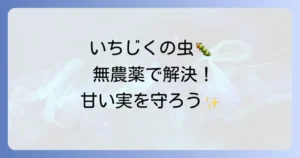甘くて美味しいいちじく。家庭菜園で育てている方も多いのではないでしょうか。しかし、大切に育てたいちじくが虫の被害にあってしまうと、本当にがっかりしますよね。「葉が穴だらけになっている…」「実の中に虫がいて気持ち悪い…」そんなお悩みを抱えていませんか?本記事では、いちじくに発生するやっかいな虫の対策について、無農薬でできる予防法から、発生してしまった後の駆除方法まで、詳しく解説していきます。正しい知識を身につけて、大切なちじくを虫から守り、美味しい果実をたくさん収穫しましょう。
いちじく栽培で注意すべき害虫一覧
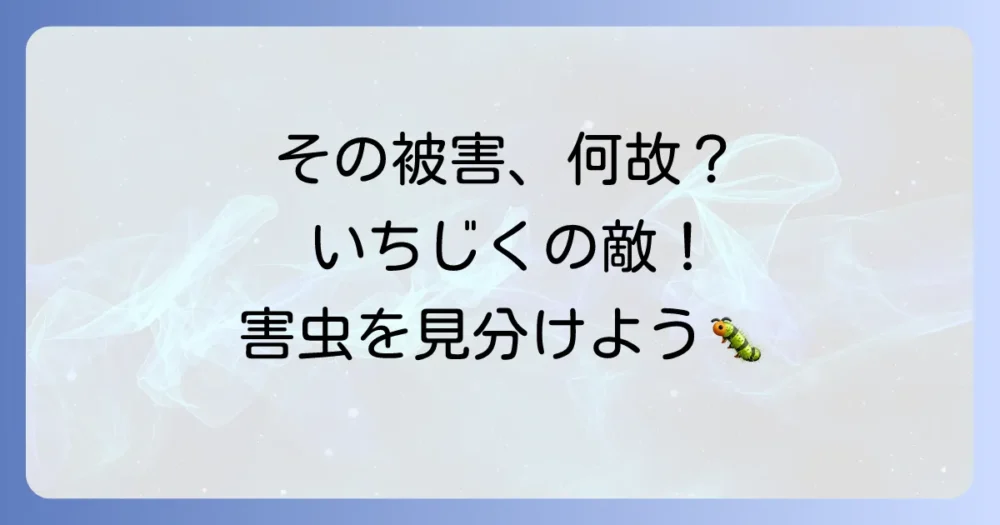
まずはいちじくにどんな虫がつくのか、敵を知ることから始めましょう。いちじくに発生しやすい代表的な害虫とその被害について解説します。ご自身のいちじくの状態と照らし合わせながら、どの害虫の仕業なのか見当をつけてみてください。
- 【最重要害虫】カミキリムシ(テッポウムシ)
- 実の中に侵入する厄介者!アザミウマ
- 葉をボロボロにする!コガネムシ・イチジクヒトリモドキ
- 大量発生して樹を弱らせる!アブラムシ・カイガラムシ
- 果実を狙う!ショウジョウバエ・アリ・ナメクジ
- その他の害虫(ハダニなど)
【最重要害虫】カミキリムシ(テッポウムシ)
いちじく栽培において最も警戒すべき害虫がカミキリムシです。 成虫は5月~7月頃に飛来し、幹や枝の樹皮をかじって産卵します。 孵化した幼虫(テッポウムシ)は木の内部に侵入し、幹を食い荒らしてしまうのです。 被害が進むと、木が栄養や水分を運べなくなり、最悪の場合、木全体が枯れてしまうこともあります。 株元に木くずのようなフンが落ちていたら、幼虫が内部にいるサインです。 見つけ次第、早急な対策が必要になります。
実の中に侵入する厄介者!アザミウマ
アザミウマは体長1~2mmほどの非常に小さな虫で、花の蜜や果汁を吸います。 いちじくの場合、果実の先端にある「目」と呼ばれる部分から内部に侵入し、果実の中を食害します。 被害を受けた果実は、外側からは分かりにくいものの、割ってみると内部が変色していたり、腐敗したりしています。 発生時期は5月下旬から7月頃がピークで、雑草などにも発生するため、畑全体の管理が重要になります。
葉をボロボロにする!コガネムシ・イチジクヒトリモドキ
いちじくの葉がレースのように穴だらけになっていたら、コガネムシやイチジクヒトリモドキの幼虫による食害が疑われます。 コガネムシは成虫が葉を食害し、ひどい場合は葉脈だけを残して食べ尽くしてしまいます。 一方、イチジクヒトリモドキは蛾の幼虫(毛虫)で、特に5月下旬頃から発生し、集団で葉を食い荒らします。 どちらも放置すると光合成ができなくなり、木の生育が悪くなったり、果実の品質が低下したりする原因となります。
大量発生して樹を弱らせる!アブラムシ・カイガラムシ
アブラムシやカイガラムシは、新芽や葉、枝にびっしりと付着し、吸汁して木を弱らせる害虫です。 これらの虫の排泄物は「すす病」の原因となり、葉や果実が黒いすすで覆われたようになってしまいます。すす病は光合成を妨げるだけでなく、見た目も悪くします。繁殖力が非常に高いため、少数を見つけたらすぐに駆除することが大切です。
果実を狙う!ショウジョウバエ・アリ・ナメクジ
熟した果実は、ショウジョウバエやアリ、ナメクジといった虫たちにとってもごちそうです。 ショウジョウバエは熟した果実の匂いに誘われて集まり、果実を腐敗させる原因となります。 アリは甘い果汁を求めて木に登り、果実の中にまで入り込むことがあります。 ナメクジも夜間に活動し、果実を食害します。これらの害虫は、収穫間際の果実を台無しにしてしまうため、油断できません。
その他の害虫(ハダニなど)
梅雨明け後の高温乾燥期に注意したいのがハダニです。 葉の裏に寄生して栄養を吸い、葉の色がかすれたように白っぽくなります。 大量に発生すると葉が枯れ落ち、木全体の生育に影響が出ます。非常に小さく、肉眼では確認しづらいですが、被害が広がる前に見つけたい害虫です。
【発生前が肝心!】農薬に頼らない!いちじくの虫を寄せ付けない予防策
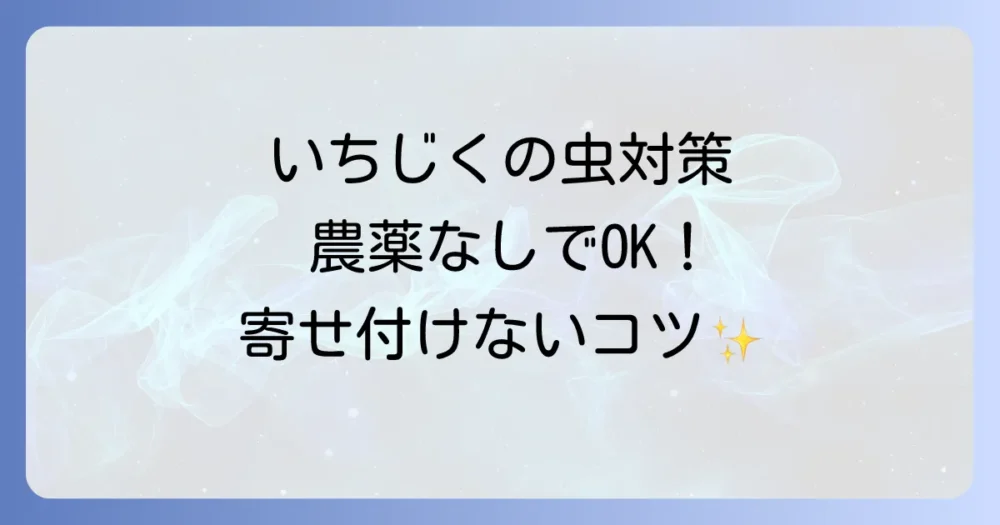
害虫対策で最も重要なのは、虫を発生させない「予防」です。農薬を使わなくても、日々のちょっとした工夫で害虫の発生を大幅に減らすことができます。ここでは、誰でも簡単に始められる予防策をご紹介します。
- 物理的に虫を防ぐ!防虫ネット・袋掛け
- 虫が嫌う環境を作る!剪定と雑草管理
- 天敵を味方につける!コンパニオンプランツと益虫
- 自然由来の力でガード!木酢液・ニームオイルの活用
物理的に虫を防ぐ!防虫ネット・袋掛け
最もシンプルで効果的な予防策が、防虫ネットや袋で物理的に虫の侵入を防ぐ方法です。 カミキリムシの成虫が飛来する時期(5月~7月頃)には、木の幹に目の細かいネットを巻いておくと産卵を防ぐことができます。 また、果実が大きくなり始めたら、一つ一つに袋をかける「袋掛け」も有効です。 アザミウマやショウジョウバエなどの小さな虫の侵入を防ぎ、きれいな果実を収穫するのに役立ちます。 少し手間はかかりますが、その効果は絶大です。
虫が嫌う環境を作る!剪定と雑草管理
害虫は、風通しが悪く湿気の多い場所を好みます。 そこで重要になるのが、適切な剪定です。 混み合った枝を切り、風通しと日当たりを良くすることで、病害虫が発生しにくい環境を作ることができます。 また、畑の周りの雑草はアザミウマなどの害虫の隠れ家や発生源になります。 特にアザミウマの活動が活発になる5月中旬までには、除草を済ませておくのが理想的です。 ただし、害虫がすでに発生している時期に草刈りをすると、虫たちが一斉にいちじくの木へ移動してしまう可能性があるので注意が必要です。
天敵を味方につける!コンパニオンプランツと益虫
害虫を食べてくれるテントウムシやカマキリなどの「益虫」を味方につけるのも、有効な対策の一つです。 益虫が好むような環境を整えることで、害虫の数を自然にコントロールできます。また、特定の植物を一緒に植えることで害虫を遠ざける「コンパニオンプランツ」もおすすめです。 例えば、マリーゴールドは根に寄生するセンチュウを、ニンニクやネギ類はその強い香りで多くのアブラムシなどの害虫を忌避する効果が期待できます。
自然由来の力でガード!木酢液・ニームオイルの活用
化学農薬に頼りたくない方には、自然由来の資材の活用がおすすめです。木酢液や竹酢液は、植物の成長を助ける効果のほか、その独特の燻製のような香りで害虫を寄せ付けにくくする効果があると言われています。また、インド原産の「ニーム」という木から抽出されるニームオイルも、多くの害虫に対して忌避効果や摂食阻害効果があり、有機栽培で広く利用されています。 定期的に希釈して散布することで、害虫が寄り付きにくい環境を維持する助けになります。
もし虫が発生してしまったら?害虫別の駆除方法
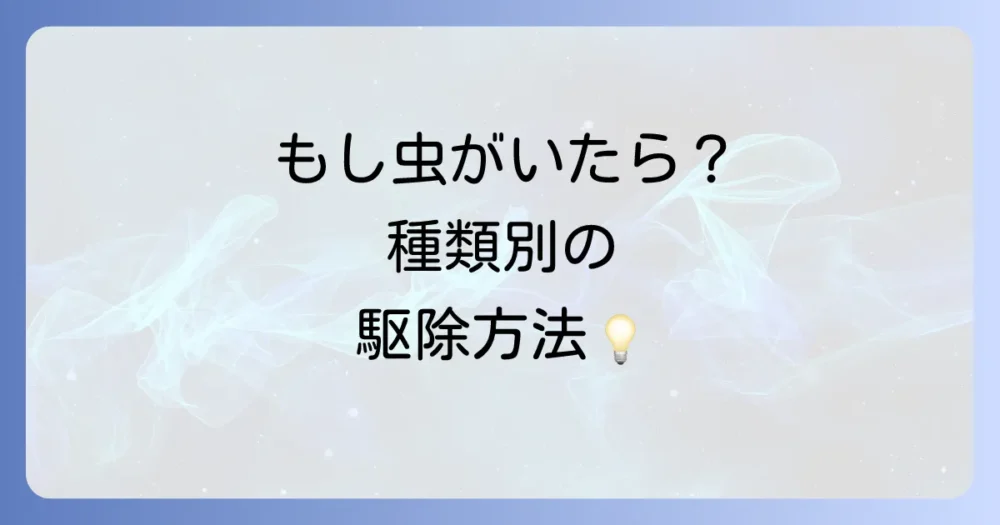
予防策を講じていても、虫が発生してしまうことはあります。大切なのは、被害が広がる前に早期発見し、適切に対処することです。ここでは、害虫の種類に応じた具体的な駆除方法を解説します。
- カミキリムシの駆除方法:幼虫(テッポウムシ)を見つけたら
- アザミウマの駆除方法:粘着シートや薬剤散布
- コガネムシ・イチジクヒトリモドキの駆除方法:見つけ次第捕殺
- アブラムシ・カイガラムシの駆除方法:初期段階での対処が重要
- ショウジョウバエ・アリ・ナメクジの駆除方法
カミキリムシの駆除方法:幼虫(テッポウムシ)を見つけたら
株元に木くずのようなフンを見つけたら、木の内部にカミキリムシの幼虫(テッポウムシ)が侵入しているサインです。 放置すると木が枯れる危険があるため、すぐに対処しましょう。 フンが出ている穴を見つけ、針金を差し込んで幼虫を刺殺する方法が原始的ですが確実です。 また、穴に専用の殺虫剤(園芸用キンチョールEなど)のノズルを差し込み、薬剤を注入する方法も効果的です。 駆除後は、傷口から病原菌が入らないように癒合剤を塗っておくと安心です。
アザミウマの駆除方法:粘着シートや薬剤散布
アザミウマは黄色や青色に誘引される習性があります。 そのため、黄色や青色の粘着トラップを畑に設置することで、成虫を捕獲し、発生状況を確認することができます。 大量に発生してしまった場合は、薬剤による防除も検討します。いちじくに登録のある農薬を使用し、特に被害が出やすい6月上旬から7月にかけて、果実の目が開く前に散布するのが効果的です。
コガネムシ・イチジクヒトリモドキの駆除方法:見つけ次第捕殺
コガネムシの成虫やイチジクヒトリモドキの幼虫は、比較的サイズが大きく見つけやすいため、見つけ次第、手で捕まえて駆除するのが最も手軽で確実な方法です。特にイチジクヒトリモドキの幼虫は、孵化したばかりの頃は葉の裏に集団でいることが多いので、その葉ごと取り除いてしまうのが効率的です。 大量に発生してしまった場合は、適用のある殺虫剤を使用することも検討しましょう。
アブラムシ・カイガラムシの駆除方法:初期段階での対処が重要
アブラムシやカイガラムシは、数が少ないうちに駆除することが鉄則です。発生初期であれば、歯ブラシなどでこすり落としたり、粘着テープで貼り付けて取り除いたりすることができます。牛乳や石鹸水をスプレーする方法も、アブラムシの気門を塞いで窒息させる効果が期待できます。広範囲に広がってしまった場合は、専用の殺虫剤を使用します。カイガラムシは成虫になると硬い殻で覆われて薬剤が効きにくくなるため、幼虫が発生する時期(5月~7月頃)に薬剤を散布するのが効果的です。
ショウジョウバエ・アリ・ナメクジの駆除方法
熟した果実を狙うこれらの害虫には、それぞれの習性を利用した対策が有効です。ショウジョウバエには、めんつゆや酢などを入れたペットボトルで誘引トラップを作るのが効果的です。 アリに対しては、木の幹に粘着テープを巻いたり、輪ゴムを巻いたりすることで、木に登るのを防ぐことができます。 ナメクジは夜行性なので、夜に見回って捕殺するか、ビールを入れた容器を置いておくと誘引されて溺れ死にます。また、熟しすぎた果実や傷んだ果実はこまめに取り除き、害虫の発生源をなくすことも重要です。
それでも解決しない場合に!農薬(殺虫剤)の上手な使い方
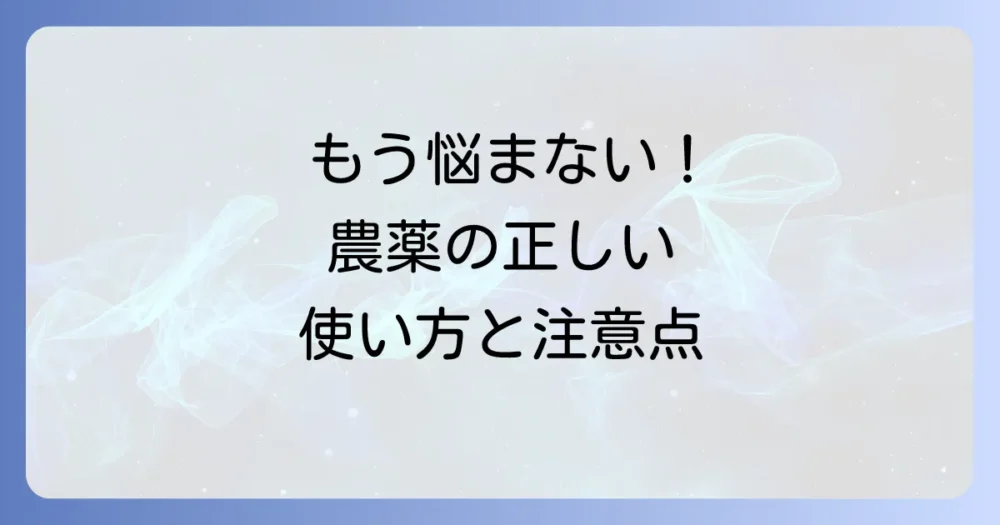
無農薬での対策が難しい場合や、害虫が大量発生してしまった場合には、農薬(殺虫剤)の使用も有効な手段です。ただし、使い方を間違えると効果がなかったり、作物や人体に悪影響を及ぼしたりする可能性もあります。ここでは、農薬を安全かつ効果的に使うためのポイントを解説します。
- いちじくに使用できる農薬の種類
- 農薬を散布する時期とタイミング
- 農薬を使う際の注意点
いちじくに使用できる農薬の種類
農薬は、対象となる害虫や病気、そして作物ごとに登録されています。いちじくに使用できる農薬かどうか、必ずラベルを確認してください。 カミキリムシの幼虫にはスプレータイプの殺虫剤(園芸用キンチョールE、ロビンフッドなど)、アザミウマやアブラムシには散布用の殺虫剤(モスピラン顆粒水和剤、ダントツ水溶剤など)が登録されています。 どの農薬を選べばよいか分からない場合は、ホームセンターの園芸担当者やJAの指導員に相談してみましょう。
農薬を散布する時期とタイミング
農薬は、害虫の活動が活発になる前や、発生初期に散布するのが最も効果的です。 例えば、アザミウマ対策であれば、成虫が飛来し始める5月下旬から6月上旬が重要な防除時期となります。 また、農薬には「収穫前日まで使用可能」「収穫7日前まで」といった使用時期の制限が定められています。 安全にいちじくを食べるためにも、ラベルに記載された使用時期や使用回数を必ず守ってください。
農薬を使う際の注意点
農薬を使用する際は、長袖、長ズボン、マスク、手袋、保護メガネを着用し、薬剤が皮膚に付着したり、吸い込んだりしないように注意しましょう。 風の強い日や雨の日の散布は、薬剤が飛散して近隣に迷惑をかけたり、効果が薄れたりするため避けてください。散布は風のない早朝や夕方に行うのがおすすめです。また、希釈タイプの農薬は、定められた倍率を正確に守ることが大切です。濃すぎると薬害の原因になり、薄すぎると効果が得られません。
よくある質問
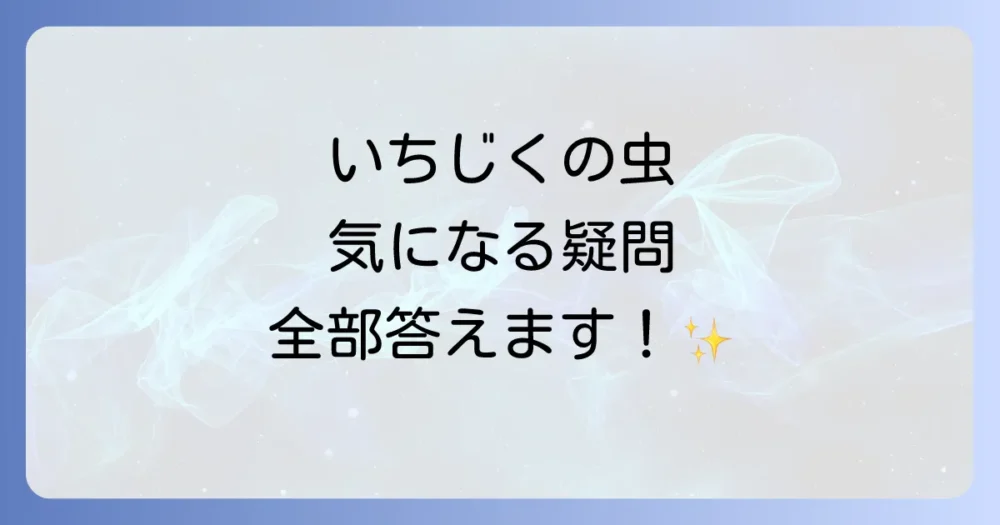
いちじくの実の中にいる虫は食べても大丈夫?
海外産の乾燥いちじくなどでは、受粉を助ける「イチジクコバチ」という蜂のメスが実の中に入り込んでいることがあります。 この蜂は食べても人体に害はないとされていますが、気になる方は取り除いてください。 一方、日本で一般的に栽培されているいちじくの品種は、受粉なしで実がなる「単為結果性」のものがほとんどで、イチジクコバチは日本には生息していないため、基本的に実の中に虫がいることはありません。 もし虫がいた場合は、アザミウマやショウジョウバエの幼虫などの害虫である可能性が高いです。
国産のいちじくに虫は入っていないって本当?
前述の通り、日本のいちじくは受粉を必要としない品種が主流のため、受粉のためのイチジクコバチが実の中に入ることはありません。 しかし、果実の先端の穴からアザミウマやショウジョウバエの幼虫などの害虫が侵入することはあり得ます。 そのため、「国産のいちじくには絶対に虫がいない」とは言い切れません。袋掛けなどの対策をすることで、害虫の侵入をかなりの確率で防ぐことができます。
無農薬でいちじくを育てるのは難しい?
結論から言うと、無農薬でいちじくを育てることは可能です。 いちじくは比較的、病害虫に強い果樹とされています。 しかし、カミキリムシのような致命的な害虫もいるため、完全に放置していては難しいでしょう。 日々の観察を怠らず、剪定や除草などの基本的な管理をしっかり行い、防虫ネットや袋掛けなどの物理的な予防策を組み合わせることが、無農薬栽培を成功させるコツです。
虫除けに効果的なコンパニオンプランツは何?
いちじくの虫除けとして相性の良いコンパニオンプランツには、いくつか種類があります。 根の周りのセンチュウ対策にはマリーゴールド、アブラムシなどの害虫忌避には強い香りを持つニンニク、ニラ、チャイブなどのネギ類がおすすめです。 また、カモミールやラベンダーは、テントウムシなどの益虫を呼び寄せる効果が期待できます。 これらの植物をいちじくの株元近くに植えることで、害虫が寄り付きにくい環境を作ることができます。
アリがたくさんいるのですが、どうすればいいですか?
いちじくの木にアリがたくさんいる場合、いくつかの原因が考えられます。一つは、アブラムシやカイガラムシが発生しており、その甘い排泄物を求めてアリが集まっているケースです。 この場合は、まずアブラムシやカイガラムシを駆除する必要があります。もう一つは、熟した果実の甘い香りに誘われているケースです。 対策としては、木の幹に粘着テープを逆向きに巻いたり、市販のアリ除け剤を木の周りに撒いたりするのが効果的です。 輪ゴムを幹に巻くだけでも、アリが嫌がって登らなくなるという報告もあります。
葉が食べられて穴だらけです。何の虫が原因ですか?
いちじくの葉が穴だらけになる場合、主な原因としてコガネムシの成虫か、イチジクヒトリモドキという蛾の幼虫(毛虫)が考えられます。 コガネムシはキラキラした甲虫で、日中に葉を食害します。 イチジクヒトリモドキの幼虫は黒っぽく毛深い見た目で、特に梅雨時期から夏にかけて大量発生し、葉脈を残してきれいに食べてしまいます。 どちらの虫も、見つけ次第捕殺するのが基本的な対策です。
まとめ
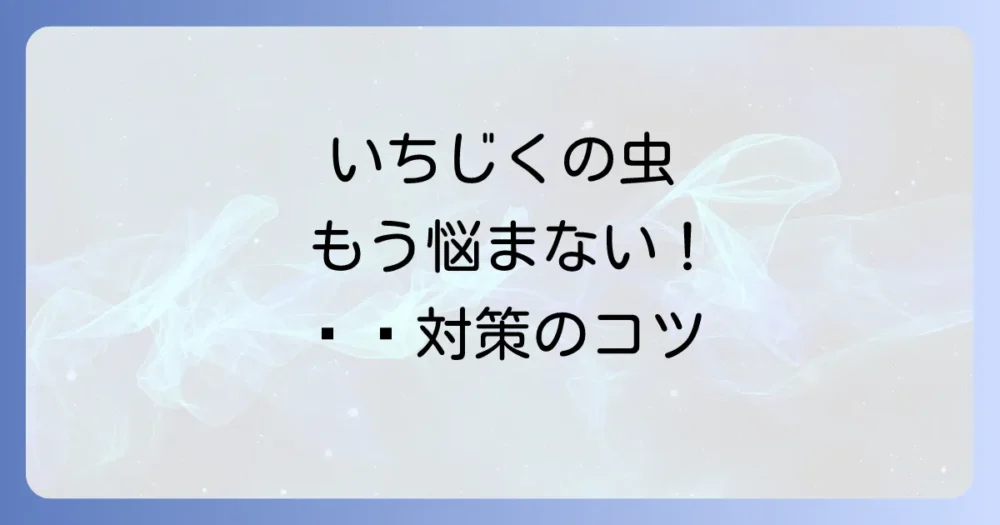
- いちじくの最重要害虫はカミキリムシ。
- 実の中にアザミウマが侵入することがある。
- 葉を食べるのはコガネムシや毛虫の仕業。
- 予防の基本は風通しを良くする剪定。
- 防虫ネットや袋掛けは物理的に虫を防ぐ。
- 雑草は害虫の隠れ家になるのでこまめに除去。
- 天敵の益虫やコンパニオンプランツを活用。
- カミキリムシの幼虫は針金や薬剤で駆除。
- アザミウマには黄色粘着シートが有効。
- アブラムシは初期のうちにこすり落とす。
- アリ対策には幹にテープや輪ゴムを巻く。
- 農薬はラベルを確認し正しく使用する。
- 日本のいちじくに受粉用の蜂は入らない。
- 無農薬栽培は日々の観察と管理が重要。
- 困ったら専門家(JAなど)に相談する。
新着記事