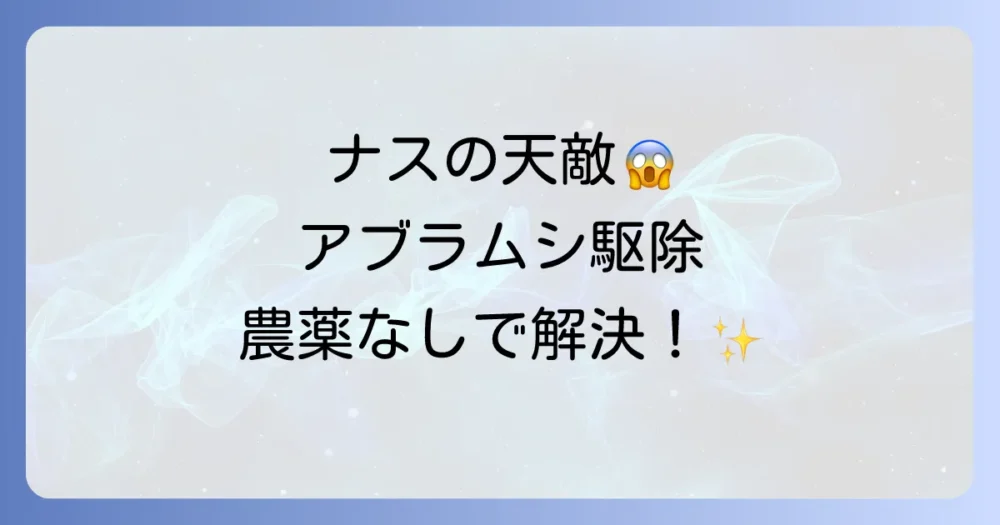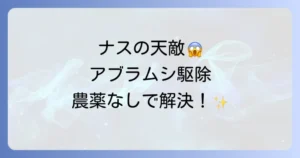家庭菜園で人気のナス。しかし、大切に育てているナスに緑や黒の小さな虫がびっしり…なんて経験はありませんか?その正体は、植物の汁を吸って弱らせる害虫「アブラムシ」かもしれません。放置すると、あっという間に増えてしまい、ナスの生育に深刻な被害を及ぼすことも。本記事では、そんな厄介なアブラムシの駆除方法を、農薬を使わない安全な方法から効果的な農薬まで、幅広くご紹介します。原因や予防策も詳しく解説するので、もうアブラムシに悩まされることはありません。
ナスのアブラムシ、放置は危険!被害と原因を知ろう
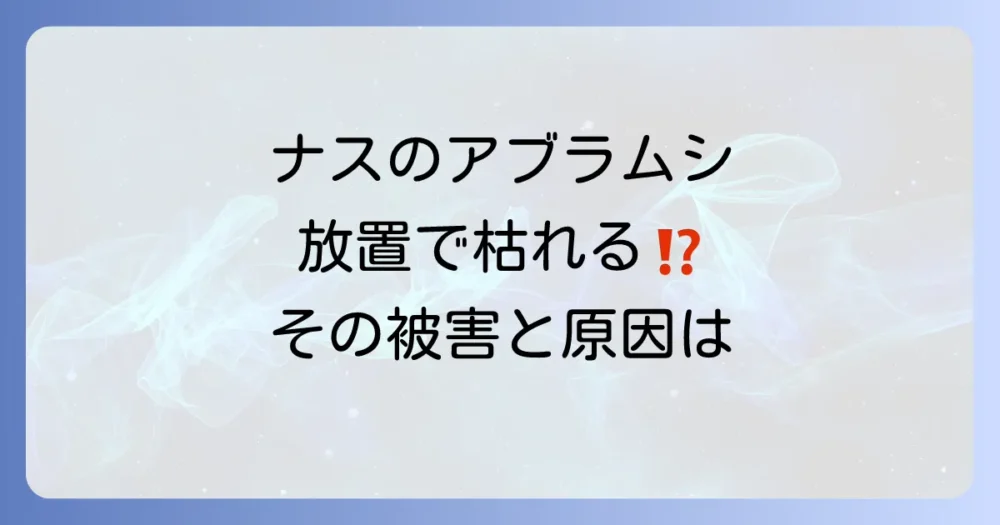
まず、なぜアブラムシを駆除しなければならないのか、その被害と発生原因について理解を深めましょう。敵を知ることが、対策の第一歩です。
この章では、以下の内容について詳しく解説します。
- アブラムシがナスに与える深刻な被害
- なぜ?ナスにアブラムシが発生する主な原因
アブラムシがナスに与える深刻な被害
アブラムシは体長1~4mmほどの小さな虫ですが、その被害は決して小さくありません。 主な被害は3つあります。
1つ目は、吸汁による生育阻害です。アブラムシはナスの葉や茎、新芽などにストロー状の口を刺し込み、栄養分である師管液を吸い取ります。 大量に発生すると、ナスは栄養不足に陥り、葉が縮れたり、生育が著しく悪くなったりします。 最悪の場合、株全体が枯れてしまうこともあるのです。
2つ目は、病気の誘発です。アブラムシの排泄物は「甘露(かんろ)」と呼ばれ、糖分を多く含んでいます。 この甘露を求めてアリが集まってくるだけでなく、これを栄養源として「すす病」という黒いカビが発生することがあります。 すす病になると葉の表面が黒いすすで覆われ、光合成が妨げられてしまい、ナスの生育がさらに悪化します。
そして3つ目が、ウイルス病の媒介です。羽の生えたアブラムシは、他の植物からウイルスを運んできて、ナスに感染させることがあります。 代表的なものに「モザイク病」があり、感染すると葉にモザイク状の模様が現れ、生育不良を引き起こします。 モザイク病には治療薬がないため、感染を防ぐにはアブラムシの飛来を防ぐことが非常に重要です。
なぜ?ナスにアブラムシが発生する主な原因
アブラムシは、なぜあなたのナスに発生してしまったのでしょうか。主な原因は3つ考えられます。
1つ目は、窒素肥料の与えすぎです。窒素は植物の成長に欠かせない栄養素ですが、与えすぎると植物体内のアミノ酸が増加します。 アブラムシはこのアミノ酸が大好物なため、窒素過多のナスはアブラムシにとって格好の餌場となってしまうのです。
2つ目は、風通しの悪さです。葉が茂りすぎて株の内部が蒸れていると、アブラムシにとって快適な環境になります。 また、風通しが悪いと天敵であるテントウムシなども寄り付きにくくなるため、アブラムシが繁殖しやすくなります。
3つ目は、外部からの飛来です。アブラムシは、春や秋の過ごしやすい時期になると、羽の生えた個体(有翅虫)が出現し、風に乗って広範囲に移動します。 近くの畑や雑草地から飛んできて、あなたのナスに住み着いてしまうのです。特に5月~6月と9月~10月は発生しやすい時期なので注意が必要です。
今すぐできる!農薬を使わないアブラムシ駆除方法8選
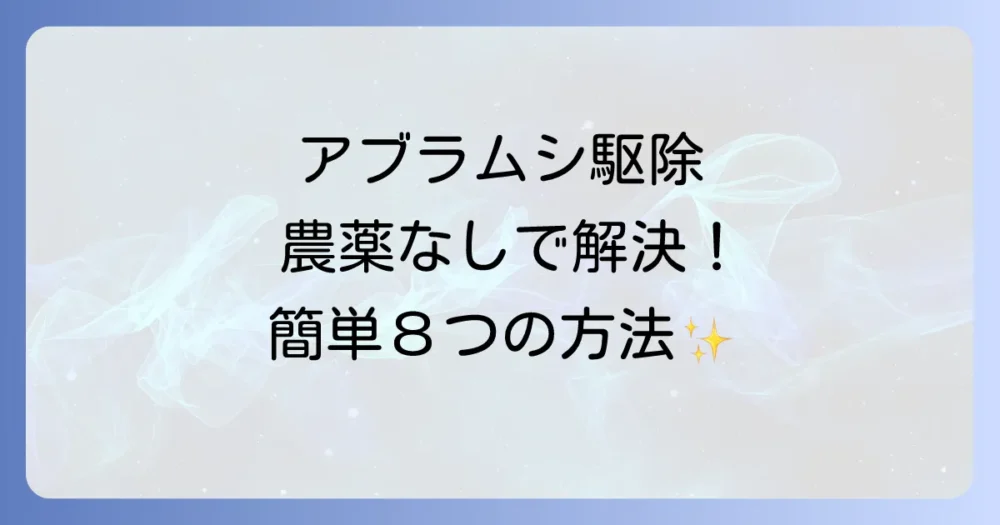
「野菜に農薬は使いたくない」と考える方は多いでしょう。ここでは、家庭で手軽に試せる、農薬を使わないアブラムシの駆除方法を8つ紹介します。発生初期であれば、これらの方法で十分に対応可能です。
この章で紹介する方法は以下の通りです。
- 【物理的に駆除】テープや歯ブラシで取り除く
- 【スプレーで駆除】牛乳スプレーの作り方と使い方
- 【スプレーで駆除】石鹸水スプレーの効果と注意点
- 【スプレーで駆除】木酢液・竹酢液の忌避効果
- 【益虫に頼る】天敵(テントウムシなど)を味方につける
- 【光で撃退】キラキラ光るアルミホイルやシルバーマルチ
- 【水で洗い流す】勢いのある水流で吹き飛ばす
- 【油で窒息させる】油せっけん水の作り方と使い方
【物理的に駆除】テープや歯ブラシで取り除く
アブラムシの数がまだ少ない初期段階であれば、物理的に取り除くのが最も手軽で確実な方法です。セロハンテープやガムテープなどの粘着テープを使い、葉の裏などにいるアブラムシをペタペタと貼り付けて取り除きます。 粘着力が強すぎると葉を傷める可能性があるので、布テープなど少し粘着力の弱いものがおすすめです。
また、使い古しの歯ブラシで優しくこすり落とす方法も効果的です。 葉の裏や茎の付け根など、凹凸のある場所にも届きやすいのがメリットです。取り除いたアブラムシは、その場で潰すか、袋に入れて処分し、再びナスに戻らないようにしましょう。
【スプレーで駆除】牛乳スプレーの作り方と使い方
牛乳を使った駆除方法は、安全性が高く人気の方法です。牛乳をスプレーでアブラムシに吹きかけると、乾燥する過程で牛乳の脂肪分が膜となり、アブラムシの気門(呼吸するための穴)を塞いで窒息死させることができます。
作り方はとても簡単で、牛乳と水を1:1の割合で混ぜるだけ。 スプレーボトルに入れて、アブラムシが発生している場所にまんべんなく吹きかけます。特に葉の裏は念入りに散布しましょう。効果を高めるため、晴れた日の午前中に散布するのがおすすめです。ただし、散布した後は牛乳が腐敗して臭いやカビの原因になることがあるため、数時間後には必ず水で洗い流してください。
【スプレーで駆除】石鹸水スプレーの効果と注意点
石鹸水も牛乳と同様に、アブラムシを窒息させて駆除する方法です。 500mlの水に対して、食器用洗剤などの液体石鹸を2~3滴混ぜて作ります。 これをスプレーボトルに入れ、アブラムシに直接かかるように散布します。
この方法も非常に手軽ですが、注意点があります。石鹸の濃度が高すぎると、ナスの葉を傷めてしまう可能性があります。 必ず薄めて使用し、散布後は牛乳スプレーと同様に、水でしっかりと洗い流すことが重要です。 また、使用する石鹸は、香料や添加物の少ない、なるべくシンプルなものを選びましょう。
【スプレーで駆除】木酢液・竹酢液の忌避効果
木酢液や竹酢液は、木炭や竹炭を作る際に出る煙を冷却して液体にしたものです。これ自体に殺虫効果はほとんどありませんが、その独特の燻製のような臭いをアブラムシが嫌うため、忌避(きひ)効果が期待できます。
使用する際は、製品の規定に従って水で500~1000倍程度に薄め、スプレーで散布します。 既に発生してしまったアブラムシを駆除するというよりは、「これ以上寄せ付けない」という予防的な目的で使うのが効果的です。 定期的に散布することで、アブラムシが寄り付きにくい環境を作ることができます。
【益虫に頼る】天敵(テントウムシなど)を味方につける
自然界には、アブラムシを食べてくれる頼もしい味方(天敵)がたくさんいます。その代表格がテントウムシです。特にナナホシテントウやナミテントウの幼虫・成虫は、1日に何十匹、何百匹ものアブラムシを捕食してくれます。 その他にも、ヒラタアブの幼虫やクサカゲロウの幼虫、寄生バチなどもアブラムシの天敵です。
これらの天敵を畑に呼び込むためには、農薬の使用を控えることが大切です。 また、天敵の隠れ家や餌となるような多様な植物(コンパニオンプランツなど)を近くに植えることも有効です。天敵が活動しやすい環境を整えることで、アブラムシの発生を自然に抑制することができます。
【光で撃退】キラキラ光るアルミホイルやシルバーマルチ
アブラムシは、キラキラと乱反射する光を嫌う習性があります。 この習性を利用したのが、アルミホイルやシルバーマルチ(銀色の農業用シート)を使った対策です。
やり方は簡単で、ナスの株元に、くしゃくしゃにしたアルミホイルを敷き詰めたり、シルバーマルチを張ったりするだけです。 太陽の光が乱反射することで、アブラムシが方向感覚を失い、ナスに寄り付きにくくなります。 これは、アブラムシが飛来してくるのを防ぐ予防策として非常に効果的です。また、地温の上昇を抑える効果や、雑草の発生を抑制する副次的な効果も期待できます。
【水で洗い流す】勢いのある水流で吹き飛ばす
アブラムシは体が小さく、植物にしっかりとしがみついているわけではありません。そのため、ホースやスプレーのジェット水流など、勢いの強い水で洗い流すだけでも、ある程度の数を駆除することができます。
特に葉の裏に集まっているアブラムシを狙って、下から上に向かって水をかけると効果的です。ただし、水の勢いが強すぎると、ナスの葉や花を傷つけてしまう可能性があるので注意が必要です。また、この方法は一時的な対策であり、地面に落ちたアブラムシが再び這い上がってくることもあるため、他の方法と組み合わせることをおすすめします。
【油で窒息させる】油せっけん水の作り方と使い方
牛乳や石鹸水と同様に、油を使ってもアブラムシを窒息させることができます。特に「油せっけん水」は、油と石鹸を組み合わせることで効果を高めたものです。
作り方は、水500mlに対して、サラダ油などの植物油を小さじ1杯、無添加の液体石鹸を数滴加えてよく混ぜ合わせます。 石鹸には、水と油を混ざりやすくする乳化剤の役割があります。これをスプレーボトルに入れ、アブラムシに直接散布します。油膜がアブラムシをしっかりと覆い、窒息させる効果が期待できます。 散布は涼しい時間帯に行い、翌日には水で軽く洗い流しておくと、植物への負担を減らすことができます。
それでもダメなら…効果的な農薬(殺虫剤)の選び方と使い方
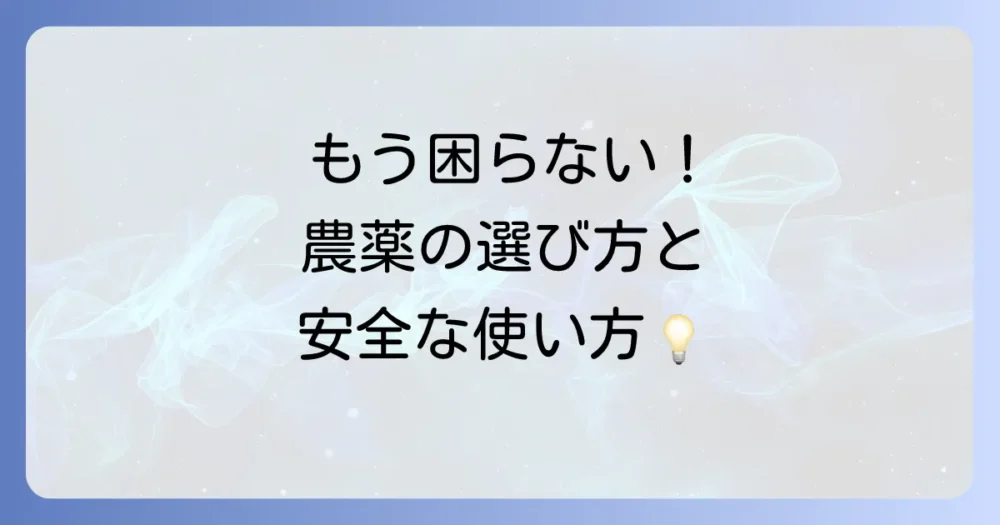
無農薬での駆除を試みても、アブラムシが大量発生して手に負えなくなってしまうこともあります。そんな時は、無理せず農薬(殺虫剤)の力を借りるのも一つの手です。ここでは、農薬の選び方と安全な使い方について解説します。
この章では、以下の内容について詳しく解説します。
- 農薬を使うメリットとデメリット
- 【初心者向け】おすすめのスプレータイプ農薬
- 【効果が持続】おすすめの粒剤タイプ農薬
- 農薬を使う際の注意点
農薬を使うメリットとデメリット
農薬を使用する最大のメリットは、迅速かつ高い効果が期待できることです。大量に発生したアブラムシを短時間で駆除し、被害の拡大を食い止めることができます。また、製品によっては、効果が一定期間持続し、予防にも繋がるものがあります。
一方、デメリットとしては、天敵などの益虫にも影響を与えてしまう可能性があることや、使用方法を誤ると作物や人体に影響を及ぼすリスクがあることが挙げられます。また、同じ系統の農薬を使い続けると、その農薬が効きにくい「抵抗性」を持ったアブラムシが出現することもあります。 メリットとデメリットをよく理解した上で、適切に使用することが重要です。
【初心者向け】おすすめのスプレータイプ農薬
家庭菜園で手軽に使えるのが、スプレータイプの農薬です。希釈する必要がなく、見つけたらすぐにシュッと吹きかけることができます。
「ベニカXネクストスプレー」などの商品は、アブラムシだけでなく、うどんこ病などの病気にも効果があるため、1本あると非常に便利です。 殺虫成分が葉に浸透し、葉の裏に隠れている害虫にも効果を発揮するタイプ(浸透移行性)のものを選ぶと、より高い効果が期待できます。 食品成分由来で収穫前日まで使える「ピュアベニカ」のような製品もあり、安全性を重視する方におすすめです。
【効果が持続】おすすめの粒剤タイプ農薬
より長期間の効果を期待するなら、粒剤タイプの農薬がおすすめです。「家庭園芸用GFオルトラン粒剤」などが代表的です。
このタイプの農薬は、ナスの株元にパラパラと撒くだけで、有効成分が根から吸収され、植物全体に行き渡ります。 これにより、直接薬がかからなかったアブラムシや、後から飛来してきたアブラムシも、ナスを吸汁することで駆除できます。効果は約2~3週間持続するため、予防効果も高く、散布の手間が省けるのが大きなメリットです。 植え付け時に土に混ぜ込むタイプもあります。
農薬を使う際の注意点
農薬を使用する際は、必ず製品のラベルに記載されている使用方法、使用時期、使用回数、希釈倍率などを厳守してください。 これらは、作物を安全に収穫するために定められた重要なルールです。
特に、収穫までの日数(使用禁止期間)は必ず守りましょう。また、散布する際は、風のない天気の良い日を選び、マスクや手袋、保護メガネなどを着用して、薬剤を吸い込んだり、皮膚に付着したりしないように注意が必要です。近隣の畑や住宅に薬剤が飛散しないよう、風向きにも十分配慮しましょう。
もう発生させない!アブラムシの徹底予防策
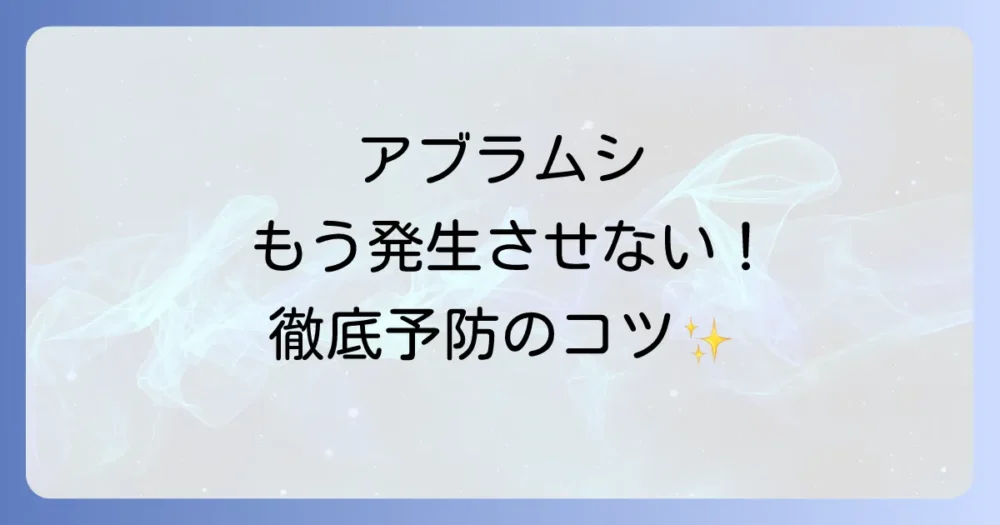
アブラムシは、一度発生すると駆除が大変です。最も大切なのは、そもそもアブラムシを発生させない、寄せ付けない環境を作ること。ここでは、明日から実践できる徹底予防策をご紹介します。
この章で紹介する予防策は以下の通りです。
- 植え付け時から対策!防虫ネットの活用
- 肥料のやり方を見直す(窒素過多に注意)
- 風通しを良くする剪定
- コンパニオンプランツを植える
植え付け時から対策!防虫ネットの活用
アブラムシの飛来を防ぐ最も物理的で効果的な方法が、防虫ネットです。 ナスの苗を植え付けた直後から、支柱を立ててトンネル状に防虫ネットをかけることで、羽の生えたアブラムシが侵入するのを防ぎます。
選ぶ際は、網目が1mm以下の細かいものを選びましょう。 ネットの裾に隙間ができないように、土でしっかりと埋めるか、専用のピンで固定することが重要です。隙間があると、そこから害虫が侵入してしまうため、注意してください。物理的に侵入を防ぐため、非常に効果の高い予防策です。
肥料のやり方を見直す(窒素過多に注意)
前述の通り、アブラムシは窒素成分が多い植物を好みます。 ナスの実をたくさん収穫したいからといって、窒素成分の多い化学肥料を過剰に与えるのは避けましょう。
肥料は、製品に記載された適量を守り、バランスの取れたものを使用することが大切です。特に、ゆっくりと効果が現れる有機肥料やぼかし肥料を活用すると、急激な窒素過多を防ぐことができます。適切な施肥管理は、アブラムシ予防の基本中の基本です。
風通しを良くする剪定
ナスの葉が茂ってくると、株の中心部の風通しが悪くなり、湿気がこもりやすくなります。これはアブラムシにとって絶好の隠れ家であり、繁殖場所となってしまいます。
混み合っている葉や、黄色くなった古い葉、内側に向かって伸びている枝などを定期的に剪定(せんてい)し、株全体の風通しと日当たりを良くしましょう。 これにより、アブラムシが住み着きにくい環境になるだけでなく、病気の予防にも繋がります。また、株の様子を観察する良い機会にもなり、アブラムシの早期発見に繋がります。
コンパニオンプランツを植える
コンパニオンプランツとは、一緒に植えることでお互いに良い影響を与え合う植物のことです。アブラムシ対策として有効なコンパニオンプランツをナスの近くに植えることで、被害を軽減することができます。
例えば、マリーゴールドの根にいる微生物が土壌のセンチュウを減らす効果があるほか、その独特の香りが害虫を遠ざけると言われています。 また、カモミールやニンニクなども、アブラムシを寄せ付けにくくする効果が期待できます。 天敵であるテントウムシを呼び寄せる効果のある植物を植えるのも良いでしょう。ただし、植物同士の相性もあるため、事前に調べてから植えるようにしましょう。
よくある質問
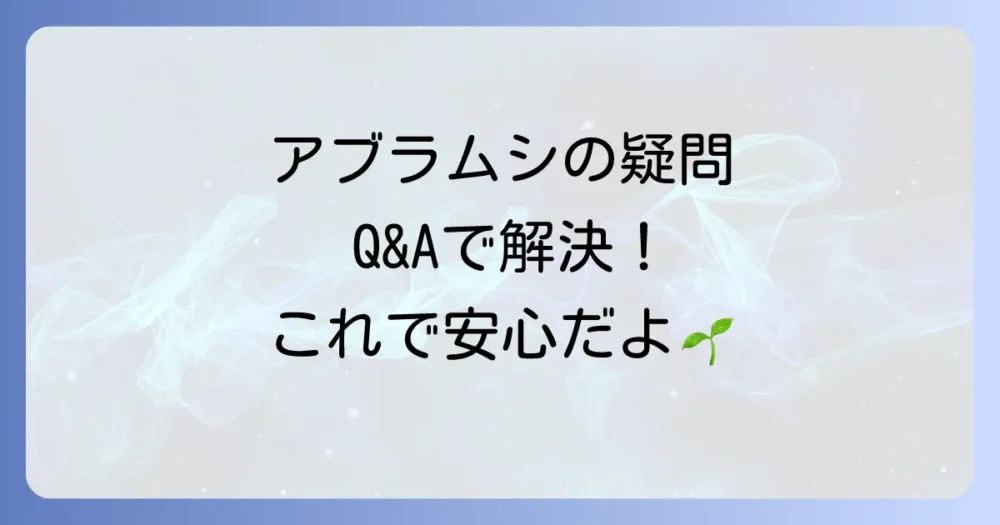
アブラムシ駆除に酢は効きますか?
お酢を水で薄めたスプレーも、アブラムシ駆除に効果があると言われています。お酢に含まれる酢酸が、アブラムシの体を柔らかくして駆除する効果や、忌避効果が期待できます。作り方は、穀物酢などを水で10倍程度に薄めてスプレーします。 ただし、濃度が濃すぎると植物を傷める可能性があるため、注意が必要です。
アブラムシが大量発生してしまったらどうすればいいですか?
大量に発生してしまった場合は、まずホースの強い水流である程度洗い流し、数を減らしましょう。 その後、牛乳スプレーや石鹸水スプレーなどを散布します。それでも手に負えない場合は、無理をせず、即効性のある農薬(殺虫剤)の使用を検討するのが現実的です。被害が広がる前に、迅速に対処することが重要です。
天敵のテントウムシはどこで手に入りますか?
テントウムシは、農薬を使っていない公園や草地などで見つけることができます。また、近年では、害虫駆除用の天敵製剤として、テントウムシやコレマンアブラバチなどが市販されている場合もあります。 農業資材店やオンラインショップで探してみるのも一つの方法です。
牛乳スプレーの後、洗い流さないとどうなりますか?
牛乳スプレーを散布した後に洗い流さないと、乾燥した牛乳が葉に残り、悪臭の原因になったり、カビが発生したりすることがあります。 また、葉の気孔を塞いでしまい、植物の呼吸を妨げる可能性も考えられます。アブラムシを窒息させる効果が出た後は、必ず水で綺麗に洗い流すようにしましょう。
まとめ
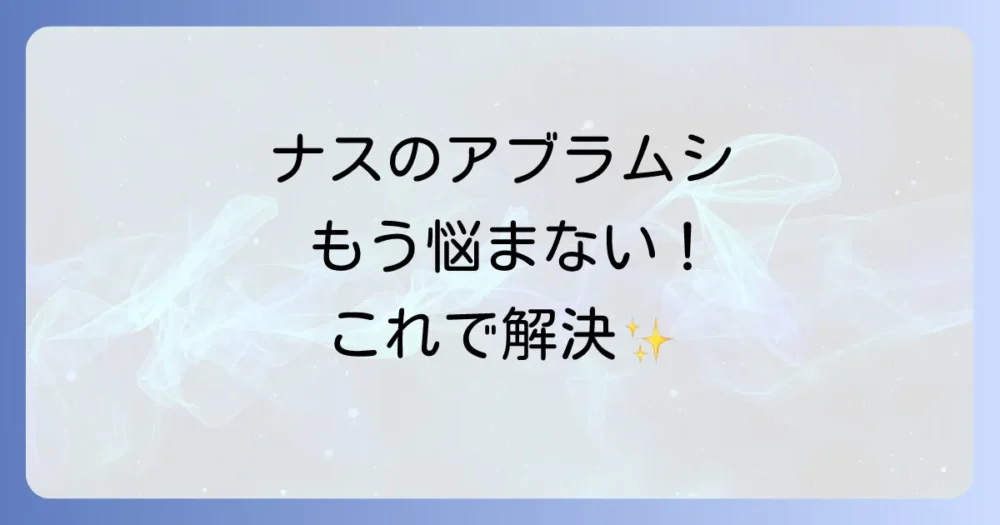
- アブラムシは吸汁被害、すす病、ウイルス病を引き起こす。
- 窒素肥料の過多や風通しの悪さが主な発生原因。
- 農薬を使わない駆除法にはテープや歯ブラシでの除去がある。
- 牛乳や石鹸水のスプレーはアブラムシを窒息させる。
- 木酢液には殺虫効果はなく、忌避効果が期待できる。
- 天敵のテントウムシなどを活用するのも有効な手段。
- アルミホイルの光の反射でアブラムシを寄せ付けない。
- 勢いのある水流で物理的に洗い流すことも可能。
- 手に負えない場合はスプレーや粒剤タイプの農薬を使う。
- 農薬使用時はラベルの指示を必ず守ること。
- 予防策として防虫ネットの活用が非常に効果的。
- 肥料の適量管理と風通しを良くする剪定が重要。
- コンパニオンプランツを植えて害虫を遠ざける。
- 大量発生時はまず水で流し、薬剤の使用を検討する。
- 駆除と予防を組み合わせ、ナスをアブラムシから守ることが大切。