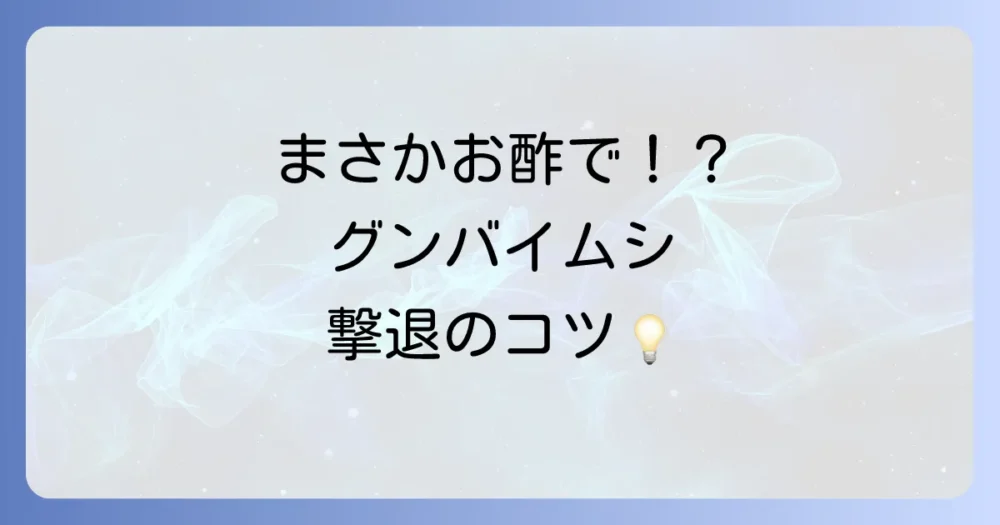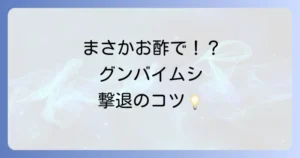大切に育てている庭木やベランダの植物の葉が、なんだか白っぽくカサカサに…。よく見ると、葉の裏に小さな虫がびっしり!その正体、もしかしたら「グンバイムシ」かもしれません。繁殖力が強く、あっという間に広がるグンバイムシの被害に、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。「できれば農薬は使いたくない」「家庭にあるもので手軽に対策したい」そんな時に思いつくのが「お酢」を使った駆除方法。本記事では、グンバイムシ駆除におけるお酢の効果から、具体的な使い方、さらにはお酢以外の安全な対策法まで、あなたの悩みを解決するための情報を詳しく解説していきます。
グンバイムシ駆除に「酢」は効果があるの?気になる真実
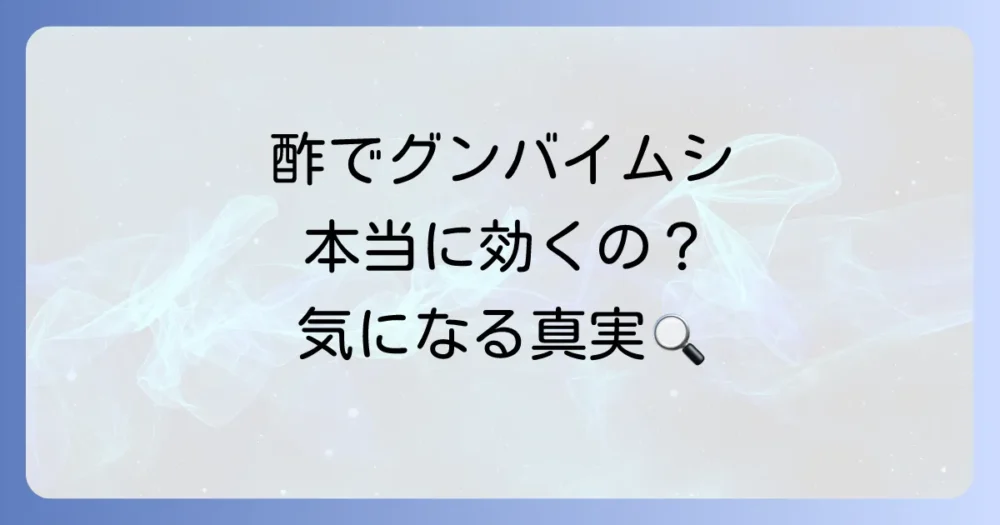
家庭にある身近な調味料「お酢」が、本当にやっかいな害虫駆除に使えるのでしょうか。農薬を使いたくないと考える方にとって、その効果は非常に気になるところです。ここでは、グンバイムシに対するお酢の効果について、その真実に迫ります。
本章では、以下の内容で解説を進めていきます。
- 結論:酢には限定的な忌避効果が期待できる
- なぜ酢がグンバイムシに効くとされるのか?
- 酢を使った駆除のメリット・デメリット
結論:酢には限定的な忌避効果が期待できる
結論から言うと、お酢にはグンバイムシに対する直接的な殺虫効果はほとんど期待できません。しかし、グンバイムシが嫌う「におい」による忌避(きひ)効果、つまり虫を寄せ付けにくくする効果は一定程度期待できます。 お酢の主成分である酢酸のツンとした刺激臭を害虫が嫌うため、散布することでグンバイムシが寄り付きにくい環境を作ることができるのです。
ただし、これはあくまで「寄せ付けにくくする」効果です。すでに大量発生してしまったグンバイムシを完全に駆除する力はありません。また、効果の持続時間も短いため、こまめな散布が必要になります。お酢での対策は、発生初期や予防策の一つとして捉えるのが良いでしょう。
なぜ酢がグンバイムシに効くとされるのか?
お酢が害虫対策に効果があるとされる主な理由は、その主成分である「酢酸」にあります。 酢酸には、以下のような働きがあると考えられています。
- 強い刺激臭による忌避効果: 多くの昆虫は、お酢のツンとした酸っぱいにおいを嫌います。このにおいを植物にまとわせることで、グンバイムシが寄り付くのを防ぐ効果が期待されます。
- 抗菌・殺菌作用: お酢には菌の繁殖を抑える働きがあります。 植物の病気の原因となる菌を減らすことで、植物自体を健康に保ち、結果的に害虫がつきにくい環境を作る手助けになります。
これらの作用により、お酢は化学薬品を使わない自然派の害虫対策として注目されています。しかし、前述の通り、その効果は殺虫ではなく、あくまで忌避や環境改善が中心であることを理解しておくことが重要です。
酢を使った駆除のメリット・デメリット
お酢を使ったグンバイムシ対策には、良い点と注意すべき点があります。両方を理解した上で、ご自身の状況に合わせて活用することが大切です。
メリット
安全性が高い: 食品であるお酢は、人間やペット、そして環境に対して非常に安全です。小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使用できます。
手軽で安価: どこの家庭にもある調味料なので、思い立ったらすぐに、そして安価に対策を始めることができます。
植物への影響が少ない(正しく使えば): 適切な濃度に薄めて使用すれば、化学農薬に比べて植物への負担が少ないとされています。
デメリット
殺虫効果はほぼない: 大量に発生したグンバイムシを駆除する力はありません。あくまで忌避効果が主体です。
効果の持続性が低い: 雨が降ったり、時間が経ったりすると効果が薄れてしまうため、定期的な散布が必要です。
濃度を間違えると植物を傷める: 酢の酸が強すぎると、植物の葉を傷つけたり、土壌の酸性度を変えてしまったりする可能性があります。
においが気になる: 散布中や散布後しばらくは、お酢のにおいが気になる場合があります。
これらのメリット・デメリットを踏まえ、お酢は「グンバイムシを寄せ付けないための予防策」や「発生ごく初期の応急処置」として活用するのが最も効果的と言えるでしょう。
【実践編】お酢を使ったグンバイムシ対策スプレーの作り方と使い方
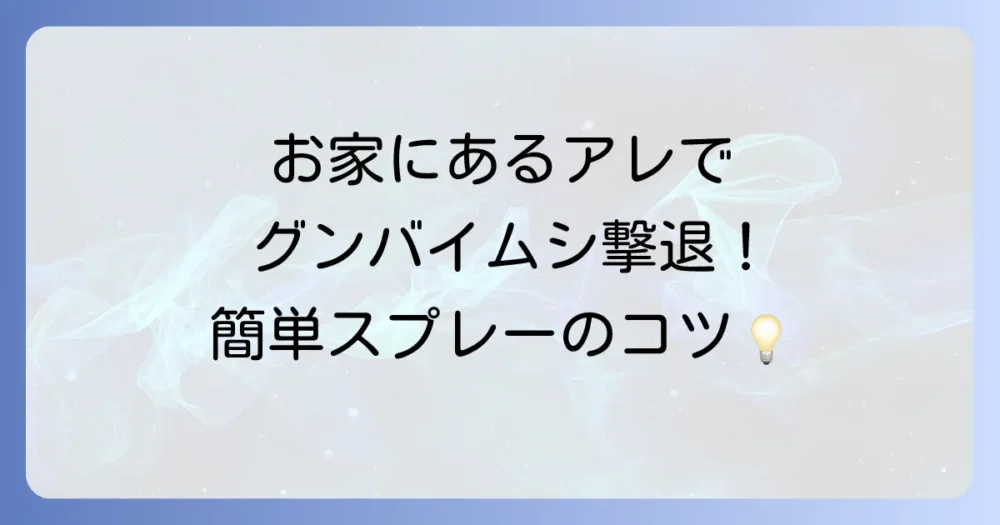
お酢がグンバイムシに対して限定的ながら忌避効果を持つことが分かりました。では、実際にどのように使えば良いのでしょうか。ここでは、誰でも簡単に作れる「お酢スプレー」の作り方から、効果的な散布方法、そして使用する上での大切な注意点までを具体的に解説します。
この章でご紹介するのは、以下の内容です。
- 用意するもの
- 作り方の手順
- 効果的な散布方法とタイミング
- 使用上の注意点
用意するもの
まず、お酢スプレー作りに必要なものを揃えましょう。特別なものは必要なく、ご家庭にあるもので手軽に準備できます。
- 食酢: 穀物酢や米酢など、一般的なもので構いません。糖分などが含まれていない、シンプルな醸造酢を選びましょう。
- 水: 水道水で大丈夫です。
- スプレーボトル: 霧吹きなど、液体を噴霧できる容器を用意してください。100円ショップなどで手に入ります。
- (お好みで)展着剤代わりの食器用洗剤: ほんの数滴加えることで、スプレー液が葉に付着しやすくなります。ただし、入れすぎには注意が必要です。
これだけです。とてもシンプルでしょう?準備が整ったら、早速作っていきましょう。
作り方の手順
お酢スプレーの作り方は非常に簡単です。ポイントは「濃度」です。濃すぎると植物を傷めてしまう原因になるので、必ず希釈して使いましょう。
- お酢を水で薄める: 基本的な希釈倍率は、水とお酢を1:1の割合で混ぜ合わせます。 例えば、500mlのスプレーボトルなら、水250ml、お酢250mlが目安です。植物の種類や状態によっては、もう少し薄め(水3:酢1など)から試すとより安全です。
- (お好みで)食器用洗剤を加える: 展着剤として食器用洗剤を加える場合は、500mlのスプレー液に対して1〜2滴で十分です。入れすぎると泡立ってしまい、植物にも良くありません。
- よく混ぜる: スプレーボトルの蓋をしっかりと閉め、よく振って水と酢(と洗剤)を均一に混ぜ合わせたら完成です。
たったこれだけで、安全な手作り防虫スプレーが出来上がります。とても簡単なので、ぜひ試してみてください。
効果的な散布方法とタイミング
せっかく作ったお酢スプレーも、使い方が正しくなければ効果は半減してしまいます。効果を最大限に引き出すための散布方法とタイミングを覚えておきましょう。
- 散布場所: グンバイムシは葉の裏に潜んでいることがほとんどです。 そのため、葉の表面だけでなく、葉の裏側まで念入りに、しずくが滴るくらいたっぷりと散布するのが最も重要です。茎や枝にも忘れずに散布しましょう。
- 散布のタイミング: 散布に最適な時間帯は、日差しの弱い朝方か夕方です。 日中の強い日差しの下で散布すると、葉に残った水滴がレンズの役割をして葉焼けを起こす原因になります。
- 散布の頻度: お酢の効果は長続きしません。そのため、週に1〜2回を目安に定期的に散布するのがおすすめです。 特に、雨が降った後は効果が流れてしまうため、雨上がりに再度散布すると効果的です。
この3つのポイントを押さえることで、お酢スプレーの忌避効果をより高めることができます。
使用上の注意点
手軽で安全なお酢スプレーですが、いくつか注意点があります。大切な植物を守るためにも、以下の点は必ず守ってください。
- 必ず薄めて使う: 原液のまま散布するのは絶対にやめましょう。強い酸性が植物の細胞を破壊し、枯らしてしまう原因になります。
- 最初は試し吹きをする: 植物によっては、お酢に対して敏感に反応する場合があります。初めて使用する際は、まず数枚の葉にだけスプレーしてみて、数日間様子を見る「試し吹き」を行うと安心です。
- 花や実にはかけない: 花びらや果実の部分は特にデリケートです。変色や傷みの原因になることがあるため、直接かからないように注意しましょう。
- 高温時の使用は避ける: 気温が高い時に散布すると、植物への負担が大きくなります。真夏の炎天下などは避け、涼しい時間帯を選んでください。
これらの注意点を守り、正しく使うことで、お酢はガーデニングの心強い味方になってくれるでしょう。
酢だけじゃない!農薬を使わないグンバイムシ駆除方法
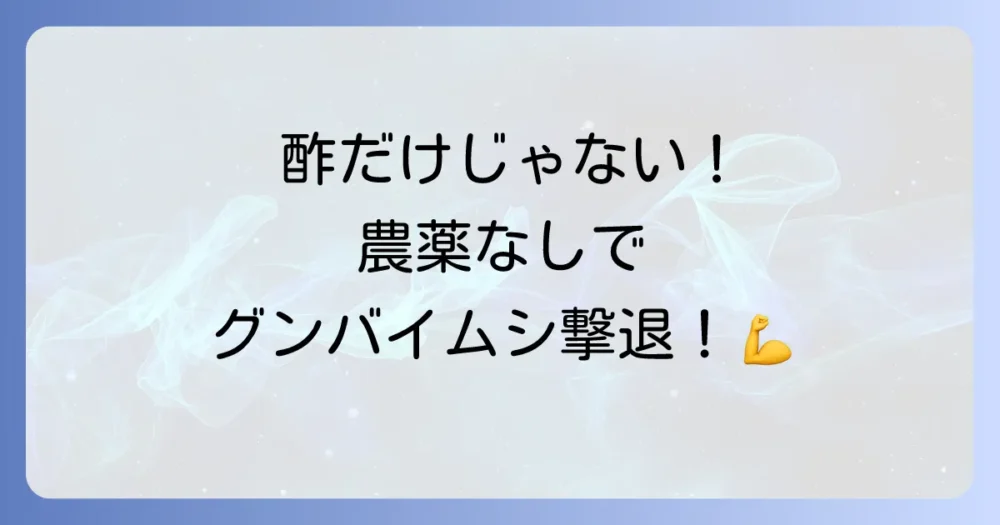
お酢スプレーは手軽な予防策ですが、すでに発生してしまったグンバイムシには力不足な面も。しかし、農薬を使いたくないという方のために、お酢以外にも試せる自然派の駆除方法がいくつか存在します。ここでは、物理的に駆除する方法から、他の自然由来成分を活用する方法まで、幅広くご紹介します。
この章で解説するのは、以下の内容です。
- 発生初期に有効!物理的な駆除方法
- 自然由来の成分を活用する方法
発生初期に有効!物理的な駆除方法
グンバイムシの数がまだ少ない発生初期であれば、薬剤を使わずに物理的に取り除く方法が非常に効果的です。地道な作業ですが、確実性が高く、植物へのダメージも最小限に抑えられます。
強力な水流で洗い流す
ホースのノズルをジェット水流などに設定し、葉の裏に潜むグンバイムシを強力な水圧で吹き飛ばすというシンプルな方法です。 特に、幼虫は集団でいることが多いため、一網打尽にできる可能性があります。ポイントは、葉の裏側を狙って、下から上に向かって水をかけることです。植物が傷まない程度の水圧に調整しながら行いましょう。定期的に葉水を与えることは、乾燥を嫌うグンバイムシの予防にも繋がります。
粘着テープやブラシで取り除く
ガムテープや粘着クリーナー(コロコロ)の粘着面を葉の裏にペタペタと押し当てて、グンバイムシをくっつけて捕獲する方法です。 幼虫だけでなく、動きの鈍い成虫にも有効です。また、使い古しの歯ブラシなどで葉の裏を優しくこすり落とす方法もあります。葉を傷つけないように、力加減には注意してください。
被害のひどい葉や枝の剪定
すでにびっしりとグンバイムシに覆われ、白く変色してしまった葉は、回復が見込めません。このような被害が深刻な葉や枝は、思い切って剪定してしまうのが得策です。 これにより、見た目が良くなるだけでなく、そこに潜む成虫や卵をまとめて処分でき、被害の拡大を防ぐことができます。切り取った葉や枝は、ビニール袋などに入れてしっかりと口を縛り、速やかに処分しましょう。
自然由来の成分で駆除する方法
物理的な駆除と合わせて、他の自然由来の成分を使ったスプレーを試すのも良い方法です。お酢と同様に、安全性が高く、手軽に試せるものがいくつかあります。
木酢液・竹酢液の効果と使い方
木酢液(もくさくえき)や竹酢液(ちくさくえき)は、木炭や竹炭を焼くときに出る煙を冷やして液体にしたものです。 これらには独特の燻製のような香りがあり、お酢と同様に害虫の忌避効果が期待できます。 また、土壌の有用な微生物を増やし、植物の成長を助ける土壌改良効果もあるとされています。 使い方はお酢スプレーと同様で、製品に記載されている希釈倍率(一般的には500〜1000倍)に水で薄めて、葉の裏を中心に散布します。直接的な殺虫効果はありませんが、植物を健康に保ちながら害虫を遠ざける、予防的な使い方として非常に有効です。
牛乳スプレーも効果あり?
牛乳を水で薄めてスプレーする方法も、アブラムシ対策などで知られています。これは、スプレーした牛乳が乾燥する際に膜を作り、害虫を窒息させるという仕組みです。グンバイムシに対しても、特に動きの鈍い幼虫にはある程度の効果が期待できるかもしれません。 ただし、散布後に牛乳のにおいが残ったり、腐敗してカビの原因になったりすることもあるため、散布後は水で洗い流すなどのケアが必要です。使用する際は、牛乳と水を1:1程度に薄めて、晴れた日の午前中に散布するのが良いでしょう。
それでもダメなら…市販の薬剤(殺虫剤)を使った確実な駆除
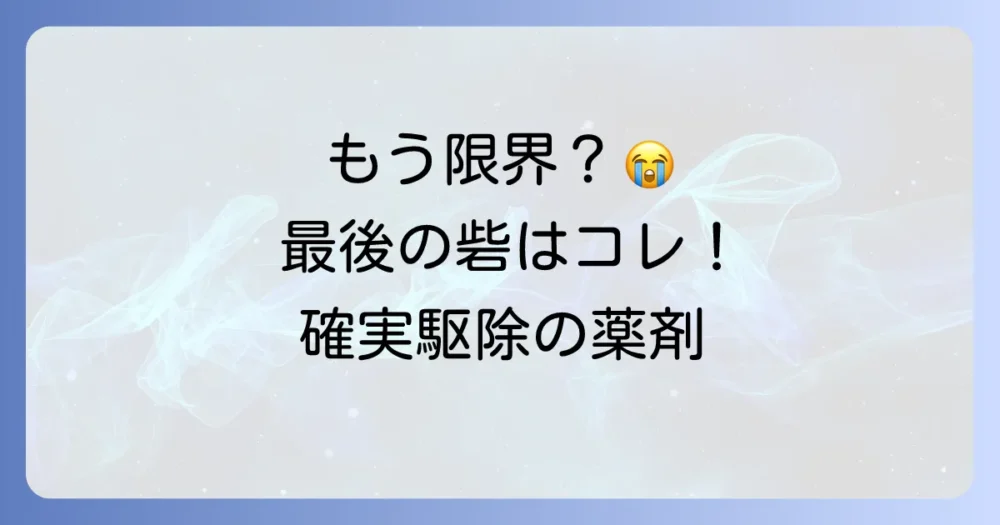
自然派の方法をいろいろ試したけれど、グンバイムシの勢いが止まらない…。被害がどんどん広がって、植物が弱っていくのを見るのは辛いものです。そんな時は、最終手段として市販の薬剤(殺虫剤)の使用を検討しましょう。正しく使えば、しつこいグンバイムシを効果的に駆除することができます。
本章では、以下のポイントを解説します。
- グンバイムシに効く殺虫剤の選び方
- おすすめの市販薬
- 薬剤を使用する際の注意点
グンバイムシに効く殺虫剤の選び方
グンバイムシは葉の裏に隠れていることが多く、スプレータイプの殺虫剤を直接当てるのが難しい場合があります。そこでおすすめなのが「浸透移行性(しんとういこうせい)」の殺虫剤です。 これは、薬剤が根や葉から植物の内部に吸収され、植物全体に行き渡るタイプの殺虫剤です。このタイプの薬剤を使うと、葉の汁を吸ったグンバイムシが、隠れている場所に関わらず薬剤に触れることになり、高い駆除効果を発揮します。
薬剤の形状には、スプレータイプ、粒剤タイプ、乳剤タイプなどがあります。
- スプレータイプ: 手軽ですぐに使えるのがメリット。葉の裏までしっかりかかるように散布しましょう。
- 粒剤タイプ: 株元にまくだけで効果が持続するのが特徴。手間がかからず、予防にも効果的です。
- 乳剤タイプ: 水で薄めて使うタイプ。広範囲に散布したい場合や、コストを抑えたい場合に適しています。
ご自身の使いやすさや、植物の状態に合わせて選びましょう。
おすすめの市販薬
園芸店やホームセンターでは、グンバイムシに効果のある様々な薬剤が販売されています。ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。
- オルトラン粒剤・水和剤: 浸透移行性の代表的な殺虫剤で、多くの園芸家が使用しています。 粒剤は株元にまくだけ、水和剤は水に溶かして散布します。効果の持続期間が長いのが特徴です。
- ベニカXネクストスプレー: 複数の有効成分を配合したスプレータイプの殺虫殺菌剤です。 グンバイムシだけでなく、アブラムシやうどんこ病など、幅広い病害虫に効果があります。予防効果も期待できるため、1本あると便利です。
- スミチオン乳剤: 幅広い害虫に効果のある、昔からある殺虫剤です。 葉の裏まで丁寧に散布することが、効果を高めるコツです。
これらの薬剤は効果が高い一方で、使用方法を誤ると植物や人体に影響が出る可能性もあります。購入の際は、必ずラベルをよく読み、対象植物や使用方法を確認してください。
薬剤を使用する際の注意点
化学薬剤を使用する際は、安全のために以下の点を必ず守ってください。
- ラベルをよく読む: 使用前に必ず製品のラベルや説明書を熟読し、対象となる植物、希釈倍率、使用回数、使用時期などの規定を守りましょう。
- 適切な服装で行う: 薬剤を吸い込んだり、皮膚に付着したりするのを防ぐため、マスク、手袋、長袖・長ズボンを着用しましょう。風上から風下に向かって散布するなど、風向きにも注意が必要です。
- 時間帯を選ぶ: 薬剤散布も、お酢スプレーと同様に日差しの強い日中を避け、朝方や夕方の涼しい時間帯に行いましょう。
- 周辺環境に配慮する: ペットや子供が散布場所に近づかないように注意し、洗濯物や近隣の住宅にかからないように配慮が必要です。また、ミツバチなどの益虫への影響が少ない薬剤を選ぶことも大切です。
- 保管方法: 使い残した薬剤は、子供やペットの手の届かない、直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
薬剤は強力な分、リスクも伴います。ルールを守って正しく使用し、大切な植物をグンバイムシの被害から守りましょう。
そもそもグンバイムシってどんな虫?生態と被害を知ろう
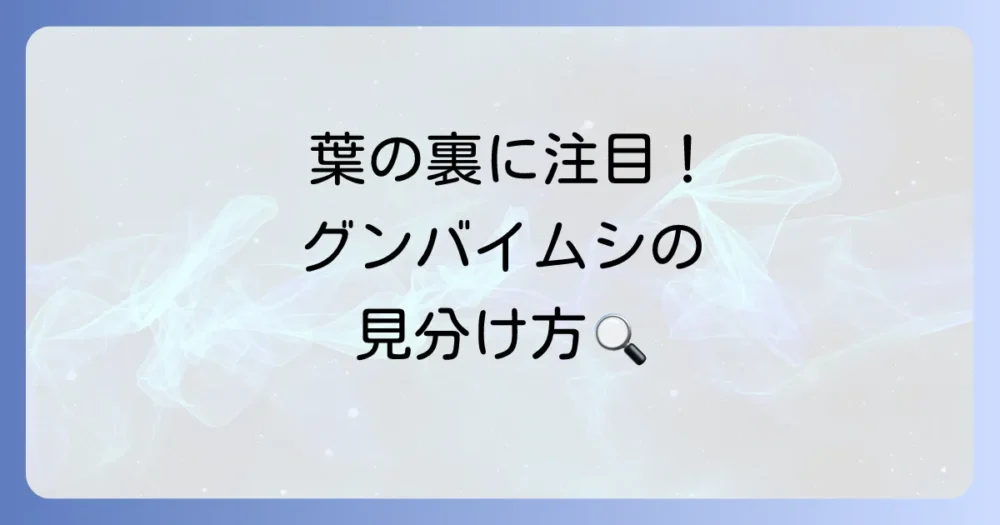
敵を知り、己を知れば百戦殆うからず。効果的な対策を行うためには、まず相手である「グンバイムシ」がどのような虫なのかを正しく理解することが重要です。そのユニークな見た目や生態、そして植物に与える被害のサインを知っておきましょう。
この章では、以下の内容を詳しく解説します。
- グンバイムシの見た目と特徴
- グンバイムシの発生時期とサイクル
- 被害のサインは?葉が白くかすり状になる
- 被害にあいやすい植物一覧
グンバイムシの見た目と特徴
グンバイムシはカメムシの仲間で、その名前は、翅(はね)をたたんだ姿が相撲の行司が持つ「軍配(ぐんばい)」に似ていることに由来します。 成虫の体長は3〜5mm程度と非常に小さいです。 翅は半透明で、レースのような美しい網目模様をしているのが大きな特徴で、このことから英語では「Lace bug(レースバグ)」と呼ばれています。
一方、幼虫は成虫とは全く違う姿をしています。紡錘形で、体中にトゲトゲとした突起があり、成虫のように翅はありません。 幼虫は集団で葉の裏に固まっていることが多いです。成虫も幼虫も、植物の葉に細い口を突き刺して汁を吸って生活しています。
グンバイムシの発生時期とサイクル
グンバイムシは、春から秋にかけての暖かい時期、主に4月から10月頃に発生・活動します。 特に、気温が高く乾燥した天気が続く初夏から夏にかけて、被害が拡大しやすい傾向にあります。 多くの種類は、落ち葉の下などで成虫の姿で冬を越し、春になると活動を再開します。
春に越冬した成虫が葉の裏の組織内に卵を産み付け、そこから孵化した幼虫が脱皮を繰り返して成虫になります。 年に数回世代を繰り返し(年間4〜5回発生する種類もいます)、条件が揃うとあっという間に数が増えてしまう、非常に繁殖力の強い害虫です。
被害のサインは?葉が白くかすり状になる
グンバイムシの被害で最も特徴的なのは、葉の表面に現れる白い斑点です。これは、グンバイムシが葉の裏から汁を吸うことで、その部分の葉緑素が抜けてしまうために起こります。 被害が進行すると、この白い斑点が無数に広がり、葉全体が白っぽくカサカサになった「かすり状」と呼ばれる状態になります。 この症状は、ハダニの被害と似ていますが、グンバイムシの場合は決定的な見分け方があります。
それは、葉の裏に付着する黒い点々です。これはグンバイムシの排泄物で、ヤニやインクのシミのように見えます。 この「葉の表は白く、裏は黒い点々で汚れている」というのが、グンバイムシ被害の最も分かりやすいサインです。被害がひどくなると、光合成ができなくなり、植物の生育が悪くなったり、見た目が著しく損なわれたり、最終的には葉が枯れて落ちてしまいます。
被害にあいやすい植物一覧
グンバイムシは非常に多くの植物に寄生しますが、特に被害にあいやすいことで知られている植物があります。ご自身の庭やベランダにこれらの植物がないか、チェックしてみてください。
- 花木類: ツツジ、サツキ、シャクナゲは特に被害が多く報告されています。 その他、アジサイ、フジ、アセビ、サクラ、プラタナスなどにも発生します。
- 草花類: キク、アスター、ヒマワリなどキク科の植物が好まれます。
- 果樹類: ナシ、リンゴ、モモ、ウメ、カキ、クリなどにも寄生する種類がいます。
- 野菜類: ナス、フキ、ゴボウ、サツマイモなどにも被害が出ることがあります。
このように、グンバイムシは庭木から草花、野菜まで、非常に広範囲の植物に被害を及ぼす可能性があります。 これらの植物を育てている場合は、特に注意深く葉の裏を観察する習慣をつけましょう。
二度と発生させない!グンバイムシの徹底予防策
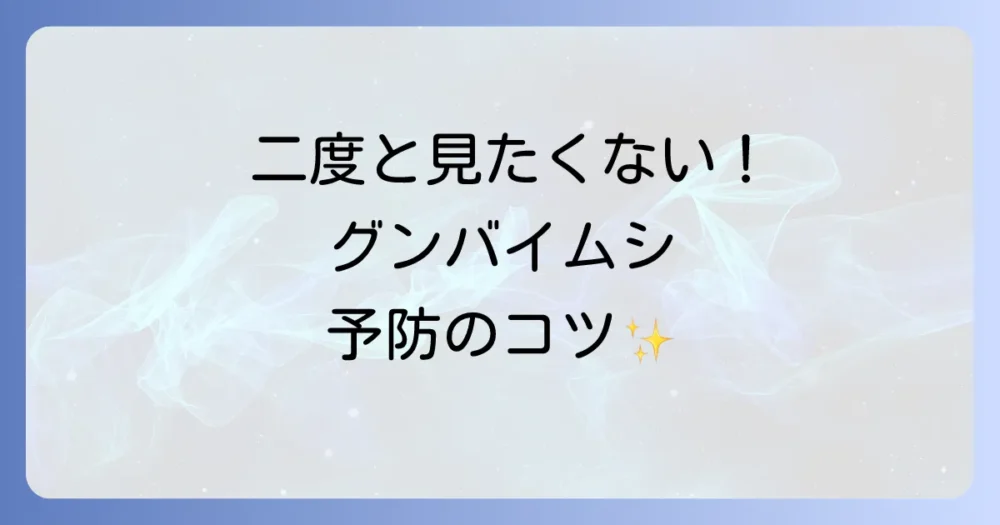
一度グンバイムシの被害にあうと、駆除には大変な手間がかかります。だからこそ、最も重要なのは「発生させない」こと、つまり予防です。グンバイムシが好む環境を作らないように日頃から少し気をつけるだけで、被害のリスクを大幅に減らすことができます。ここでは、誰でも実践できる効果的な予防策をご紹介します。
この章で解説する予防のポイントは以下の通りです。
- 風通しを良くする(剪定)
- 乾燥を防ぐ(葉水)
- 周辺の雑草を処理する
- 越冬させないための冬の対策
風通しを良くする(剪定)
グンバイムシは、風通しが悪く、湿気がこもる場所を好みます。 葉が密集して込み合っていると、グンバイムシにとって格好の隠れ家となり、繁殖しやすくなってしまいます。これを防ぐために効果的なのが「剪定」です。
混み合った枝や葉を間引くように剪定し、株全体の風通しと日当たりを良くしてあげましょう。 これにより、湿気がたまりにくくなるだけでなく、葉の裏まで日光が当たることで、グンバイムシが住みにくい環境を作ることができます。また、植物の病気予防にも繋がるため、定期的な剪定は非常に重要です。
乾燥を防ぐ(葉水)
グンバイムシは、高温で乾燥した環境で特に発生しやすくなります。 特に、雨の少ない夏場は注意が必要です。そこで有効なのが「葉水(はみず)」です。霧吹きやホースなどで、定期的に葉の表裏に水をかけてあげることで、植物周辺の湿度を保ち、乾燥を防ぎます。
この葉水は、グンバイムシの予防になるだけでなく、葉についたホコリを洗い流して光合成を助けたり、ハダニなどの他の乾燥を好む害虫の予防にもなったりと、一石二鳥の効果があります。 葉の裏側までしっかりと水をかけることを意識して、特に乾燥が続く時期にはこまめに行いましょう。
周辺の雑草を処理する
見落としがちですが、庭やプランターの周りの雑草もグンバイムシの発生源となることがあります。 特に、キク科の雑草などはグンバイムシの温床になりやすく、そこで増えたグンバイムシが大切な園芸植物に移動してくるケースが少なくありません。
大切な植物を守るためにも、周辺の雑草はこまめに抜き取り、常にきれいな状態を保つことを心がけましょう。これにより、グンバイムシだけでなく、他の病害虫の隠れ家をなくすことにも繋がります。
越冬させないための冬の対策
多くのグンバイムシは、落ち葉の下や樹皮の隙間などで成虫のまま冬を越します。 そして春になると、そこから出てきて活動を始めるのです。つまり、冬の間にこの越冬場所をなくしてしまえば、翌春の発生を大幅に抑えることができます。
具体的には、冬の間に株元の落ち葉をきれいに掃除して処分することが非常に効果的です。 これにより、越冬中のグンバイムシを物理的に取り除くことができます。少し手間はかかりますが、翌年の被害を格段に減らすことができる、最も効果的な予防策の一つと言えるでしょう。
よくある質問(Q&A)
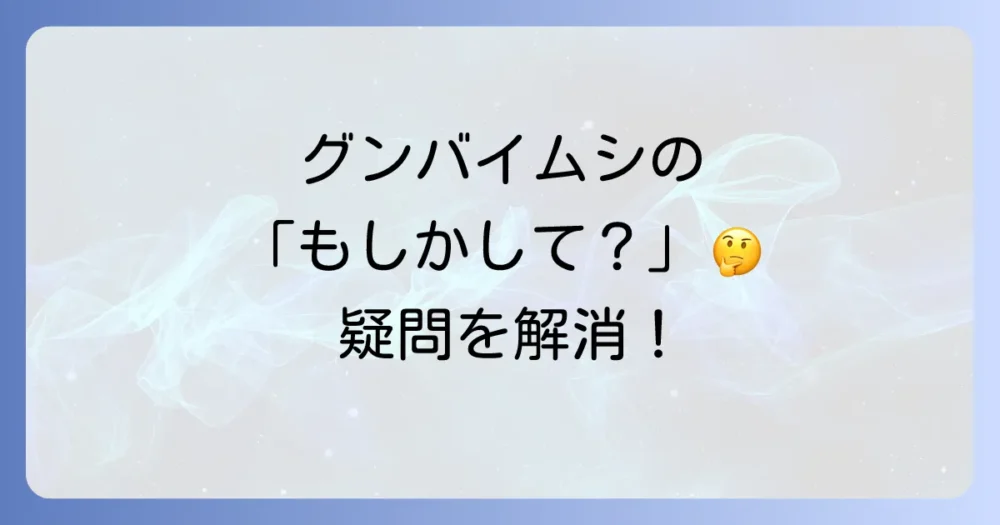
ここでは、グンバイムシの駆除や対策に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。
グンバイムシは人体に害はありますか?
グンバイムシは植物の汁を吸う害虫であり、人を刺したり咬んだりすることはありません。また、毒を持っているわけでもないので、人体に直接的な害を及ぼすことは基本的にありません。ただし、大量に発生した場合、洗濯物などについて家の中に入ってくることがあり、不快に感じることはあるかもしれません。
グンバイムシとハダニの見分け方は?
どちらも葉の養分を吸って白く変色させるため、被害症状がよく似ています。一番の見分け方は、葉の裏の状態です。 グンバイムシの被害では、葉の裏に黒いヤニ状の排泄物が多数付着します。一方、ハダニは非常に小さく(0.5mm程度)、肉眼では見えにくいですが、被害が進むと葉の裏に細かいクモの巣のような糸を張ることがあります。葉の裏を見て、黒い点々があればグンバイムシ、細かい糸があればハダニの可能性が高いと判断できます。
酢をスプレーしたら植物が枯れたりしませんか?
濃度を間違えると枯れる可能性があります。 お酢の酸は、植物の細胞を傷つける作用があるため、原液や濃すぎる希釈液を散布すると、葉が焼けたり、最悪の場合枯れてしまったりすることがあります。必ず規定の希釈倍率(水と1:1程度か、それより薄め)を守り、初めて使う際は一部の葉で試してから全体に散布するようにしてください。
木酢液と食酢の違いは何ですか?
主な違いは原料と成分です。食酢は米や穀物などをアルコール発酵させた後、酢酸菌で発酵させて作られます。主成分は酢酸です。 一方、木酢液は木材を燃やして炭にする過程で出る煙を冷却して液体にしたもので、酢酸も含まれますが、その他にも200種類以上の有機化合物が含まれているのが特徴です。 この多様な成分が、害虫忌避だけでなく土壌改良などにも効果を発揮するとされています。
グンバイムシの天敵はいますか?
グンバイムシにも天敵は存在します。例えば、ヒメハナカメムシ類やカブリダニ類、寄生蜂などが知られています。 しかし、家庭の庭やベランダで天敵の力だけでグンバイムシの発生を完全に抑えるのは難しいのが現状です。天敵が活動しやすいように、農薬の使用を控えるなどの環境づくりは有効ですが、基本的には剪定や葉水などの予防策と組み合わせることが大切です。
まとめ
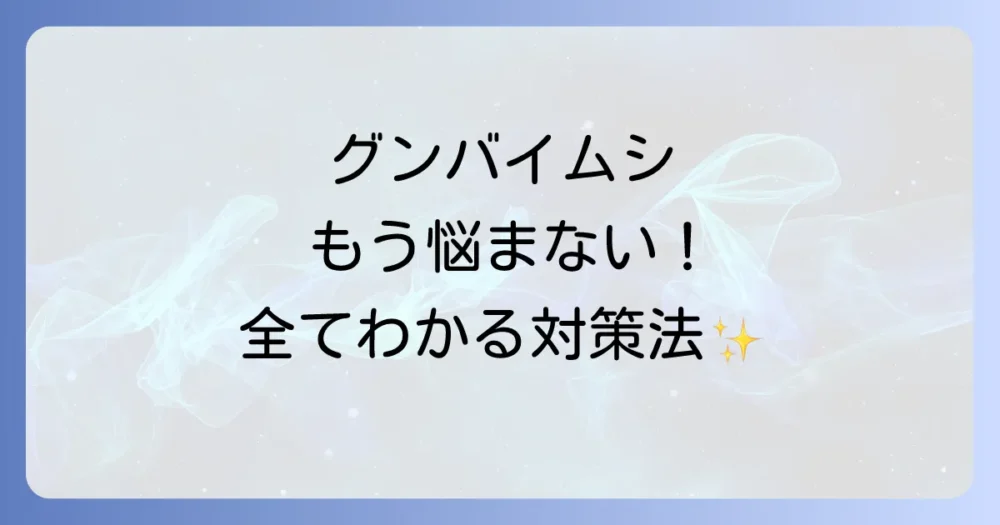
- お酢には直接的な殺虫効果はほぼなく、忌避効果が期待できる。
- お酢スプレーは水と1:1で薄め、葉の裏を中心に散布する。
- お酢での対策は、発生初期や予防策として有効。
- 農薬を使わない駆除では、水で洗い流す物理的駆除が効果的。
- 木酢液や竹酢液も、忌避効果や土壌改良効果が期待できる。
- 被害がひどい場合は、浸透移行性の殺虫剤が確実。
- オルトランやベニカXなどが市販薬として有効。
- グンバイムシは軍配に似た形の3-5mmの虫。
- 被害のサインは「葉の表が白く、裏に黒い点々」。
- ツツジ、サツキ、シャクナゲなどで特に発生しやすい。
- 予防の基本は「風通し」と「乾燥させないこと」。
- 剪定で風通しを良くすることが最も重要。
- 定期的な葉水は乾燥を防ぎ、予防に繋がる。
- 周辺の雑草はこまめに抜き、発生源をなくす。
- 冬の落ち葉掃除は、越冬させないための重要な対策。