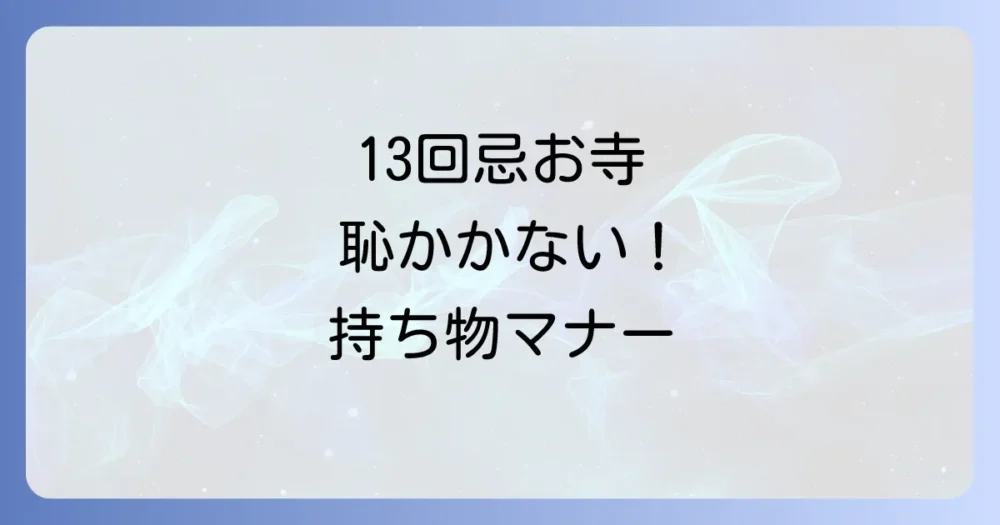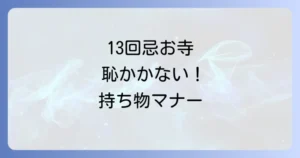故人を偲ぶ大切な法要である13回忌。七回忌から少し間が空くため、「何を持っていけばいいんだっけ?」「マナーはこれで合っているかな?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。特に、お寺で法要を行うとなると、持ち物や作法について悩んでしまいますよね。
本記事では、13回忌でお寺に行く際に必要な持ち物を、施主(主催者)側と参列者側に分けて、分かりやすくチェックリスト形式でご紹介します。さらに、気になるお布施の金額相場や服装のマナー、当日の流れまで、13回忌に関するあらゆる疑問を解消します。この記事を最後まで読めば、心の準備が整い、安心して故人様と向き合う一日を迎えられるはずです。
まずは確認!13回忌でお寺に持っていくものチェックリスト
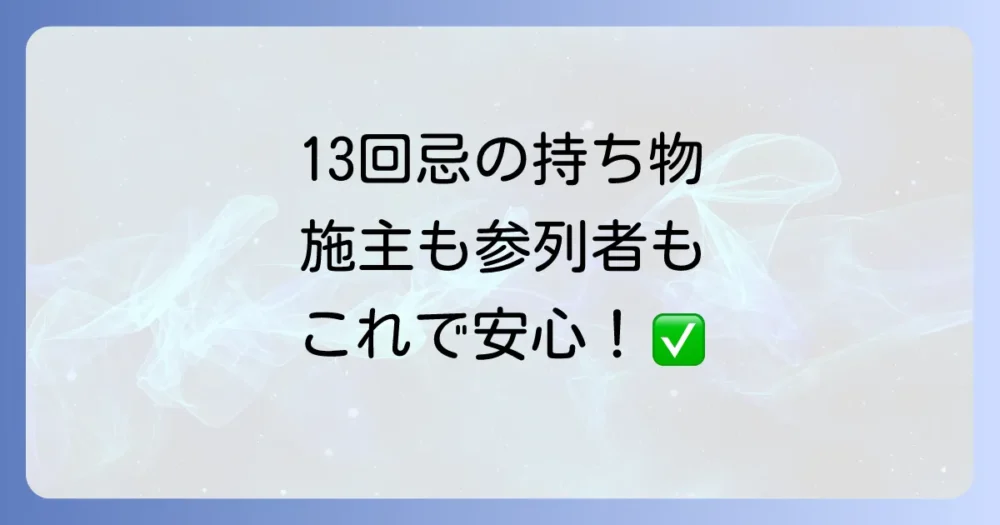
13回忌の法要は、施主(主催者)と参列者では準備するものが異なります。法要が近づいてから慌てないように、まずは持ち物リストで全体像を把握しましょう。ご自身の立場に合わせて、必要なものを確認してください。
ここでは、施主と参列者それぞれが準備すべき持ち物を一覧表にまとめました。印刷して準備の際に活用するのもおすすめです。
【施主】が準備する持ち物一覧
施主は法要全体を取り仕切るため、準備するものが多岐にわたります。特に僧侶へのお礼であるお布施や、参列者への返礼品は忘れずに準備しましょう。
| 分類 | 持ち物 | 備考 |
|---|---|---|
| お寺・僧侶へ渡すもの | お布施 | 読経や法要に対する感謝の気持ち。金額相場は後述します。 |
| 御車代 | 僧侶に自宅や会食会場など、お寺以外の場所へ出向いてもらう場合に用意します。 | |
| 御膳料 | 法要後の会食に僧侶が参加されない場合に渡します。 | |
| 法要で必要なもの | 位牌・遺影 | 本堂に飾るために持参します。忘れないようにしましょう。 |
| 過去帳 | 先祖代々の戒名や命日が記された帳面。お寺に持参し、記録してもらう場合があります。 | |
| お供え物(供物・供花) | 故人が好きだったお菓子や果物、季節の花など。お寺で用意してくれる場合もあるので事前に確認を。 | |
| 参列者へ渡すもの | 返礼品(引き出物) | 香典やお供えをいただいた方へのお返し。消え物が一般的です。 |
| 個人の持ち物 | 数珠 | 自身の宗派に合ったものを用意します。 |
| 袱紗(ふくさ) | お布施を包むために使います。紫色は慶弔両用で便利です。 |
【参列者】が持参する持ち物一覧
参列者として招かれた場合は、施主への心遣いとして香典やお供え物を持参するのが一般的です。故人を偲ぶ気持ちを大切に、基本的な持ち物を準備しましょう。
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 香典 | 不祝儀袋に入れて持参します。金額相場は故人との関係性によります。 |
| お供え物 | 施主の負担にならない程度の、日持ちするお菓子や果物などがおすすめです。 |
| 数珠 | 社会人としてのマナー。自身の宗派のものを持参しましょう。貸し借りはNGです。 |
| 袱紗(ふくさ) | 香典を包むために使用します。受付で渡す際に袱紗から出して渡すのがマナーです。 |
| ハンカチ・ティッシュ | 白や黒、紺など地味な色の無地のものを選びましょう。 |
【施主向け】最重要!お寺に渡す「お布施」の全知識
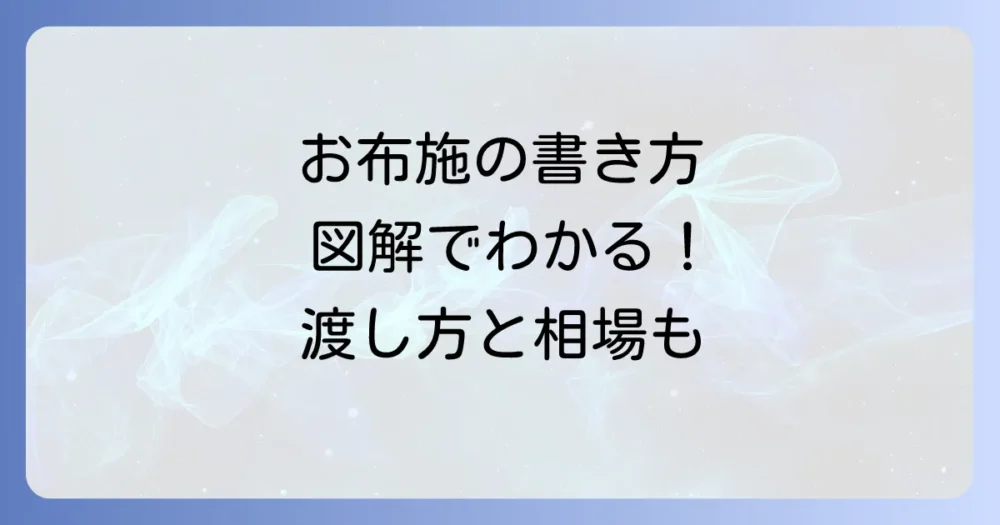
施主にとって、最も気になるのが僧侶へお渡しする「お布施」ではないでしょうか。お布施は読経や供養に対する対価ではなく、ご本尊へお供えする「感謝の気持ち」です。失礼のないように、相場やマナーをしっかりと押さえておきましょう。
この章では、以下の内容を詳しく解説していきます。
- お布施の金額相場は1万円~5万円
- お布施以外に用意する費用「御車代」と「御膳料」
- 【図解】お布施袋の書き方と包み方
- 僧侶へのスマートな渡し方とタイミング
お布施の金額相場は1万円~5万円
13回忌の法要で渡すお布施の金額相場は、1万円~5万円が一般的です。 これは、あくまで目安であり、お寺との関係性や地域、法要の規模によって変動します。これまでの法要(一周忌や三回忌など)で包んだ金額と同等額を用意するのが一つの基準になります。
お布施は感謝の気持ちを表すものなので、金額に決まりはありません。もし金額に迷う場合は、菩提寺に直接「皆様、おいくらくらい包まれていますか?」と尋ねても失礼にはあたりません。 率直に相談してみましょう。
お布施以外に用意する費用「御車代」と「御膳料」
お布施とは別に、状況に応じて「御車代」と「御膳料」を用意する必要があります。これらも白い無地の封筒に入れ、表書きをしてお布施とは別に準備します。
- 御車代(おくるまだい)
僧侶にお寺以外の場所(自宅や墓地、会食会場など)へ出向いていただいた際に、交通費としてお渡しします。相場は5,000円~1万円程度です。 施主が送迎を手配した場合は不要です。お寺で法要を行う場合も基本的には不要ですが、感謝の気持ちとしてお渡しするケースもあります。 - 御膳料(ごぜんりょう)
法要後の会食(お斎)に僧侶が参加されない場合に、食事代としてお渡しします。相場は5,000円~1万円程度が目安です。 もし僧侶が会食に参加される場合は、御膳料を用意する必要はありません。
【図解】お布施袋の書き方と包み方
お布施は、奉書紙(ほうしょがみ)で包むのが最も丁寧ですが、郵便番号欄のない白い無地の封筒でも問題ありません。 水引は不要です。
【表面の書き方】
上段中央に「御布施」または「お布施」と濃い墨の筆ペンや毛筆で書きます。下段中央には、施主の氏名(フルネーム)または「〇〇家」と書きます。
【中袋の書き方】
中袋がある場合は、表面に包んだ金額を旧字体の漢数字(例:金 参萬圓也)で記入します。 裏面には、施主の住所と氏名を記入しておくと、お寺側で管理しやすくなります。
【お札の入れ方】
お札は新札を用意するのが望ましいとされていますが、なければ綺麗なお札を選びましょう。お札の向きを揃え、肖像画が描かれている面が封筒の表側の上に来るように入れます。
僧侶へのスマートな渡し方とタイミング
お布施を渡す際は、直接手渡しするのではなく、切手盆(きってぼん)という小さなお盆に乗せるか、袱紗(ふくさ)に包んで渡すのが丁寧なマナーです。
渡すタイミングに決まりはありませんが、以下のいずれかのタイミングが一般的です。
- 法要が始まる前の挨拶の際
「本日はどうぞよろしくお願いいたします」という挨拶と共に渡します。 - 法要が終わった後の挨拶の際
「本日は心のこもったお勤め、誠にありがとうございました」というお礼の言葉と共に渡します。
お寺の控室などで、他の人がいない場所で渡すのがスマートです。渡す際は、お盆や袱紗から取り出し、僧侶から見て表書きが正面になるように向きを変えて差し出しましょう。
喜ばれる「お供え物」の選び方とマナー
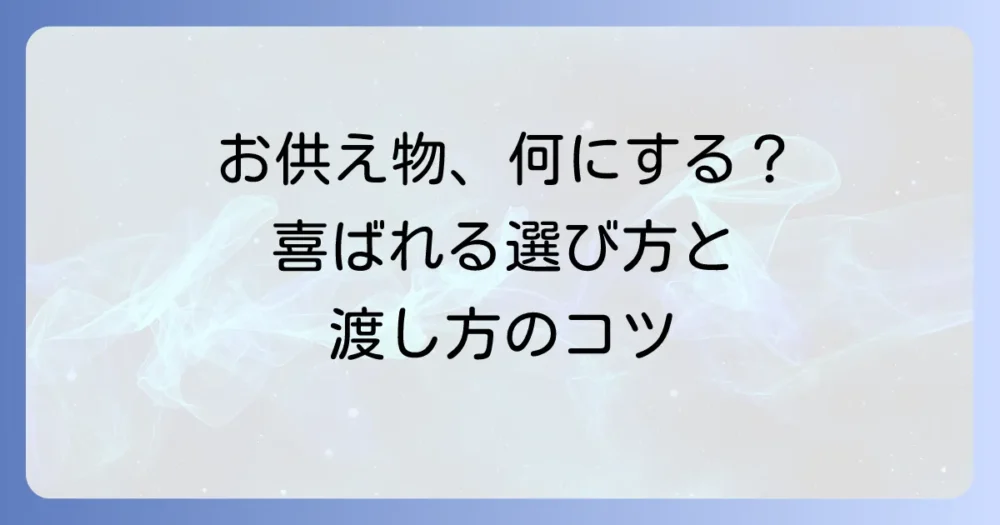
参列者として招かれた場合、香典とは別にお供え物を持参すると、より丁寧な印象になります。施主の立場であっても、ご本尊や故人へのお供え物は準備します。ここでは、お供え物選びのポイントと、失礼にならないためのマナーを解説します。
この章では、以下の内容を詳しく解説していきます。
- おすすめのお供え物5選(消え物が基本)
- これはNG!避けるべきお供え物
- お供え物の「のし」の書き方と水引の選び方
- お寺へのお供え物の渡し方と注意点
おすすめのお供え物5選(消え物が基本)
お供え物は、法要後に参列者で分け合う(お下がりをいただく)こともあるため、あとに残らない「消え物」を選ぶのが基本です。 また、日持ちがして、個包装になっているものだと、分けやすく喜ばれます。
- お菓子
クッキーやせんべい、カステラ、ゼリーなど、日持ちのする焼き菓子や和菓子が定番です。故人が好きだったお菓子を選ぶと、供養の気持ちがより伝わるでしょう。 - 果物
季節の果物の詰め合わせは彩りも良く、お供え物として人気です。りんごや梨、ぶどうなど、傷みにくく分けやすいものがおすすめです。 - 飲み物
お茶やコーヒー、ジュースのセットなども良いでしょう。故人がお酒好きだった場合はお酒をお供えすることもありますが、施主や他の参列者への配慮も必要です。 - 花(供花)
故人が好きだった花や、白を基調とした淡い色の花束やアレンジメントが適しています。 トゲのある花や香りの強い花は避けましょう。 - 線香・ろうそく
毎日使う消耗品なので、実用的で喜ばれます。少し高級なものや、香りの良いものを選ぶと特別感が出ます。
これはNG!避けるべきお供え物
一方で、お供え物としてふさわしくないとされるものもあります。良かれと思って持参したものが、かえって迷惑になってしまうことのないよう注意しましょう。
- 肉や魚などの「生臭もの」
仏教では殺生を連想させるため、タブーとされています。 - トゲや毒のある花
バラやアザミなどのトゲのある花、彼岸花などの毒のある花は避けましょう。 - 香りの強すぎるもの
香水や香りの強い花は、お香の香りを妨げるため避けるのが無難です。 - 日持ちのしないもの
生クリームを使ったケーキなど、すぐに傷んでしまうものは避けましょう。
お供え物の「のし」の書き方と水引の選び方
お供え物には、掛け紙(のし紙)をかけるのがマナーです。品物に直接かける「内のし」と、包装紙の上からかける「外のし」がありますが、どちらでも構いません。
- 水引
黒白または双銀、関西など地域によっては黄白の結び切りを使用します。 結び切りは「不幸が二度と繰り返されないように」という意味が込められています。 - 表書き
水引の上段中央に、濃い墨で「御供」または「御供物」と書きます。 - 名前
水引の下段中央に、贈り主の氏名をフルネームで書きます。
もしお供え物ではなく現金を包む場合は、「御供物料」として不祝儀袋に入れて渡します。
お寺へのお供え物の渡し方と注意点
お供え物は、紙袋や風呂敷から取り出して、施主に直接手渡すのがマナーです。 勝手に仏壇にお供えするのは避けましょう。
渡す際には、「どうぞ御仏前にお供えください」と一言添えます。その際、相手からのし紙の表書きが読める向きにして差し出すのが丁寧です。
また、お寺によっては、お供え物を辞退されたり、お寺で一括して準備されたりする場合があります。 特に遠方から参列する場合などは、事前に施主に確認しておくと、持ち運びの負担も減り、お互いにスムーズです。
恥をかかないための13回忌の服装マナー
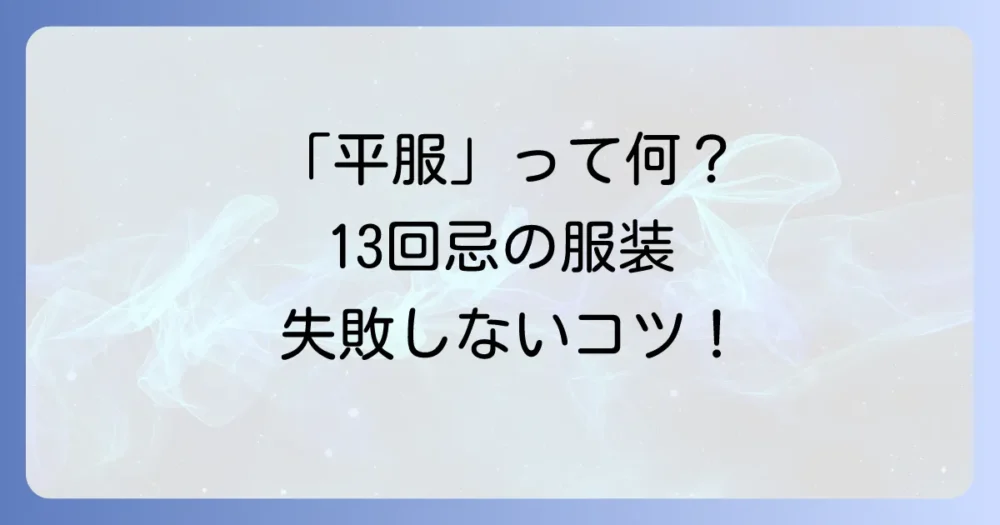
13回忌ともなると、故人が亡くなってから12年という歳月が流れています。そのため、葬儀や一周忌のような厳格な喪服ではなく、少しずつ服装の格式も緩やかになります。しかし、法要であることに変わりはありません。故人への敬意と、その場にふさわしい服装を心がけましょう。
この章では、以下の内容を詳しく解説していきます。
- 基本は「平服(略喪服)」でOK
- 【男性】ダークスーツが基本
- 【女性】露出を控えたダークカラーの服装
- 【子供】制服または落ち着いた色の服
基本は「平服(略喪服)」でOK
13回忌の法要では、施主・参列者ともに「平服(へいふく)」での参加が一般的です。 ここで注意したいのが、法事における「平服」とは、普段着のことではなく「略喪服(りゃくもうふく)」を指すという点です。 Tシャツやジーンズのようなカジュアルな服装はマナー違反ですので、絶対に避けましょう。
施主から「平服でお越しください」と案内があった場合は、この略喪服を着用します。特に案內がなくても、13回忌であれば略喪服で問題ありません。
【男性】ダークスーツが基本
男性の服装は、黒や濃紺、ダークグレーなどの地味な色のスーツが基本です。 光沢のない素材を選びましょう。
- スーツ:黒、濃紺、チャコールグレーなどのダークスーツ。無地が望ましい。
- シャツ:白無地のワイシャツ。色柄物は避けます。
- ネクタイ:黒無地のもの。
- 靴下:黒無地。
- 靴:黒の革靴。金具などの飾りがなく、光沢の少ないシンプルなデザインのものを選びましょう。
結婚指輪以外のアクセサリーや、派手な腕時計は外しておくのが無難です。
【女性】露出を控えたダークカラーの服装
女性も同様に、黒や濃紺などのダークカラーで、露出の少ない服装を心がけます。
- 服装:黒、濃紺、ダークグレーなどのワンピース、アンサンブル、スーツ。パンツスーツも着用可能です。 スカート丈は膝が隠れる長さにし、体のラインが出過ぎないデザインを選びましょう。
- ストッキング:黒の薄手のもの。厚手のタイツや網タイツ、素足はNGです。
- 靴:黒の布製または革製のパンプス。ヒールは高すぎず、光沢や飾りのないシンプルなものが適しています。
- アクセサリー:基本的には結婚指輪のみ。着ける場合は、一連の真珠のネックレスやイヤリング(ピアス)までとされています。二連のネックレスは「不幸が重なる」ことを連想させるため避けましょう。
- メイク・ネイル:派手なメイクは避け、ナチュラルな薄化粧を心がけます。ネイルは落としておくのが基本ですが、難しい場合はベージュなどの目立たない色にするか、手袋で隠すなどの配慮をしましょう。
【子供】制服または落ち着いた色の服
子供が参列する場合、学校の制服があればそれが正装となります。 制服がなければ、大人に準じて地味な色の服装を選びましょう。
- 男の子:白いシャツに、黒や紺、グレーのズボンとブレザーなど。
- 女の子:白いブラウスに、黒や紺、グレーのスカートやワンピースなど。
キャラクターが描かれた服や、派手な色の服は避け、清潔感のある服装を心がけてください。
13回忌法要当日の流れと準備
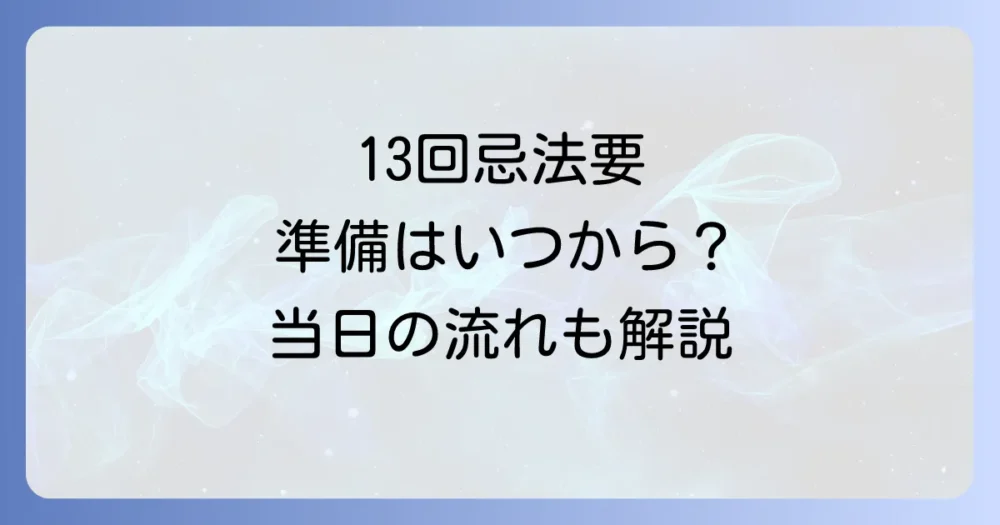
13回忌の法要をスムーズに執り行うためには、事前の準備と当日の流れを把握しておくことが大切です。特に施主は、日程調整から会食の手配まで、やることがたくさんあります。ここでは、一般的な準備の段取りと、当日の流れをご紹介します。
この章では、以下の内容を詳しく解説していきます。
- 事前準備から当日までのスケジュール
- 法要当日の一般的な流れ
事前準備から当日までのスケジュール
施主は、遅くとも法要の2ヶ月前くらいから準備を始めると安心です。
- 【2ヶ月前】日程・場所の決定、僧侶への依頼
まず、お寺(僧侶)の都合を確認し、法要の日時を決定します。 命日に行うのが理想ですが、平日の場合は参列者の都合を考慮し、命日より前の土日祝日に行うのが一般的です。 日程が決まったら、会場(お寺、自宅、斎場など)を確定させます。 - 【1ヶ月半前】参列者の決定と案内状の送付
誰を招待するかを家族で話し合って決めます。13回忌は親族のみなど小規模で行うことが多いです。 参列者が決まったら、案内状を送付し、出欠の返信をお願いします。 - 【1ヶ月前】会食・返礼品の手配
出欠の返信が届き始めたら、おおよその人数を把握し、会食(お斎)の会場や料理、返礼品(引き出物)の手配を進めます。 - 【1週間前~前日】最終確認
お布施、お供え物、位牌などの持ち物を最終確認します。参列者の人数が確定したら、会食会場に最終連絡を入れましょう。
法要当日の一般的な流れ
お寺で行う場合の一般的な法要の流れは以下の通りです。法要自体は1時間程度、その後の会食などを含めると全体で3~4時間ほど見ておくと良いでしょう。
- 参列者集合・受付
施主は早めに会場に到着し、僧侶への挨拶と参列者の出迎えをします。 - 僧侶入場・開式の挨拶
定刻になったら僧侶が入場し、一同着席します。施主が簡単な開式の挨拶を述べます。 - 読経
僧侶による読経が始まります。 - 焼香
僧侶の案内に従い、施主、遺族、親族、友人の順に焼香を行います。 - 法話
僧侶からありがたいお話(法話)をいただきます。 - 僧侶退場・閉式の挨拶
僧侶が退場した後、施主が参列者へのお礼と、この後の会食などの案内をして閉式となります。 - お墓参り(任意)
お寺の境内にお墓がある場合は、法要後にお墓参りをすることが多いです。 - 会食(お斎)
場所を移して会食を行います。施主は下座に座り、参列者をもてなします。会食の最後に、施主が改めてお礼の挨拶をし、返礼品を渡してお開きとなります。
13回忌に関するよくある質問
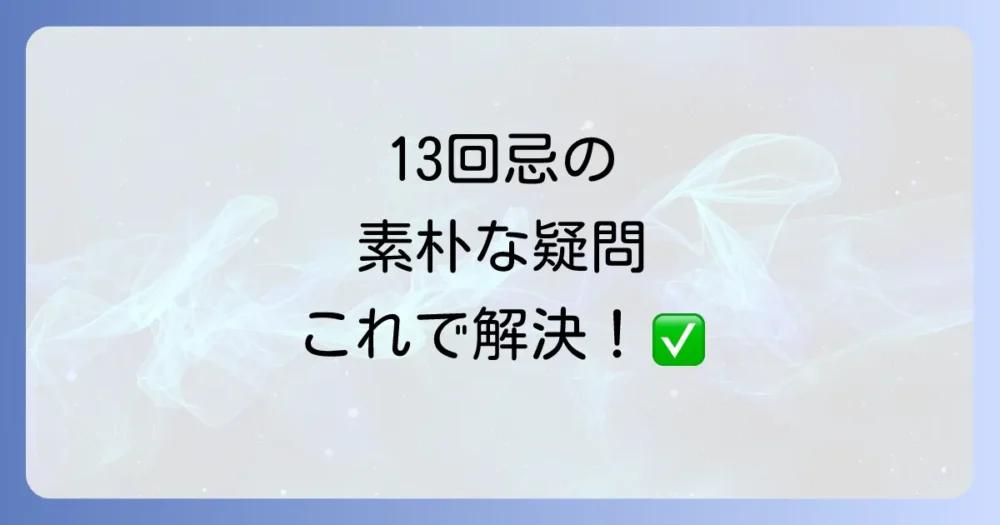
ここまで13回忌の持ち物やマナーについて解説してきましたが、まだ細かな疑問が残っている方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、13回忌に関してよく寄せられる質問にお答えします。
13回忌はいつ、誰と行うものですか?
13回忌は、故人が亡くなってから満12年目の祥月命日(しょうつきめいにち)に行う法要です。 亡くなった年を1年目と数えるため、「13回忌」となります。 参列者に特に決まりはありませんが、七回忌以降は規模を縮小していくのが一般的で、故人の子どもや孫といったごく近しい親族のみで執り行われることが多くなります。
家族だけで行う場合、持ち物や香典はどうなりますか?
家族だけで行う場合でも、施主が準備する持ち物(お布施、位牌、お供え物など)は基本的に同じです。ただし、参列者である家族間の取り決めとして、香典やお供え物を省略するケースも多く見られます。 その場合は、施主も返礼品の準備は不要になります。事前に家族間で「香典はなしにしよう」などと話し合っておくと、お互いに気を遣わずに済み、スムーズです。
お寺に渡すものは現金(お布施)だけでも大丈夫ですか?
はい、基本的にお寺(僧侶)へのお礼は、現金(お布施、御車代、御膳料)で問題ありません。お供え物については、お寺で用意してくださる場合や、お供えのスペースの都合などもあるため、施主がお供え物を持参する場合でも、事前に一度お寺に確認しておくのが最も丁寧です。参列者の場合は、施主(ご遺族)の負担を考え、現金(香典)のみでも失礼にはあたりません。もしお供え物を持参できないけれど気持ちを伝えたい場合は、「御供物料」として現金を包む方法もあります。
13回忌のお返し(引き出物)は必要ですか?相場は?
はい、香典やお供え物をいただいた場合は、お返しとして引き出物(返礼品)を用意するのがマナーです。 金額の相場は、いただいた香典やお供え物の3分の1から半額程度が目安です。 品物は、お茶や海苔、お菓子、洗剤といった「消え物」が定番です。最近では、相手が好きなものを選べるカタログギフトも人気があります。
13回忌に持っていかない方が良いものはありますか?
お供え物の章でも触れましたが、肉や魚などの生臭ものや、バラのようなトゲのある花、香りの強すぎるものは避けるべきです。 また、服装や持ち物に関しても、殺生を連想させる動物の革製品(バッグやコートなど)や、光り輝く派手なアクセサリーは法要の場にふさわしくありません。故人を偲ぶ場であることを念頭に置き、華美なものは避けるのが賢明です。
まとめ
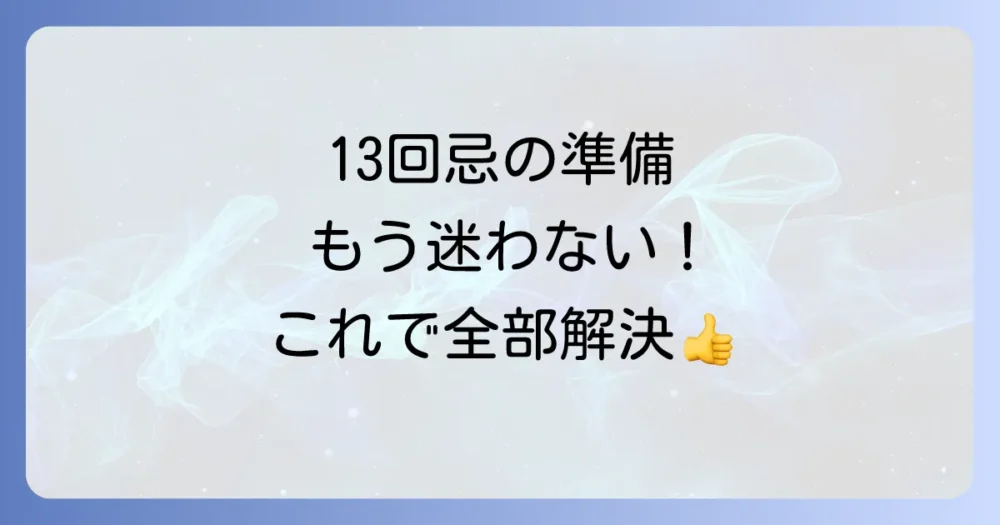
- 13回忌は故人が亡くなって満12年目に行う法要です。
- 施主は「お布施」「位牌」「返礼品」などを準備します。
- 参列者は「香典」「お供え物」「数珠」を持参します。
- お布施の相場は1万円~5万円が一般的です。
- 状況により「御車代」「御膳料」も用意します。
- お供え物は日持ちのする「消え物」が基本です。
- 肉や魚、トゲのある花はお供え物としてNGです。
- お供え物ののしは「御供」とし、黒白等の結び切りを使います。
- 服装は施主・参列者ともに「平服(略喪服)」がマナーです。
- 男性はダークスーツ、女性はダークカラーのワンピースなどが基本です。
- 法要は僧侶への依頼から始まり、会食で終わるのが一般的です。
- 家族のみで行う場合、香典を省略することもあります。
- 香典を頂いたら、3分の1~半額程度の返礼品を用意します。
- 持ち物やマナーで迷ったら、施主や菩提寺に確認するのが確実です。
- 最も大切なのは、故人を敬い、偲ぶ気持ちです。
新着記事