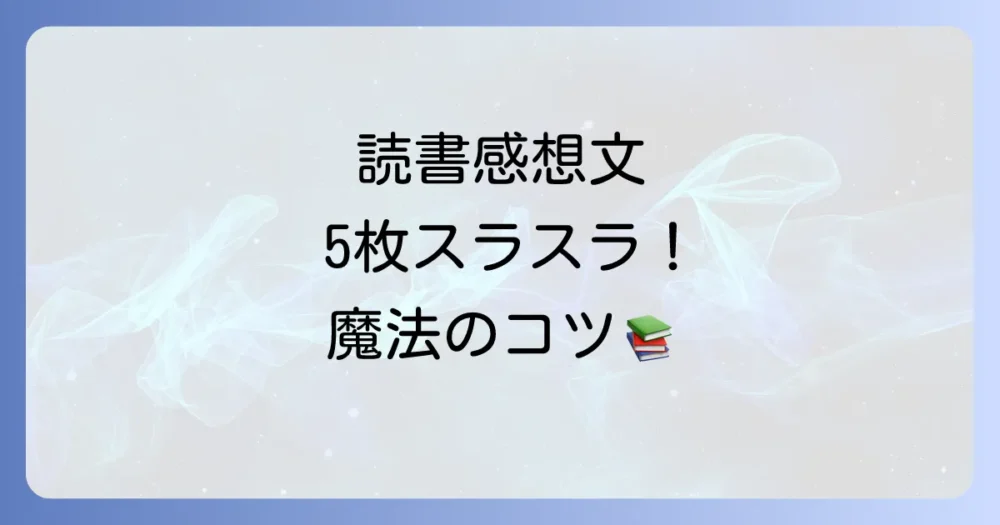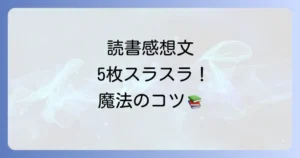夏休みの宿題の定番、読書感想文。毎年「今年こそは!」と思うものの、いざ原稿用紙を前にすると「何から書けばいいんだろう…」「5枚も書けないよ…」と頭を抱えてしまう中学生は多いのではないでしょうか。せっかく本を読んだのに、感想を言葉にするのは難しいですよね。
本記事では、そんな悩める中学生のために、原稿用紙5枚の読書感想文をスラスラ書けるようになる、魔法のような構成テンプレートと書き方のコツを徹底解説します。この記事を最後まで読めば、もう読書感想文は怖くありません。友達に「すごい!」と言われるような感想文を、一緒に完成させましょう!
読書感想文が書けない…中学生が抱える3つの悩み
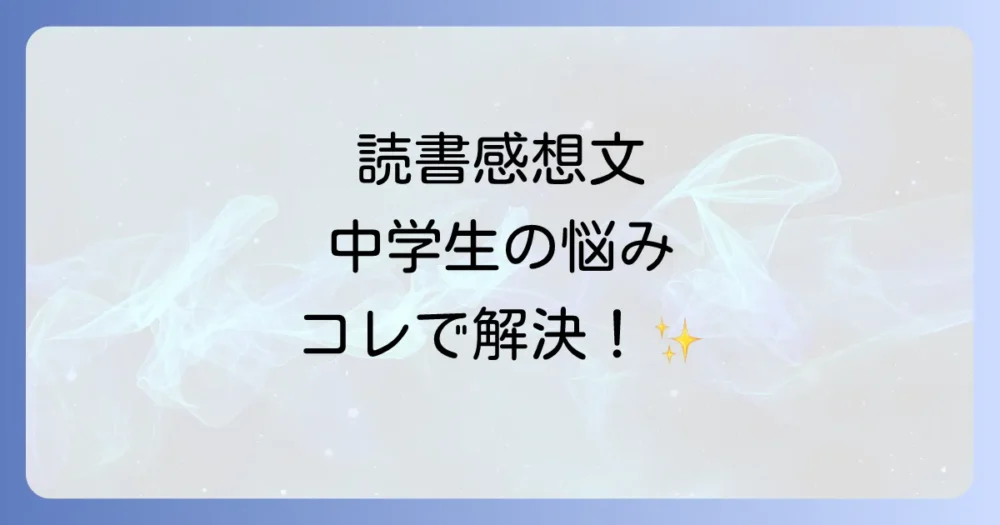
読書感想文と聞くだけで、憂鬱な気分になる人もいるかもしれません。多くの人が同じような悩みを抱えています。まずは、なぜ読書感想文が難しいと感じるのか、その原因を探ってみましょう。きっと「自分だけじゃなかったんだ」と安心できるはずです。
本章では、中学生が読書感想文でつまずきがちなポイントを3つに絞って解説します。
- 悩み①:何を書けばいいのか分からない
- 悩み②:原稿用紙5枚も埋められない
- 悩み③:ありきたりな感想になってしまう
悩み①:何を書けばいいのか分からない
最も多い悩みが、「そもそも何を書けばいいのか分からない」というものです。本を読んで「面白かった」「感動した」という気持ちはあっても、それをどう文章にすれば良いのか、具体的な言葉にできないのですね。
「あらすじを書いてはいけない」とよく言われますが、では何を書けばいいのか。 心に残った場面やセリフを挙げようとしても、どうして心に残ったのかを深く掘り下げて説明するのは、なかなか難しい作業です。結果として、何を書けば評価されるのか分からず、ペンが止まってしまいます。
悩み②:原稿用紙5枚も埋められない
次に多いのが、「原稿用紙5枚(2000字)という分量の多さに圧倒されてしまう」という悩みです。書きたいことがいくつか思い浮かんでも、それを5枚分にまで膨らませる方法が分からない、というケースです。
書き出しはなんとかクリアできても、すぐにネタが尽きてしまい、同じような内容を繰り返してしまったり、無理やり文章を引き延ばそうとして不自然な日本語になったり…。 延々とあらすじを書いて文字数を稼ごうとしてしまうのも、この悩みが原因であることが多いです。
悩み③:ありきたりな感想になってしまう
「面白かったです」「感動しました」といった月並みな言葉で終わってしまい、「自分らしいオリジナリティのある感想文にならない」という悩みも深刻です。 他の人の感想文と似たような内容になってしまい、先生に評価してもらえないのではないか、という不安を感じる人もいるでしょう。
自分の経験や考えをどうやって文章に盛り込めば良いのか、どうすれば他の人とは違う、深みのある感想文になるのか。その方法が分からず、結局は本の表面的な感想だけで終わってしまうのです。
これで完璧!読書感想文5枚の黄金構成テンプレート
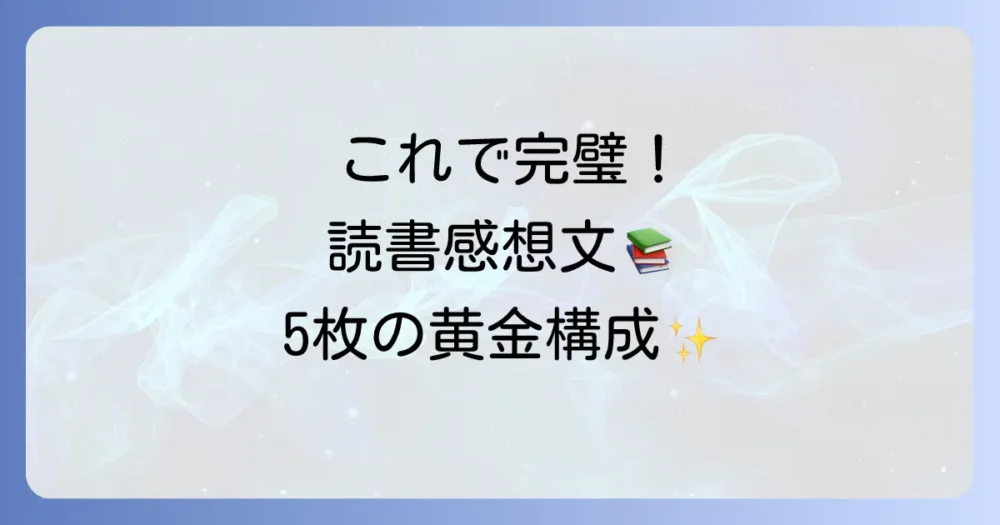
「5枚も書けない!」という悩みを解決する最強の方法、それは「構成のテンプレート」を使うことです。 あらかじめ書く順番と内容の骨組みを決めておくことで、迷うことなくスラスラと書き進められます。ここでは、原稿用紙5枚の読書感想文に最適な「5部構成」のテンプレートを紹介します。この型に沿って書けば、自然と内容に深みが出て、文字数もクリアできますよ!
この章で紹介する構成は以下の通りです。
- 構成①:はじめ(書き出し)- 本との出会いとあらすじ(原稿用紙1枚目半分)
- 構成②:なか① – 心に残った部分とその理由(原稿用紙1枚目半分~2枚目)
- 構成③:なか② – 自分の経験との比較(原稿用紙3枚目)
- 構成④:なか③ – 作品から学んだこと・考えたこと(原稿用紙4枚目)
- 構成⑤:おわり(まとめ)- 今後の自分と社会への広がり(原稿用紙5枚目)
構成①:はじめ(書き出し)- 本との出会いとあらすじ(原稿用紙1枚目半分)
読書感想文の導入部分です。ここでは、読者の興味を引きつけ、「この先を読んでみたい」と思わせることが重要です。 まず、なぜこの本を選んだのかという「本との出会い」を書きましょう。 「表紙の絵に惹かれた」「タイトルが気になった」「友達にすすめられた」など、正直な理由で構いません。
次に、本を読んでいない人にも内容が伝わるように、ごく簡単なあらすじを紹介します。 ただし、ダラダラと長く書くのはNG。全体の1割程度、原稿用紙5枚なら10行(200字)以内に収めるのが目安です。 主人公がどんな状況で、どんな出来事に遭遇し、物語がどう展開していくのかを簡潔にまとめましょう。
構成②:なか① – 心に残った部分とその理由(原稿用紙1枚目半分~2枚目)
ここからが感想文のメインパートです。本を読んで、最も心が動かされた場面やセリフを具体的に取り上げます。 そして、なぜそこに心を惹かれたのか、その理由を深く掘り下げていきましょう。「なぜ?」を何度も自問自答するのがコツです。
例えば、「主人公の〇〇というセリフに感動した」と書くだけでなく、「なぜ感動したのか?→自分も同じようなことで悩んでいたから」「なぜ悩んでいたのか?→友達関係がうまくいっていなかったから」というように、自分の内面と向き合ってみましょう。 この部分で、あなたの感想に深みが生まれます。
構成③:なか② – 自分の経験との比較(原稿用紙3枚目)
感想文にオリジナリティを出すための最も重要な部分です。構成②で取り上げた心に残った部分と、あなた自身の経験を結びつけてみましょう。 主人公の行動や気持ちと、自分の過去の体験を比較することで、読者はあなただけの物語として感想文を読むことができます。
「主人公はここで勇気を出して行動したけれど、自分だったらどうしただろうか」「登場人物の〇〇の気持ち、すごくよく分かる。私も以前、同じような悔しい思いをしたことがある」といったように、本の世界と自分の世界を重ね合わせることで、文章に説得力と共感が生まれます。
構成④:なか③ – 作品から学んだこと・考えたこと(原稿用紙4枚目)
この本を読んだことで、あなた自身にどのような変化があったのかを書くパートです。 本を読む前と後で、考え方や価値観がどう変わったのかを具体的に示しましょう。
「この本を読むまで、〇〇について深く考えたことがなかったけれど、今では△△が大切だと思うようになった」「主人公の生き方から、困難に立ち向かう勇気をもらった」など、読書を通して得た「学び」や「気づき」を自分の言葉で表現します。 これにより、感想文が単なる感想に終わらず、知的な探求の記録になります。
構成⑤:おわり(まとめ)- 今後の自分と社会への広がり(原稿用紙5枚目)
いよいよ締めくくりです。これまでの内容を総括し、感想文を力強く締めましょう。 まず、作品全体を通して学んだことを改めてまとめます。そして、その学びをこれからの自分の生活にどう活かしていきたいか、未来に向けた決意や抱負を述べます。
さらに視点を広げ、「この本で描かれている問題は、現代社会の〇〇という問題にも通じるのではないか」というように、社会全体へと考察を広げられると、より評価の高い感想文になります。 読書体験が自分自身の成長だけでなく、社会を見る目をも養ったことをアピールしましょう。
【ステップ別】構成に沿った読書感想文の書き方徹底解説
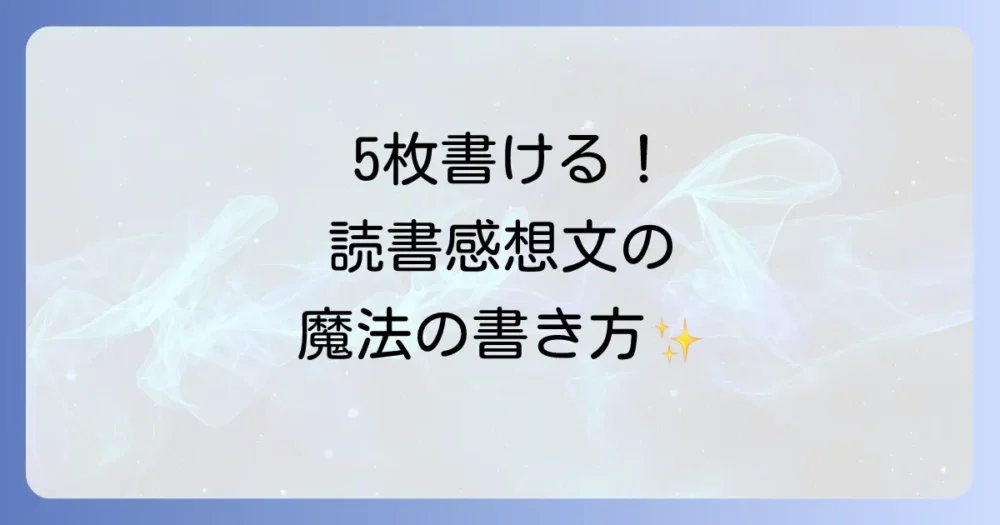
黄金構成テンプレートで骨組みはバッチリですね。でも、「具体的にどんな文章を書けばいいの?」と不安な人もいるでしょう。ご安心ください。ここでは、各構成パートをさらに詳しく、ステップバイステップで解説します。例文も交えながら、読者を引き込む文章作成のコツを伝授します!
この章で解説するステップは以下の通りです。
- ステップ1:はじめ(書き出し)で読者を引き込むコツ
- ステップ2:なか①(心に残った部分)を深掘りする方法
- ステップ3:なか②(自分の経験)でオリジナリティを出す
- ステップ4:なか③(学び)で文章に深みを与える
- ステップ5:おわり(まとめ)で感動的に締めくくる
ステップ1:はじめ(書き出し)で読者を引き込むコツ
書き出しは第一印象を決める大切な部分。ありきたりな表現は避け、読者の心を掴む工夫をしましょう。 おすすめは、印象的な一文から始める方法です。 例えば、本のテーマに触れる問いかけから始めたり、最も心に残ったセリフを引用したりするのも効果的です。
書き出しの例文
- 問いかけから:「もし、明日世界が終わるとしたら、あなたは何をしますか。私がこの本を手に取ったのは、そんな壮大な問いを突きつけられた気がしたからだ。」
- セリフの引用から:「『本当の豊かさとは、目に見えないものなんだよ』。この一言が、私の価値観を大きく揺さぶった。」
その後に、本を選んだ素直なきっかけと、物語の核心に触れすぎない程度の簡潔なあらすじを続けます。 これで、読者はスムーズにあなたの感想文の世界に入り込むことができるでしょう。
ステップ2:なか①(心に残った部分)を深掘りする方法
「感動した」だけで終わらせないためには、「なぜ?」の連鎖で感情を深掘りすることが不可欠です。 まず、心に残った場面やセリフを具体的に引用します。そして、その部分の何が、どのように自分の心に響いたのかを分析していくのです。
深掘りの思考プロセス例
- 心に残った部分:主人公が親友の裏切りを知りながらも、彼を許した場面。
- なぜ心に残った?:普通なら許せないようなことを許した主人公の心の広さに驚いたから。
- なぜ驚いた?:自分だったら絶対に許せないと思ったから。むしろ、仕返しを考えてしまうかもしれない。
- なぜ許せないと思う?:裏切られることは、自分の存在を否定されるようで、とても辛いことだから。
- そこから分かること:主人公の「許す」という行為は、単なる優しさではなく、相手を信じ抜く強さの表れなのかもしれない。
このように思考を深めることで、表面的な感想から一歩踏み込んだ、説得力のある文章になります。
ステップ3:なか②(自分の経験)でオリジナリティを出す
読書感想文は、あなたのことを書いてこそ意味があります。本の内容と自分の体験をリンクさせましょう。 どんな些細なことでも構いません。部活動での挫折、友達との喧嘩、家族への感謝など、自分の引き出しの中から、物語と共鳴するエピソードを探してみてください。
自分の経験と結びつける例文
「主人公がたった一人で困難に立ち向かう姿は、中学最初の部活の試合で、緊張のあまり頭が真っ白になった自分と重なった。周りの期待に応えなければというプレッシャーで押しつぶされそうだったあの時、主人公のように強くありたいと心から思った。彼は、ただ物語の登場人物なのではなく、あの時の自分を励ましてくれる、もう一人の自分のように感じられた。」
このように書くことで、本があなたにとって特別な一冊になったことが伝わり、感想文に血が通い始めます。
ステップ4:なか③(学び)で文章に深みを与える
読書は、新しい世界や価値観に触れる旅です。その旅を通して、あなたが何を発見し、どう成長したのかを具体的に示しましょう。 読む前と読んだ後で、自分の考えがどう変化したのかを対比させると、成長が分かりやすく伝わります。
学びと成長を示す例文
「この本を読む前の私は、正直言って、ボランティア活動などに興味がなかった。自分のことで精一杯で、他人のために時間を使うなんて考えられなかったからだ。しかし、貧しい国の子どもたちのために尽力する主人公の姿に触れ、自分の考えの浅はかさを恥じた。本当の幸せとは、誰かのために何かをすることの中にこそあるのかもしれない。この読書体験は、私の視野を大きく広げてくれた。」
このように、読書による内面的な変化を正直に綴ることで、文章に深みが生まれます。
ステップ5:おわり(まとめ)で感動的に締めくくる
締めくくりは、読者の心に余韻を残す大切なパートです。これまでの議論をまとめ、未来への展望で締めましょう。 この本から得た教訓を、これからの学校生活や人生でどのように活かしていきたいかを力強く宣言します。
感動的な締めくくりの例文
「『絶望の淵でこそ、人は本当の希望を見出す』。この言葉を胸に、私はこれからどんな困難に直面しても、決して諦めない人間になりたい。この一冊の本が、私の人生の羅針盤となってくれるだろう。そしていつか、私も誰かの心を照らす光のような存在になれるよう、日々を大切に生きていきたい。」
このように、本からの学びを自分の未来へと繋げることで、読後感の良い、印象的な感想文が完成します。
原稿用紙5枚を埋めるための事前準備とコツ
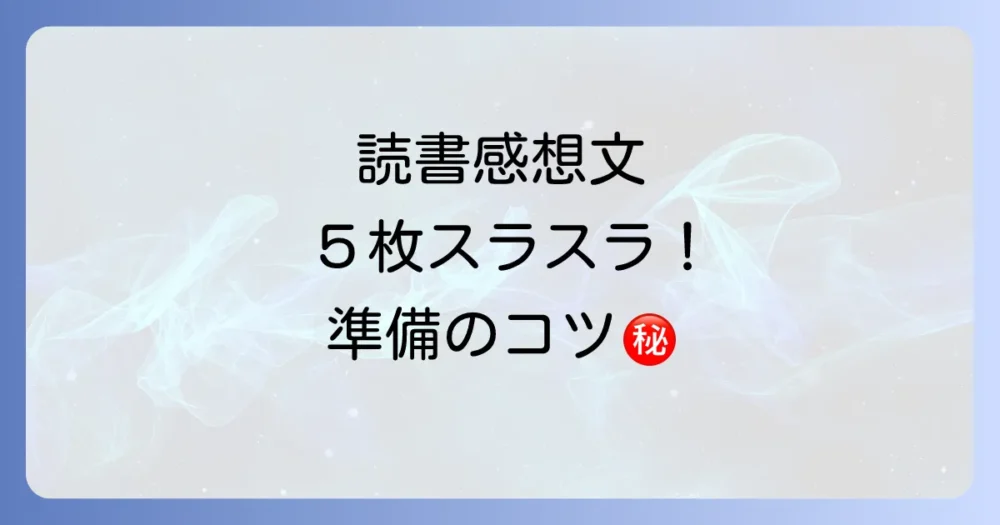
構成や書き方のステップが分かっても、いざ書くとなると材料がなければ始まりません。実は、読書感想文の成功は、本を読み始める前の「準備」で8割決まると言っても過言ではありません。 ここでは、スムーズに5枚を書き上げるための、読み方やメモの取り方といった事前準備のコツを紹介します。
この章で紹介するコツは以下の3つです。
- コツ①:本選びで8割決まる!感想文が書きやすい本の選び方
- コツ②:付箋とメモを活用!読みながらネタを集める方法
- コツ③:魅力的な題名(タイトル)の付け方
コツ①:本選びで8割決まる!感想文が書きやすい本の選び方
どんなに素晴らしい構成を知っていても、感想を書きにくい本を選んでしまっては元も子もありません。感想文が書きやすい本には、いくつかの共通点があります。
感想文が書きやすい本のポイント
- 主人公が自分と同年代、または共感できる状況にいる本:自分の経験と重ね合わせやすく、感情移入しやすいです。
- 友情、家族、夢、命など、普遍的なテーマを扱っている本:自分の考えを深めやすく、書きたいことが見つかりやすいです。
- 主人公や物語に大きな変化(ビフォーアフター)がある本:何がきっかけで変化したのかを分析することで、感想文の核が作りやすくなります。
- ノンフィクションや伝記:事実に基づいているため、社会問題や自分の生き方と結びつけて考えやすいです。
逆に、あまりに専門的で難解な本や、自分の興味からかけ離れた本は避けた方が無難です。「課題図書だから」という理由だけで選ばず、自分が「これなら書けそう!」と直感的に思える本を選ぶ勇気も大切です。
コツ②:付箋とメモを活用!読みながらネタを集める方法
本を読み終えてから「さて、何を書こうか」と思い出そうとしても、細かい感情や心に残ったセリフは忘れてしまいがちです。そこでおすすめなのが、付箋とメモを使いながら読む方法です。
付箋とメモの活用法
- 準備するもの:数色の付箋、ノート、ペン
- 読みながらやること:
- 心が動いた箇所(感動、驚き、疑問など)に付箋を貼る。感情の種類によって色を分けると後で整理しやすいです。
- 付箋を貼ったページ数と、その時感じたことを一言、ノートにメモしておく。「p.56 主人公のセリフに共感。自分も同じことを考えていた。」のように。
- 特に重要だと感じた箇所は、セリフや文章をそのまま書き写しておくと、後で引用しやすくなります。
- 読み終えた後:ノートを見返しながら、どのエピソードを感想文の中心にするか考えます。付箋がたくさん貼られた部分が、あなたの心が最も動いた証拠です。
この一手間をかけるだけで、書き始める段階で豊富な材料が手元に揃っている状態になり、格段に筆が進みやすくなります。
コツ③:魅力的な題名(タイトル)の付け方
題名は、感想文の「顔」です。読者(先生)が最初に目にする部分であり、ここで興味を引けるかどうかが決まります。 「〇〇を読んで」というシンプルな題名も悪くはありませんが、一工夫加えることで、ぐっと印象的な感想文になります。
魅力的な題名の付け方アイデア
- 本から学んだことを入れる:「『本当の強さ』を教えてくれた一冊」
- 最も印象に残った言葉を入れる:「『明日は明日の風が吹く』という言葉の意味」
- 自分の変化を入れる:「臆病だった僕を変えた、たった一つの勇気」
- 問いかけの形にする:「人は何のために生きるのか」
- 本の内容と自分を組み合わせる:「『星の王子さま』と見つけた私の大切なもの」
題名は、感想文を全て書き終えてから、内容全体を最もよく表す言葉を選ぶのがおすすめです。 最後に最高の「顔」を与えてあげましょう。
これはNG!読書感想文でやってはいけない注意点
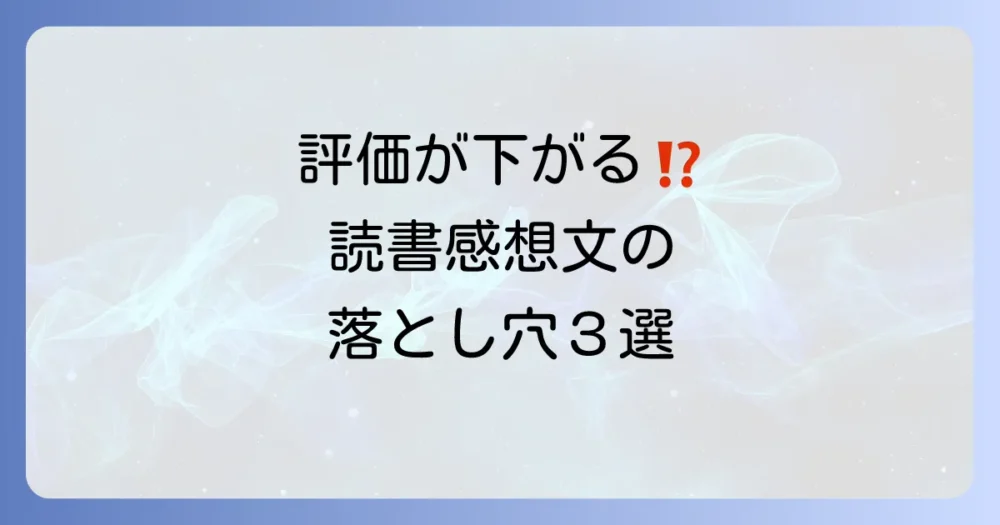
一生懸命書いたのに、評価が低かったら悲しいですよね。そうならないために、読書感想文でやりがちな「NGポイント」を事前に知っておきましょう。これらの点に気をつけるだけで、あなたの感想文は格段にレベルアップします。うっかりやってしまいがちなミスを防いで、先生を「おっ」と思わせる文章を目指しましょう!
この章で解説する注意点は以下の通りです。
- 注意点①:あらすじばかり書く
- 注意点②:「面白かった」「感動した」だけで終わる
- 注意点③:本の受け売りや解説文の丸写し
注意点①:あらすじばかり書く
読書感想文で最も多い失敗例が、感想ではなく、あらすじの紹介で終わってしまうことです。 文字数を埋めるために、物語の展開を延々と説明してしまう気持ちは分かりますが、先生が知りたいのは「本のあらすじ」ではなく「あなたが本を読んで何を感じ、考えたか」です。
あらすじは、本を読んでいない人にも話が通じるようにするための、あくまで導入部分です。 全体の1割程度に留め、すぐにあなたの「感想」に入ることを意識しましょう。あらすじ紹介文ではなく、あなたの意見文を書くのです。
注意点②:「面白かった」「感動した」だけで終わる
「この本はとても面白かったです」「すごく感動しました」という言葉は、もちろんあなたの素直な気持ちでしょう。しかし、それだけでは感想文としては不十分です。 なぜなら、読者は「なぜ面白かったのか」「どこに、どのように感動したのか」を知りたいからです。
「面白かった」という言葉を使うなら、「主人公のユーモアあふれる会話のテンポが良く、まるで自分もその場にいるかのように楽しめたから面白かった」というように、必ず具体的な理由をセットで書きましょう。 感情の背景を説明することで、あなたの感想に説得力が生まれます。
注意点③:本の受け売りや解説文の丸写し
インターネットで検索すれば、本のあらすじや解説、他の人の感想文が簡単に見つかります。しかし、それらを安易にコピー&ペーストするのは絶対にやめましょう。 先生は多くの感想文を読んでいるので、コピペはすぐに見抜かれてしまいます。何より、それではあなた自身の力がつきません。
大切なのは、たとえ稚拙な表現になったとしても、あなた自身の言葉で、あなた自身の考えを綴ることです。 本の解説文に書かれているような立派な分析ではなく、あなたが感じた素朴な疑問や、心に響いた小さな感動こそが、オリジナルの感想文を作る上で最も価値のある材料なのです。
よくある質問
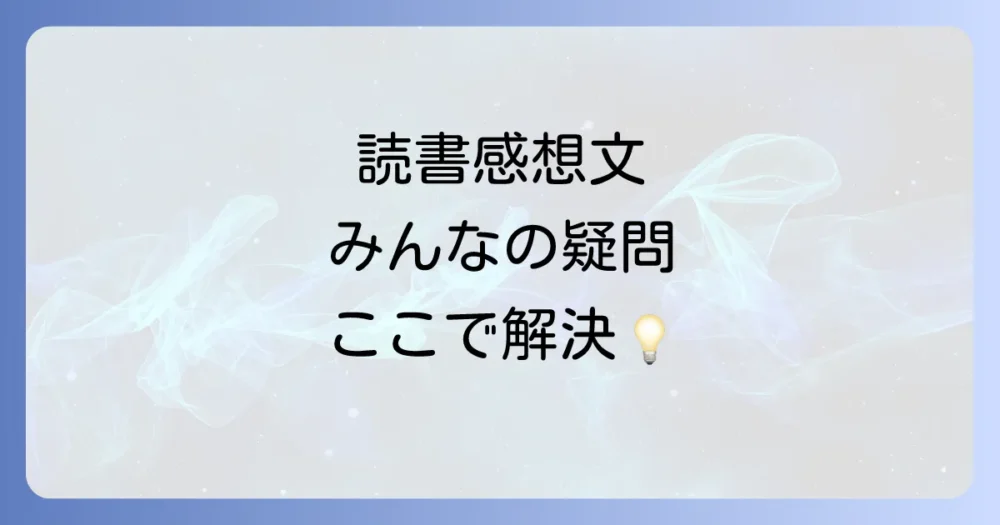
読書感想文の題名はいつ考えればいいですか?
読書感想文の題名は、本文をすべて書き終えてから考えるのがおすすめです。 なぜなら、書き終えた後の方が、文章全体の内容や、自分が最も伝えたかったテーマが明確になっているからです。本文全体を象徴するような、最もふさわしい「顔」を最後につけてあげましょう。
どうしても5枚埋まらない時はどうすればいいですか?
文字数が足りない時は、「自分の経験」や「考えたこと」の部分をさらに深掘りしてみましょう。 例えば、「主人公の行動に共感した」と書いた部分について、「なぜ共感したのか」「自分だったら具体的にどう行動するか」「その経験から何を学んだか」など、「なぜ?」「もし~だったら?」と自問自答を繰り返すことで、内容はどんどん膨らんでいきます。あらすじを増やすのではなく、自分の意見を膨らませるのがコツです。
読書が苦手で本を読み切れません。
読書が苦手な場合は、無理に分厚い長編小説を選ぶ必要はありません。短編集や、自分が興味のある分野のノンフィクション、読みやすいライトノベルなどから始めてみましょう。 大切なのは、最後まで読み通し、何か一つでも心に残ることを見つけることです。映画化された作品の原作を読んで、映像との違いを比較するのも面白い感想文になりますよ。
先生に評価される読書感想文のポイントは何ですか?
先生が評価するポイントは、主に3つあります。
- 自分自身の言葉で書かれているか:解説文の受け売りではなく、自分の体験や考えが正直に書かれていることが重要です。
- 内容に深まりがあるか:「なぜそう感じたのか」が深く掘り下げられており、読書を通して考えが深まっている様子が伝わるか。
- 文章構成がしっかりしているか:「はじめ・なか・おわり」といった構成が整っており、論理的で読みやすい文章になっているか。
上手な文章であること以上に、本と真剣に向き合った跡が見える感想文が高く評価されます。
読書感想文に書いてはいけないことはありますか?
明確に「書いてはいけない」とされていることは少ないですが、避けるべき点がいくつかあります。第一に、本の結末をすべて明かしてしまうこと(ネタバレ)です。特に、物語の核心となるトリックや驚きの結末については、ぼかして書く配慮が必要です。また、根拠のない作品や作者への誹謗中傷、差別的な表現は絶対に避けましょう。感想は自由ですが、他者を尊重する姿勢は忘れてはいけません。
まとめ
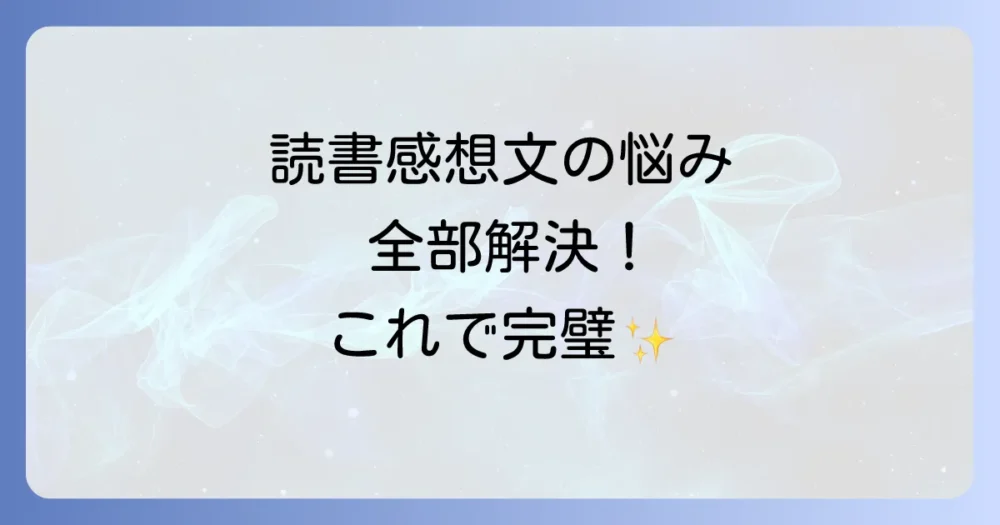
- 読書感想文の悩みは「何を書くか」「分量」「オリジナリティ」。
- 5枚構成のテンプレートを使えば、迷わず書ける。
- 構成は「はじめ」「なか①②③」「おわり」の5部立て。
- 「はじめ」では本との出会いと簡単なあらすじを書く。
- 「なか①」では心に残った部分とその理由を深掘りする。
- 「なか②」で自分の経験と結びつけオリジナリティを出す。
- 「なか③」では本から得た学びや自分の変化を書く。
- 「おわり」で学びを未来の行動へとつなげる。
- 書きやすい本を選ぶことが成功の8割を占める。
- 付箋とメモを使いながら読むと、後で楽になる。
- 題名は感想文の「顔」、最後にじっくり考える。
- NGなのは「あらすじだけ」「感想が浅い」「コピペ」。
- 文字数が足りない時は自分の考えを深掘りする。
- 評価されるのは「自分の言葉」で「深く考えた」文章。
- ネタバレや誹謗中傷は避けるのがマナー。