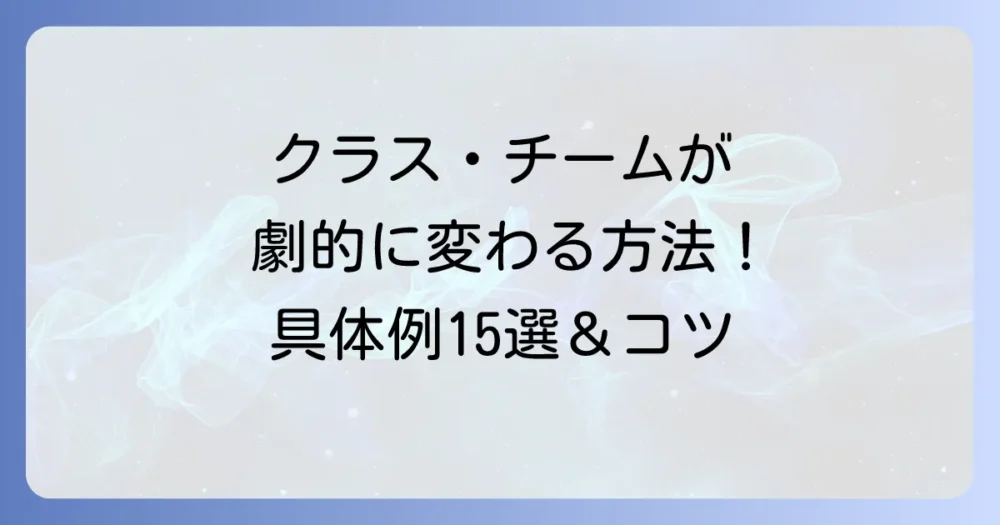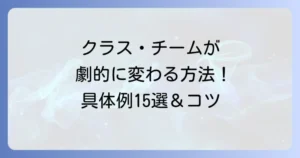「クラスやチームの雰囲気を良くしたい」「メンバー同士がもっと打ち解けるきっかけが欲しい」と感じていませんか?そんな悩みを解決する手法として注目されているのが「構成的グループエンター」です。しかし、言葉は聞いたことがあっても、「具体的に何をすればいいの?」「難しそう…」と感じる方も多いかもしれません。本記事では、構成的グループエンカウンターの基本的な知識から、初心者でもすぐに実践できる具体的なエクササイズ例、成功させるためのコツまで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたも自信を持って構成的グループエンカウンターを企画し、活気あるグループ作りを実現できるでしょう。
構成的グループエンカウンターとは?まず基本をおさえよう
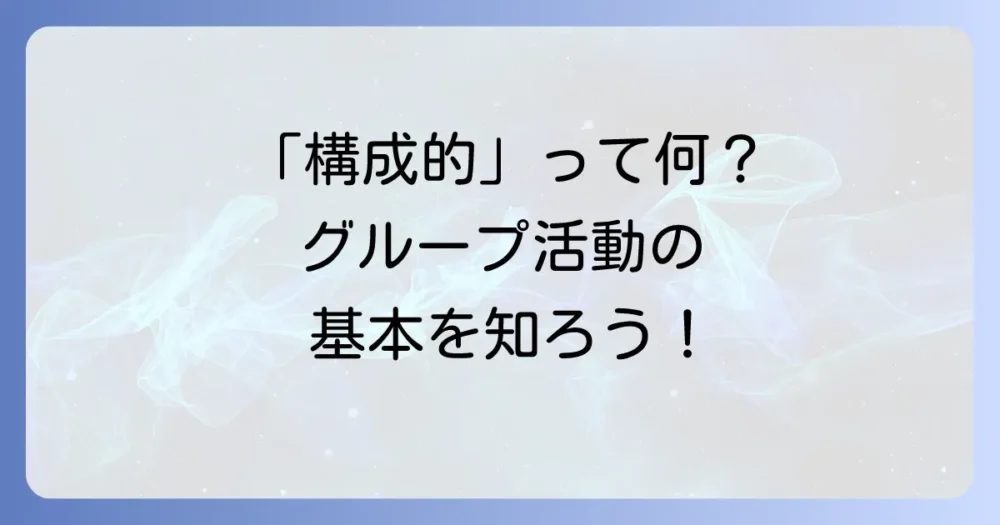
構成的グループエンカウンターは、一言でいうと「あらかじめ決められたエクササイズ(活動)を通して、参加者同士の心と心のふれあいを促し、自己理解や他者理解を深めるグループ体験」のことです。 ただのゲームやレクリエーションとは異なり、体験後の「シェアリング(分かち合い)」で感じたことや気づいたことを言葉にし、感情を共有することに重きを置いています。 これにより、参加者は自分や他者について新たな発見をし、人間関係を豊かにしていくことを目指します。 この章では、まずその基本的な目的と、よく比較される非構成的グループエンカウンターとの違いについて見ていきましょう。
- 構成的グループエンカウンターの目的
- 非構成的グループエンカウンターとの違い
構成的グループエンカウンターの目的
構成的グループエンカウンターの主な目的は、「ふれあい」と「自己発見」です。 エクササイズという共通体験を通して、普段はなかなか言えない本音を安心して表現できる場を作り出します。
参加者は、自分の本当の気持ちに気づき(自己理解)、それを言葉にして伝える(自己開示)練習をします。同時に、他のメンバーの考えや感情に触れることで、自分とは違う価値観を理解し、受け入れる(他者理解)経験を積むことができます。 このような心と心の交流を通じて、互いへの信頼感を育み、より良い人間関係を築いていくことが大きなねらいです。 学校のクラス作りや企業のチームビルディング研修など、様々な場面で活用されています。
非構成的グループエンカウンターとの違い
グループエンカウンターには、「構成的」の他に「非構成的(ベーシック)」と呼ばれるものがあります。 両者の最も大きな違いは、決まったプログラム(エクササイズ)があるかないかです。
非構成的エンカウンターは、特定のテーマや課題を設けず、参加者の自由な対話を中心に進められます。 そのため、より深いレベルでの感情交流が期待できますが、進行が参加者に委ねられる部分が大きく、時間もかかりがちで、リーダーには高度な専門性が求められます。
一方、構成的エンカウンターは、リーダーがエクササイズを準備し、明確な指示のもとで進めるため、初心者でも実施しやすく、限られた時間でも効果を出しやすいという特長があります。 学校の授業や研修など、目的や時間、参加者の特性に合わせて柔軟にプログラムを組めるのが大きなメリットです。
| 項目 | 構成的グループエンカウンター | 非構成的グループエンカウンター |
|---|---|---|
| プログラム | あらかじめエクササイズが決められている | 決まったプログラムはなく、自由な対話が中心 |
| リーダーの役割 | 明確な指示を出し、集団を主導する | 進行を促すファシリテーター役(主導権は低い) |
| 時間 | 短時間でも実施可能 | 時間がかかることが多い |
| 対象 | クラス単位など、大人数でも可能 | 自発的に集まった少人数が基本 |
| 難易度 | 初心者でも比較的実施しやすい | リーダーには高い専門性が求められる |
【初心者でも安心】構成的グループエンカウンターの進め方3ステップ
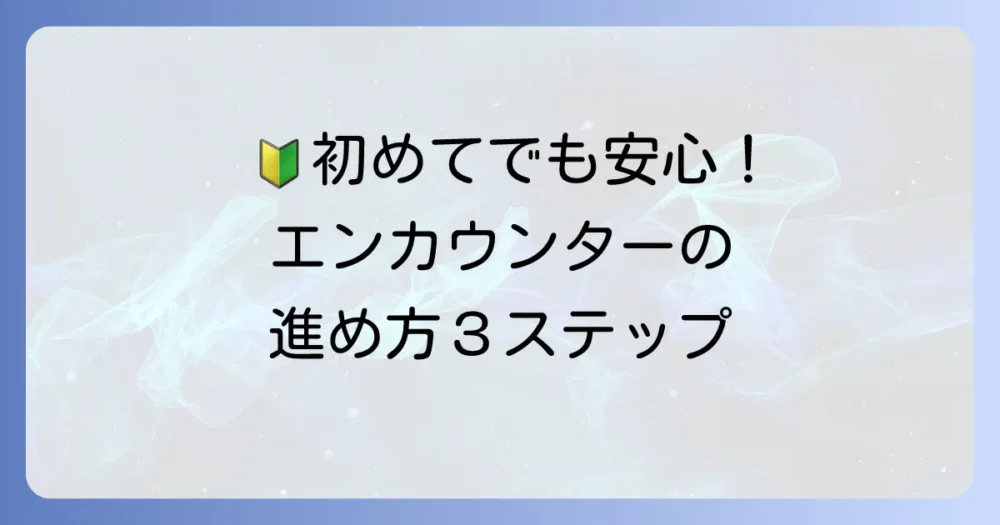
構成的グループエンカウンターは、しっかりとした型に沿って進めることで、誰でも安全かつ効果的に実施することができます。その流れは、大きく分けて「導入」「展開」「まとめ」の3つのステップで構成されています。この流れを意識することで、参加者は安心して活動に集中でき、心を開きやすくなります。ここでは、それぞれのステップで具体的に何を行うのか、そしてどのような点に気をつければ良いのかを詳しく解説していきます。
- ステップ1:導入(ウォーミングアップ)
- ステップ2:展開(メインエクササイズ)
- ステップ3:まとめ(シェアリング・ふりかえり)
ステップ1:導入(ウォーミングアップ)
最初のステップは、参加者の緊張をほぐし、安心して活動に取り組める雰囲気を作るための「導入」です。アイスブレイクとも呼ばれ、本題に入る前の大切な準備運動と位置づけられます。
まずはリーダーが自己紹介をし、これから行うエンカウンターの目的や簡単なルール(例:「人の話を最後まで聞く」「否定しない」など)を説明します。 これにより、参加者は見通しを持って活動に参加できます。その後、「歩き回って挨拶」「簡単な自己紹介ゲーム」など、体を動かしたり、軽いコミュニケーションを取ったりするエクササイズを行います。 ここでの目的は、参加者の心と体をほぐし、グループの一体感を高めることです。楽しい雰囲気作りを心がけましょう。
ステップ2:展開(メインエクササイズ)
ウォーミングアップで場が温まったら、いよいよ中心となる「展開」のステップに移ります。ここでは、その日の目的に合わせたメインのエクササイズを実施します。 例えば、「自己理解を深める」が目的なら「ライフラインチャート」、「他者との協力」が目的なら「ペーパータワー」といったエクササイズを選びます。
リーダーは、エクササイズのやり方を分かりやすく、具体的に説明します(インストラクション)。 参加者が混乱しないよう、手順を一つひとつ丁寧に伝え、必要であれば見本を見せることも効果的です。活動中は、各グループの様子を見守り、困っている参加者がいればそっと声をかけるなど、参加者が安心して活動に没頭できるよう支援します。
ステップ3:まとめ(シェアリング・ふりかえり)
エクササイズが終わったら、最も重要なステップである「まとめ」に入ります。ここでは、体験したことを通して何を感じ、何を考えたのかをグループ内で共有する「シェアリング」を行います。 「エクササイズをやってみてどうだった?」「新しい発見はあった?」といった問いかけを元に、一人ひとりが自分の言葉で気持ちを語ります。
ここでのルールは、誰かの発言を否定したり、茶化したりしないこと。 全員が安心して本音を話せる雰囲気作りが何よりも大切です。リーダーは、全員が話せるように時間配分に気を配り、話しやすい雰囲気を作ります。最後に、リーダーが全体を振り返り、参加者の頑張りを認め、次につながるような言葉で締めくくります。
【目的別】すぐに使える!構成的グループエンカウンターの具体例15選
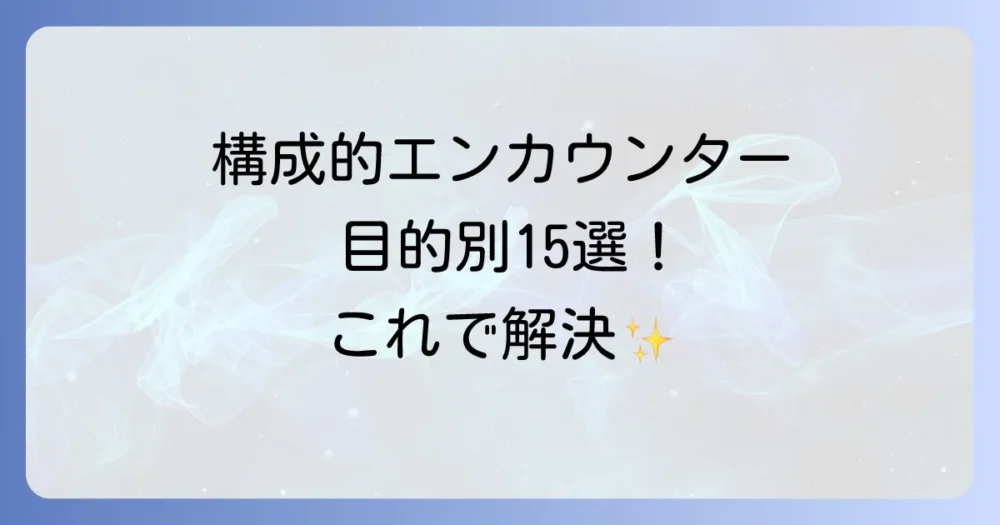
構成的グループエンカウンターの魅力は、目的に合わせて多種多様なエクササイズを組み合わせられる点にあります。ここでは、「アイスブレイク」「自己紹介・自己開示」「他者理解・コミュニケーション」「協力・合意形成」という4つの代表的な目的に分け、明日からでもすぐに使える具体的なエクササイズを15個、厳選してご紹介します。それぞれのやり方やポイントを参考に、あなたのクラスやチームにぴったりのエクササイズを見つけてください。
- アイスブレイク・緊張をほぐす例
- 自己紹介・自己開示を深める例
- 他者理解・コミュニケーションを促す例
- 協力・合意形成を高める例
アイスブレイク・緊張をほぐす例
まずは、場の空気を和ませ、参加者の緊張を解きほぐすためのアイスブレイク例です。活動の導入部分に最適です。
- グッドアンドニュー
- 目的:ポジティブな雰囲気を醸成し、話しやすい空気を作る。
- 準備物:なし。
- 手順:24時間以内にあった「良かったこと(Good)」や「新しい発見(New)」を、グループ内で一人ずつ順番に発表する。
- ポイント:どんな些細なことでもOKというルールを伝え、発表のハードルを下げることが大切です。
- サイコロトーク
- 目的:偶然性を楽しみながら、手軽に自己開示を行う。
- 準備物:テーマを書いたサイコロ(なければ、数字に対応するテーマ表)。
- 手順:サイコロを振り、出た目のテーマについて話す。「好きな食べ物」「最近ハマっていること」など、話しやすいテーマを設定する。
- ポイント:話す時間は1分程度と区切り、テンポよく進めると盛り上がります。
- バースデーライン
- 目的:言葉を使わずに協力する体験を通して、一体感を醸成する。
- 準備物:なし。
- 手順:声を出さずに、ジェスチャーだけでコミュニケーションを取り、誕生日順(1月1日~12月31日)に一列に並ぶ。
- ポイント:終わった後に、答え合わせをしながら「どうやって伝えた?」と振り返ることで、コミュニケーションの面白さに気づけます。
- 人間知恵の輪
- 目的:自然な身体的接触を通して、心理的な壁を取り払う。
- 準備物:なし。
- 手順:全員で輪になり、両隣以外の人と手をつなぐ。絡まった手を離さずに、全員で協力して一つの大きな輪に戻る。
- ポイント:安全に配慮し、無理な体勢にならないよう声をかけることが重要です。
自己紹介・自己開示を深める例
お互いのことをより深く知るための、自己紹介や自己開示を促すエクササイズです。
- 他己紹介
- 目的:相手の話を傾聴する姿勢を養い、紹介を通して他者理解を深める。
- 準備物:筆記用具、メモ用紙。
- 手順:ペアになり、お互いにインタビューをし合う。その後、全体の前でペアの相手を「〇〇さんは、こんな人です」と紹介する。
- ポイント:インタビュー時間をしっかり確保し、相手の魅力を引き出す質問の例(趣味、特技、週末の過ごし方など)を提示すると良いでしょう。
- 自分新聞
- 目的:自分自身を客観的に見つめ、楽しみながら自己表現を行う。
- 準備物:A4用紙、ペン、色鉛筆など。
- 手順:自分をテーマにした新聞を作成する。自分の好きなもの、ニュース、4コマ漫画などを自由にレイアウトする。完成したら、グループ内で発表し合う。
- ポイント:絵や図をたくさん使うことを奨励し、表現の自由度を高めると、個性豊かな作品が生まれます。
- ライフラインチャート
- 目的:これまでの人生を振り返り、自己理解を深めるとともに、他者の人生に触れる。
- 準備物:用紙、ペン。
- 手順:横軸に年齢、縦軸に幸福度や満足度をとり、これまでの人生の浮き沈みを一本の線でグラフにする。山や谷になった出来事を書き込み、グループで共有する。
- ポイント:プライベートな内容を含むため、話したくないことは話さなくて良いという安心できるルールを最初に伝えることが不可欠です。
他者理解・コミュニケーションを促す例
自分とは異なる視点に気づき、コミュニケーションの重要性を体感するエクササイズです。
- 共通点探しゲーム
- 目的:対話を通して、相手との共通点を見つけ、親近感を育む。
- 準備物:なし。
- 手順:4〜5人のグループになり、制限時間内にグループ全員の共通点をできるだけ多く見つける。「出身地」や「血液型」といった簡単なものから、「昨日食べたもの」など意外なものまで探す。
- ポイント:「当たり前」と思えることでも書き出すように促すと、数が伸びて盛り上がります。
- ブラインドウォーク
- 目的:言葉による的確な指示と、相手を信頼することの重要性を体験する。
- 準備物:アイマスク。
- 手順:ペアになり、一人がアイマスクをして目隠しをし、もう一人が言葉だけで障害物を避けながら目的地まで誘導する。
- ポイント:安全な場所を確保し、ゆっくり進むことを徹底します。終わった後、誘導役と歩行役の両方の気持ちをシェアすることが重要です。
- お絵かき伝言ゲーム
- 目的:言葉以外の情報(絵)が、どのように伝わり、変化していくかを体験する。
- 準備物:紙、ペン。
- 手順:一列に並び、最後の人だけがお題(例:東京タワー)を見る。見たお題を前の人の背中に指で描き、描かれた人はそれを解読してさらに前の人の背中に…と伝えていく。一番前の人が、何が伝わってきたかを絵に描いて発表する。
- ポイント:お題を少し複雑にすると、予想外の結末になりやすく、笑いが生まれます。
- アサーション・トレーニング(DESC法)
- 目的:相手を尊重しつつ、自分の意見を誠実に伝える方法を学ぶ。
- 準備物:状況設定が書かれたカード。
- 手順:「貸した本を返してほしい」などの状況を設定し、DESC法(D:描写、E:表現、S:提案、C:選択)に沿って、相手に伝えるロールプレイングを行う。
- ポイント:あくまで練習であることを伝え、様々な表現を試せる雰囲気を作ります。良い点や改善点をフィードバックし合う時間を設けます。
協力・合意形成を高める例
チームで一つの目標に向かって協力し、意見をまとめていくプロセスを学ぶエクササイズです。
- ペーパータワー
- 目的:限られた資源と時間の中で、役割分担や協力をしながら成果を出す体験をする。
- 準備物:A4用紙(20〜30枚程度)、ハサミ、定規など。
- 手順:グループごとに、決められた枚数の紙だけを使って、制限時間内にできるだけ高いタワーを作る。
- ポイント:作戦タイムと作業タイムを分けるルールにすると、計画性の重要性に気づきやすくなります。
- NASAゲーム
- 目的:個人の意見とグループの意見を比較し、合意形成の難しさと重要性を学ぶ。
- 準備物:問題用紙、解答用紙。
- 手順:「月で遭難した」という設定で、手元に残った15個のアイテムに、生き残るために重要な順に優先順位をつける。まず個人で考え、その後グループで話し合って一つの結論を出す。最後に専門家の解答と見比べ、個人とグループのスコアを比較する。
- ポイント:結論を出す過程で、なぜその順位にしたのか理由を述べ合うことを促し、活発な議論を奨励します。
- マシュマロチャレンジ
- 目的:試行錯誤を繰り返しながら、チームで協力して課題を解決する楽しさを体験する。
- 準備物:乾燥パスタ、マスキングテープ、ひも、マシュマロ。
- 手順:グループごとに、これらの材料だけを使って、制限時間内に自立可能なタワーを建て、てっぺんにマシュマロを置く。最も高いタワーを作ったチームが勝利。
- ポイント:「まずやってみる」ことの重要性に気づけるゲームです。PDCAサイクルを回す練習にもなります。
- コンセンサスゲーム
- 目的:多数決ではなく、全員が納得する結論を導き出すプロセス(コンセンサス)を学ぶ。
- 準備物:物語が書かれた問題用紙。
- 手順:「無人島に漂着した」などの設定で、登場人物の中で誰を助けるべきか、あるいはどのアイテムを持っていくべきか、グループで話し合い、全員一致の結論を出す。
- ポイント:全員が納得するまで話し合うというルールを徹底することが最も重要です。時間内に結論が出なくても、そのプロセス自体が学びになります。
構成的グループエンカウンターを成功に導く3つのコツ
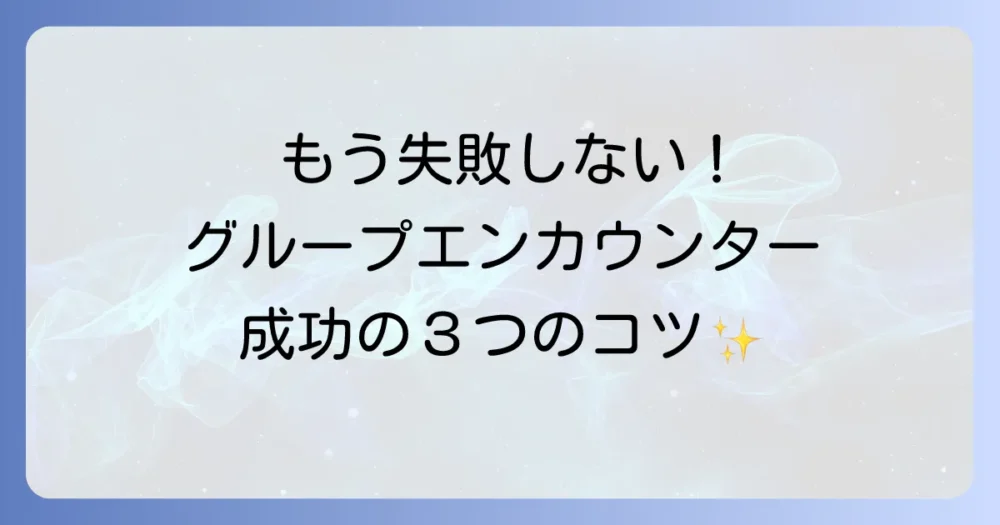
構成的グループエンカウンターをより有意義なものにするためには、ただエクササイズを実施するだけではなく、いくつかの重要なコツがあります。参加者が心から安心して参加し、「やってよかった」と感じられるような場を作るためには、リーダーの細やかな配慮が欠かせません。ここでは、エンカウンターを成功させるために特に意識したい3つのコツ、「安全な雰囲気づくり」「ファシリテーターの心構え」「時間配分と柔軟な対応」について、具体的なポイントを交えながら解説します。
- コツ1:何よりも大切な「安全な雰囲気づくり」
- コツ2:リーダーに求められる「ファシリテーターの心構え」
- コツ3:計画と現実のバランス「時間配分と柔軟な対応」
コツ1:何よりも大切な「安全な雰囲気づくり」
構成的グループエンカウンターの成否は、参加者が「ここでは何を言っても大丈夫」と感じられる心理的安全性にかかっています。 本音を話すことは、勇気がいる行為です。だからこそ、リーダーは誰かの発言を笑ったり、否定したり、評価したりする空気が生まれないよう、細心の注意を払う必要があります。
具体的には、活動の最初に「グランドルール」を全員で確認することが有効です。例えば、「人の話を最後まで聞く」「否定しない、アドバイスしない」「話したくないことはパスできる」「ここで聞いた話は外に持ち出さない」といったルールです。この約束事を共有することで、参加者は安心して自己開示に臨むことができます。リーダー自身が、温かく受容的な態度を終始示すことも、安全な雰囲気を作る上で非常に重要です。
コツ2:リーダーに求められる「ファシリテーターの心構え」
リーダーは、単なる指示役ではありません。参加者の自発的な気づきや交流を促す「ファシリテーター(促進役)」としての役割が求められます。 リーダーが前に出過ぎず、主役はあくまで参加者であるという意識を持つことが大切です。
エクササイズの説明は分かりやすく簡潔に行い、活動中は全体を見渡しながら、孤立している参加者がいないか、議論が停滞しているグループはないかに気を配ります。もし介入が必要な場合でも、答えを教えるのではなく、「〇〇さんはどう思う?」「別の見方はないかな?」といった問いかけで、参加者自身の力で考え、解決できるよう促すのが良いファシリテーターです。 また、参加者一人ひとりの小さな変化や良い点を見つけて認め、勇気づけることも、参加者の意欲を高める上で重要な役割となります。
コツ3:計画と現実のバランス「時間配分と柔軟な対応」
事前にしっかりと計画を立てることは重要ですが、当日は計画通りに進まないことも少なくありません。 あるエクササイズが予想以上に盛り上がったり、逆に参加者の反応が鈍かったりすることもあります。そんな時、計画に固執しすぎず、その場の状況に応じて柔軟に対応することが成功のコツです。
例えば、盛り上がっている活動は少し時間を延長し、逆に関心が低いようであれば早めに切り上げて次の活動に移る、といった判断が求められます。そのためには、時間管理を徹底しつつも、いくつか予備のエクササイズを用意しておくと心に余裕が生まれます。最も大切なのは、参加者の「いま、ここ」での感情や興味を尊重することです。 計画はあくまで目安と考え、ライブ感を大切にしながら進めていきましょう。
よくある質問
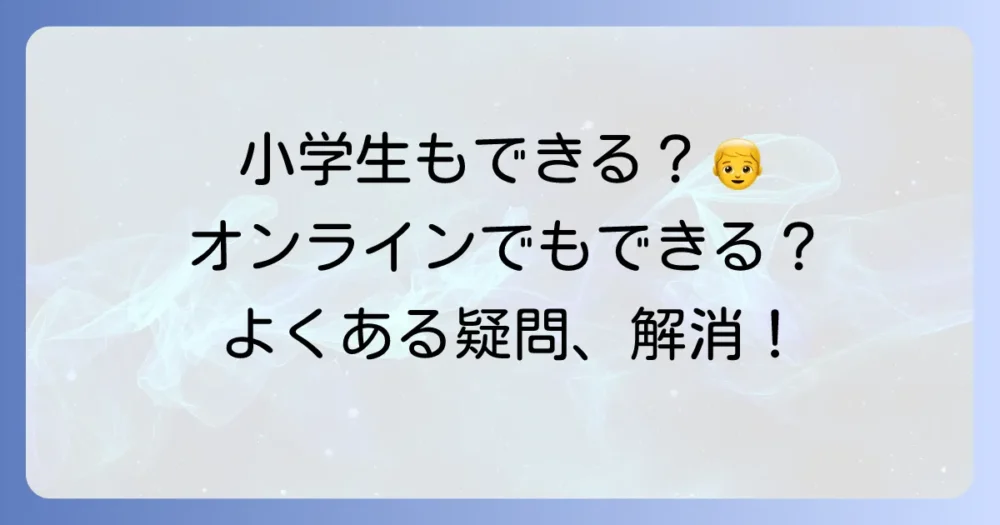
小学生向けにおすすめの構成的グループエンカウンターの例はありますか?
はい、小学生向けには、ルールが分かりやすく、体を動かす要素を取り入れたエクササイズがおすすめです。 例えば、以下のようなものが挙げられます。
- じゃんけん列車:じゃんけんをして負けた人が勝った人の後ろにつながっていくゲームです。 全員が一体となる楽しさを味わえます。
- なんでもバスケット:「フルーツバスケット」の応用版で、「朝ごはんがパンだった人!」などのお題で席を移動します。 友達の意外な一面を知るきっかけになります。
- サイン集め:クラスメイトに話しかけて、サインや簡単な質問の答えを書いてもらう活動です。 自然な会話のきっかけ作りに役立ちます。
これらの活動は、楽しみながら自然にコミュニケーションが取れるため、低学年から高学年まで幅広く活用できます。活動の前後で、どんな気持ちだったかを簡単に話し合う時間を設けると、より学びが深まります。
オンラインでも構成的グループエンカウンターは実施できますか?
はい、オンラインでも工夫次第で十分に実施可能です。オンラインならではのツールを活用すると良いでしょう。
- チャット機能を使った「グッドアンドニュー」:良かったことや新しい発見をチャットに書き込み、順番に発表します。
- ホワイトボード機能を使った「共通点探し」:ブレイクアウトルームに分かれ、共有のホワイトボードにグループの共通点を書き出していきます。
- アンケート機能を使った「なんでもバスケット」:リーダーがお題を出し、当てはまる人にアンケート機能で投票してもらう形式です。
ブレイクアウトルームを活用して少人数での対話を促すことや、カメラのオン・オフ、リアクションボタンなどを活用して参加者の反応を見ることが成功のポイントです。対面よりも表情が読み取りにくいため、リーダーはより意識的に参加者へ声かけをすると良いでしょう。
人数が少ない、または多い場合の調整方法はありますか?
はい、人数に応じて調整が可能です。
人数が少ない場合(5〜6人程度):
グループ分けをせず、全員で一つの輪になって活動できます。一人ひとりの話す時間を十分に確保できるため、「ライフラインチャート」や「自分新聞」など、じっくりと自己開示に取り組むエクササイズに向いています。深いレベルでの共有が期待できるでしょう。
人数が多い場合(30人以上):
4〜6人程度の小さなグループに分けて活動するのが基本です。 リーダーは全体への指示を明確にした後、各グループを巡回してサポートします。グループ対抗戦の形をとる「ペーパータワー」や「共通点探し」などは、人数が多くても盛り上がりやすいです。 シェアリングの際は、各グループの代表者に発表してもらうなど、効率的に意見を共有する工夫が必要になります。
構成的グループエンカウンターで気をつけるべきことは何ですか?
最も重要なのは、参加者の心理的な安全性を確保することです。 そのために、以下の点に特に注意してください。
- 強制しない:エクササイズへの参加や、シェアリングでの発言は強制しない。「パス」する権利を保障することが大切です。
- 否定・批判をしない:どんな意見や感情も、まずは「そう感じたんだね」と受け止める雰囲気を作ります。リーダーが率先してその姿勢を見せることが重要です。
- 秘密を守る:エンカウンターで話された個人的な内容は、その場限りのものとする「守秘義務」のルールを最初に確認します。
これらのルールを最初に全員で共有し、約束事として設定することで、参加者は安心して自分を表現できるようになります。エンカウンターは「楽しかった」で終わるだけでなく、「安心して話せた」という体験が成長につながります。
まとめ
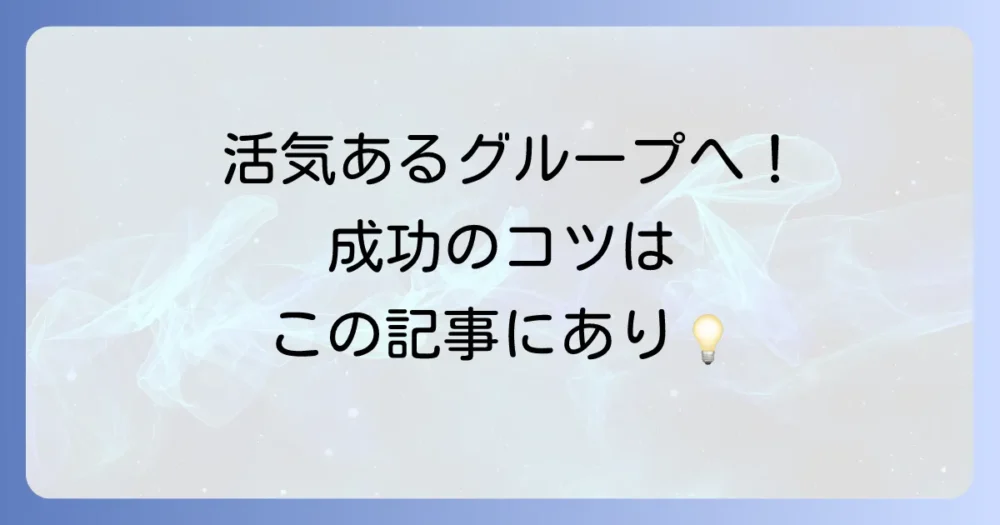
- 構成的グループエンカウンターは、決められた活動で心の交流を促す手法である。
- 主な目的は「ふれあい」と「自己理解・他者理解」の促進にある。
- 決まったプログラムがない「非構成的」と違い、初心者でも実施しやすい。
- 進め方は「導入」「展開」「まとめ」の3ステップが基本である。
- 導入ではアイスブレイクで緊張をほぐし、安心できる場を作ることが重要だ。
- 展開では目的に合わせたメインエクササイズを実施する。
- まとめの「シェアリング」で、体験から得た気づきや感情を共有する。
- アイスブレイクには「グッドアンドニュー」や「バースデーライン」が効果的だ。
- 自己開示を促す例として「他己紹介」や「ライフラインチャート」がある。
- 他者理解には「共通点探し」や「ブラインドウォーク」が役立つ。
- チームでの協力体験には「ペーパータワー」や「NASAゲーム」が適している。
- 成功のコツは、何よりも「心理的に安全な雰囲気」を作ることだ。
- リーダーは指示役ではなく、参加者を促す「ファシリテーター」を意識する。
- 計画に固執せず、場の状況に応じた柔軟な時間配分と対応が求められる。
- 小学生やオンライン、人数の増減にも工夫次第で対応可能である。
新着記事