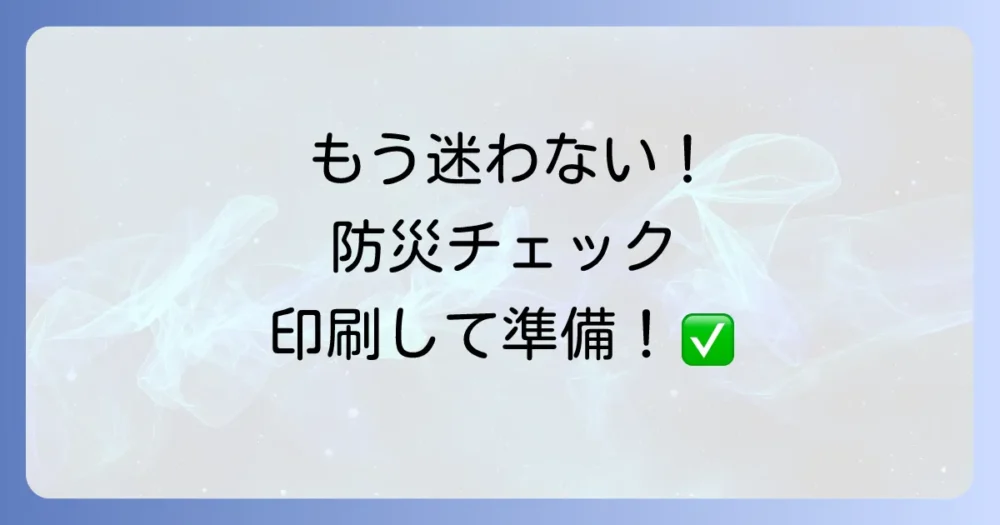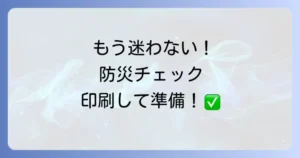「防災グッズを揃えたいけど、何から手をつけていいかわからない…」
「いざという時のために、本当に必要なものを抜け漏れなく準備したい」
地震や台風など、いつ起こるかわからない災害。そんな不安を抱えながらも、日々の忙しさで防災対策が後回しになっていませんか?本記事では、そんなあなたのために、わかりやすさを最優先した防災用品チェックリストを作成しました。この記事を読めば、もう防災準備で迷うことはありません。
【印刷OK】基本の防災用品チェックリスト|まずはこれを揃えよう!
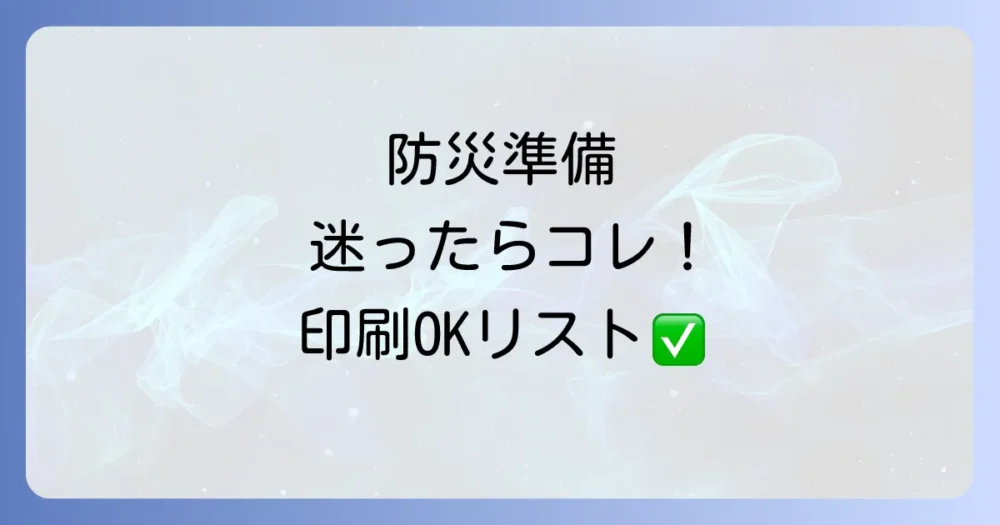
災害への備えの第一歩は、基本となる防災用品を把握することから始まります。ここでは、災害発生直後に命を守り、安全に避難するために必要な「非常持ち出し袋」と、避難生活を支えるための「備蓄品」に分けて、それぞれ必要なものをリストアップしました。このリストを印刷して、一つひとつチェックしながら準備を進めていきましょう。
この章では、以下の内容について詳しく解説します。
- 非常持ち出し袋(一次避難用)に入れるもの
- 備蓄品(二次避難・在宅避難用)として準備するもの
非常持ち出し袋(一次避難用)に入れるもの
非常持ち出し袋は、災害発生時に真っ先に持ち出して避難するためのものです。重すぎると避難の妨げになるため、本当に必要なものを厳選することが重要です。両手が使えるリュックサックにまとめて、すぐに持ち出せる玄関先や寝室に置いておきましょう。重さの目安は、男性で15kg、女性で10kg程度です。
| 分類 | 品名 | チェック | ポイント |
|---|---|---|---|
| 貴重品 | 現金(公衆電話用に10円玉も) | ☐ | 停電時は電子マネーやカードが使えません。お札だけでなく小銭も用意しましょう。 |
| 身分証明書・保険証のコピー | ☐ | 家族全員分をまとめて防水ケースに入れておくと安心です。 | |
| 食料・飲料 | 飲料水(500ml×2本程度) | ☐ | 持ち運びやすいサイズを選びましょう。 |
| 非常食(すぐに食べられるもの) | ☐ | カンパン、エナジーバー、ようかんなど、調理不要で高カロリーのものがおすすめです。 | |
| アメやチョコレート | ☐ | 手軽に糖分補給ができ、不安な気持ちを和らげる効果も期待できます。 | |
| 情報・安全確保 | スマートフォン・携帯電話 | ☐ | 常に充電しておく習慣をつけましょう。 |
| モバイルバッテリー | ☐ | フル充電されたものを。ソーラー充電機能付きも便利です。 | |
| 携帯ラジオ | ☐ | スマホが使えない場合の情報収集に必須。手回し充電式がおすすめです。 | |
| 懐中電灯・ヘッドライト | ☐ | 両手が空くヘッドライトが特に便利です。予備電池も忘れずに。 | |
| ホイッスル | ☐ | 瓦礫の下敷きになった際など、助けを呼ぶために役立ちます。 | |
| 衛生用品 | マスク | ☐ | 感染症対策や粉塵を防ぐために必須です。 |
| 除菌シート・アルコール消毒液 | ☐ | 水が使えない状況で手や身の回りを清潔に保ちます。 | |
| 携帯トイレ | ☐ | 災害直後はトイレが使えなくなる可能性が高いです。最低でも3回分は用意しましょう。 | |
| ティッシュ・トイレットペーパー | ☐ | 芯を抜くとコンパクトになります。 | |
| 常備薬・お薬手帳 | ☐ | 持病のある方は必須。最低でも3日分、できれば1週間分を用意しましょう。 | |
| 救急セット | ☐ | 絆創膏、消毒液、ガーゼ、包帯、痛み止めなど。 | |
| 生理用品 | ☐ | 女性は必須。多めに用意しておくと安心です。 | |
| その他 | 軍手 | ☐ | 瓦礫の撤去やガラス片から手を守ります。滑り止め付きがおすすめです。 |
| タオル | ☐ | 体を拭くだけでなく、防寒やケガの手当にも使えます。 | |
| アルミ製ブランケット | ☐ | 薄くて軽いのに保温性が高い優れもの。寒さ対策に必須です。 |
備蓄品(二次避難・在宅避難用)として準備するもの
備蓄品は、災害発生後の数日間を生き延びるためのアイテムです。ライフライン(電気・ガス・水道)が止まっても、自宅や避難所で生活できるように準備します。最低でも3日分、大規模災害に備えるなら1週間分の備蓄が推奨されています。 普段使っているものを少し多めに買っておき、使った分だけ買い足す「ローリングストック法」なら、無理なく備蓄を続けられます。
| 分類 | 品名 | チェック | ポイント(1人あたりの目安) |
|---|---|---|---|
| 食料・飲料 | 飲料水 | ☐ | 1日3リットル × 3~7日分。調理用の水も考慮しましょう。 |
| 非常食 | ☐ | 1日3食 × 3~7日分。アルファ米、レトルト食品、缶詰、フリーズドライ食品など。 | |
| 生活用品 | カセットコンロ・ガスボンベ | ☐ | 温かい食事は心と体を温めます。ボンベは1週間で6本程度が目安です。 |
| 簡易トイレ・トイレットペーパー | ☐ | 1日5回 × 3~7日分。 トイレットペーパーは多めに備蓄しましょう。 | |
| ラップ・アルミホイル | ☐ | 食器に敷けば洗う手間が省けます。防寒や止血にも役立ちます。 | |
| 衛生用品 | 歯磨きシート・マウスウォッシュ | ☐ | 水が貴重な状況で口内を清潔に保ちます。 |
| ウェットティッシュ・体拭きシート | ☐ | お風呂に入れない時に体を清潔に保つために重宝します。 | |
| ゴミ袋(大小) | ☐ | ゴミをまとめるだけでなく、簡易トイレや防寒着、水の運搬にも使えます。 | |
| 洗剤・石鹸 | ☐ | 長期の避難生活では洗濯や衛生管理に必要です。 | |
| その他 | 新聞紙 | ☐ | 防寒対策、着火剤、簡易トイレの吸収剤など、多用途に使えます。 |
| 養生テープ・ガムテープ | ☐ | 割れた窓の補修やメモの貼り付け、骨折時の固定など、幅広く活用できます。 | |
| 寝袋・エアーマット | ☐ | 避難所の硬い床でも快適に眠るために。体温維持にも役立ちます。 |
【状況別】あなたに必要な防災用品は?追加チェックリスト
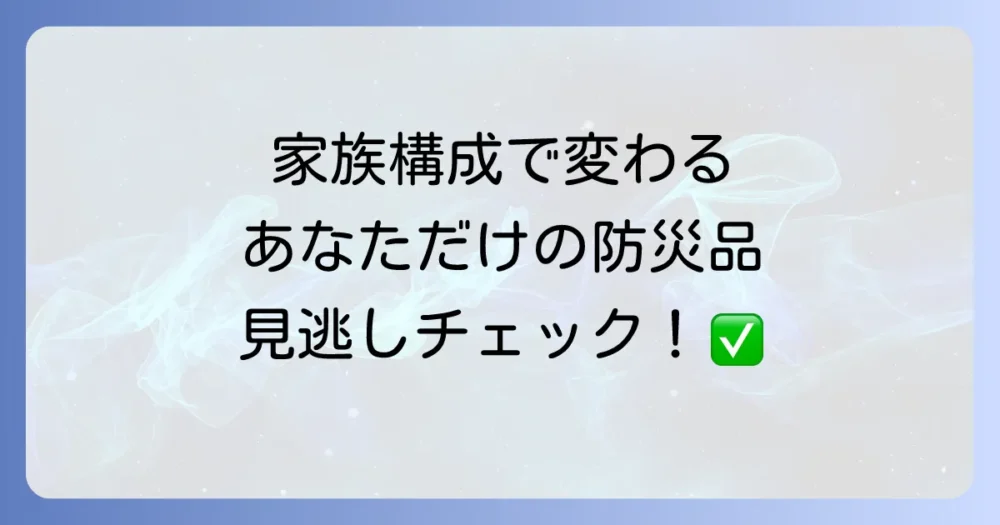
基本の防災用品に加えて、家族構成や個人の状況に合わせたアイテムを準備することで、より安心して災害に備えることができます。ここでは、一人暮らしの方からお子様や高齢者のいるご家庭、女性ならではの視点、そして大切なペットのための備えまで、それぞれの状況に応じた追加のチェックリストをご紹介します。「自分には何が必要だろう?」と考えながら、リストを確認してみてください。
この章では、以下の状況に合わせた追加アイテムを解説します。
- 一人暮らしの方向け
- 赤ちゃん・小さなお子さんがいるご家庭向け
- 高齢者がいるご家庭向け
- 女性ならではの必需品
- ペット(犬・猫)と暮らしている方向け
一人暮らしの方向け
一人暮らしの場合、災害時に助けを呼んだり、頼ったりできる人が近くにいない可能性があります。そのため、自分自身で情報を収集し、安全を確保するための備えが特に重要になります。また、避難所での生活も考慮し、プライバシーを守るためのグッズや、近隣住民とのコミュニケーションツールも準備しておくと心強いでしょう。
- 近隣住民の連絡先リスト: 万が一の時に助け合えるよう、大家さんや隣人の連絡先を控えておきましょう。
- 防犯ブザー: 避難時や避難所での防犯対策に。
- 耳栓・アイマスク: 多くの人が集まる避難所で、少しでも快適に過ごすための必需品です。
- お菓子などの小分けできる食料: 周囲の人とのコミュニケーションのきっかけになります。
- 本や携帯ゲーム機など: 不安な時間を乗り切るための娯楽品も大切です。
赤ちゃん・小さなお子さんがいるご家庭向け
赤ちゃんや小さなお子さんがいるご家庭では、大人とは別に特別な配慮が必要です。ミルクやおむつなど、普段使っているものが手に入りにくくなることを想定し、多めにストックしておくことが大切です。また、避難生活でのストレスを少しでも和らげるためのおもちゃなども忘れずに準備しましょう。
- 粉ミルク・液体ミルク: 液体ミルクは調乳不要ですぐに飲ませられるため、災害時に非常に便利です。
- 哺乳瓶・使い捨て哺乳瓶: 洗浄や消毒が難しい状況を想定し、使い捨てタイプも用意しておくと安心です。
- 離乳食・ベビーフード: お子さんの月齢に合った、そのまますぐに食べさせられるものを選びましょう。
- おむつ・おしりふき: 最低でも1週間分は備蓄しておきたいアイテム。普段使っているサイズを多めに用意しましょう。
- 抱っこ紐: 避難時に両手が空き、安全にお子さんを運ぶことができます。
- お気に入りのおもちゃ・絵本: 不安な環境でも、お子さんが少しでも安心できるように。
- 母子手帳のコピー: アレルギーや予防接種の記録など、お子さんの健康状態を伝えるために重要です。
高齢者がいるご家庭向け
高齢者の方は、持病があったり、体力の低下がみられたりするため、特別な配慮が求められます。普段から服用している薬はもちろん、身体的な負担を軽減するためのグッズを準備することが重要です。また、入れ歯や補聴器など、生活に欠かせないものも忘れないようにしましょう。
- 常備薬: 最低でも1週間分、可能であればそれ以上を用意し、お薬手帳のコピーも一緒に保管しましょう。
- 入れ歯・洗浄剤: 予備の入れ歯もあれば安心です。
- 補聴器・予備電池: 災害情報を聞き逃さないためにも重要です。
- 杖・シルバーカー: 普段使っているものをすぐに持ち出せるように。折りたたみ式の杖も便利です。
- 大人用紙おむつ・尿とりパッド: トイレが不自由な場合に備えて。
- おかゆ・刻み食など: 咀嚼や嚥下がしやすい、食べ慣れた介護食を用意しましょう。
- 老眼鏡: 予備も準備しておくと安心です。
女性ならではの必需品
避難所生活では、プライバシーの確保が難しく、衛生面や防犯面での不安も大きくなります。女性ならではの視点で必要なものを準備しておくことで、心身の負担を大きく軽減できます。普段使っているものを中心に、少し多めに用意しておきましょう。
- 生理用品: 最低でも2サイクル分あると安心です。普段使っているものを多めに備蓄しましょう。
- サニタリーショーツ・おりものシート: 下着の替えが少ない状況でも衛生的に過ごすために。
- スキンケア用品・化粧品: オールインワンジェルなど、手軽に使えるものが便利です。普段使っているもののサンプルも役立ちます。
- 防犯ブザー・ホイッスル: 常に身につけておきましょう。
- 大きめのストールやケープ: 授乳や着替えの際の目隠し、防寒対策にもなります。
- 髪をまとめるゴム・ヘアブラシ: 衛生面だけでなく、気分転換にもつながります。
- 中身が見えないビニール袋: 使用済みの生理用品などを捨てる際に役立ちます。
ペット(犬・猫)と暮らしている方向け
大切な家族の一員であるペットの防災対策も忘れてはいけません。災害時には、ペットとはぐれてしまったり、避難所に一緒にいられない「同行避難」になる可能性も考慮する必要があります。ペットの命と健康を守るための準備をしっかりと行いましょう。
- ペットフード・水: 最低でも5日分、できれば7日分以上を用意しましょう。
- 常備薬: 持病のあるペットは必ず準備しましょう。
- トイレ用品(ペットシーツ、猫砂など): 環境の変化でトイレを失敗することもあるため、多めに用意すると安心です。
キャリーバッグ・ケージ: 避難所での生活や移動に必須です。普段から慣れさせておきましょう。
- リード・ハーネス(首輪): 迷子札を必ずつけておきましょう。予備も準備しておくと安心です。
- ペットの写真・ワクチン接種証明書: 迷子になった際や、避難所で受け入れてもらう際に必要です。
- お気に入りのおもちゃ・タオル: 不安なペットを落ち着かせるために役立ちます。
防災用品を賢く揃えるコツ
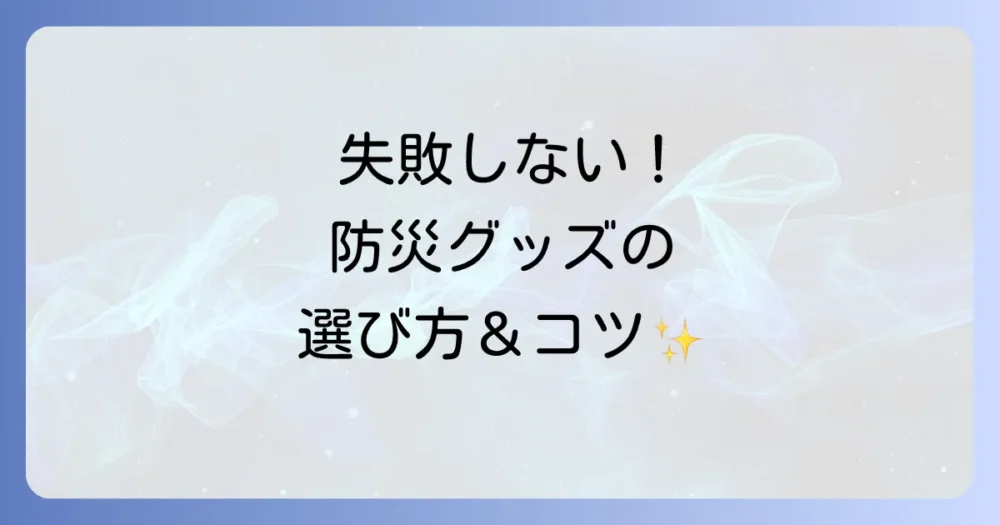
防災用品をすべて完璧に揃えようとすると、費用も手間もかかってしまい、途中で挫折してしまうかもしれません。しかし、ちょっとしたコツを知っていれば、無理なく、そして賢く防災用品を準備することができます。ここでは、100円ショップの活用法から、おすすめの防災セットの選び方、そして「買って後悔した」という声が多いアイテムまで、防災準備に役立つ実践的な情報をお届けします。
この章では、以下のコツについて詳しく解説します。
- 100円ショップで揃えられる便利なアイテム
- おすすめの防災セットは?選び方のポイント
- 失敗しないための注意点|実は不要だったもの
100円ショップで揃えられる便利なアイテム
「防災用品は高い」というイメージがあるかもしれませんが、実は100円ショップでも揃えられる便利なアイテムがたくさんあります。コストを抑えながら、必要なものを効率的に集めることができるので、ぜひ活用しましょう。ただし、品質や耐久性には注意が必要です。特にライトやラジオなどの電子機器は、専門店での購入をおすすめします。
以下は100円ショップで手に入りやすい防災グッズの一例です。
- ウェットティッシュ・除菌シート: 断水時に手や体を拭くのに重宝します。
- 軍手: 滑り止め付きのものを選びましょう。
- ゴミ袋: 様々なサイズを揃えておくと、ゴミ出し以外にも簡易ポンチョや水の運搬など多用途に使えて便利です。
- アルミブランケット: コンパクトで軽量ながら保温性が高く、体温維持に役立ちます。
- 携帯トイレ: 災害直後のトイレ問題は深刻です。いくつか試してみて、使いやすいものを選んでおくと良いでしょう。
- ラップ・アルミホイル: 食器に敷いて使えば洗い物が不要に。体に巻いて防寒対策にもなります。
- ウォータータンク: 給水車から水をもらう際に必要です。折りたたみ式がコンパクトで便利。
- スリッパ: 避難所で足元を清潔に保ち、ガラス片などから足を守ります。
おすすめの防災セットは?選び方のポイント
「何から揃えればいいか分からない」という方には、必要なものが一通り揃った防災セットが便利です。 しかし、セット内容は商品によって様々。自分や家族にとって本当に必要なものが入っているか、購入前にしっかりと中身を確認することが大切です。防災セットを基本に、自分に必要なものを追加していくのが賢い方法です。
防災セットを選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 防災士監修かどうか: 災害のプロが監修したセットは、実践的で本当に役立つアイテムが厳選されていることが多いです。
- リュックの機能性: 防水・撥水加工が施されているか、反射材が付いているか、背負いやすいかなどをチェックしましょう。デザイン性が高く、普段使いできるものなら、いざという時も持ち出しやすいです。
- 食料・水の内容と賞味期限: アレルギーに対応しているか、調理不要で食べられるか、賞味期限は十分かを確認しましょう。水や食料が入っていないセットもあるので注意が必要です。
- 自分に必要なものが揃っているか: 女性向け、子供向けなど、ターゲットを絞ったセットもあります。家族構成に合わせて選び、足りないものは個別に追加購入しましょう。
- レビューや口コミ: 実際に購入した人の声は非常に参考になります。特に、リュックの重さや収納力、中身の品質についてのレビューは要チェックです。
失敗しないための注意点|実は不要だったもの
防災準備でよくあるのが、「念のために」と色々詰め込みすぎて、重くて持ち運べなくなってしまうケースです。また、被災経験者の声を聞くと、「これは要らなかった」というアイテムも意外と多くあります。 本当に必要なものを見極め、身軽に動けるようにすることが、安全な避難につながります。
以下は、「不要だった」という声が比較的多いアイテムです。ただし、状況によっては役立つ場合もあるため、自分の環境に合わせて判断してください。
- ロープ: 救助活動などで使うイメージがありますが、専門的な知識がないと使いこなすのが難しく、かえって危険な場合もあります。
- コンパス(方位磁石): スマートフォンの地図アプリで代用できることが多く、避難経路はハザードマップで事前に確認しておくことが重要です。
- ろうそく: 火災や火傷のリスクがあるため、灯りとしてはLEDライトやランタンの方が安全で推奨されます。
- インスタントラーメン(カップ麺): 調理に多くの水やお湯が必要なため、断水時には貴重な水を消費してしまいます。 水なしで食べられる非常食の方が適しています。
- テント: 避難所に入れない場合に備えるものですが、重くてかさばるため、持ち出し袋に入れるのは現実的ではありません。 在宅避難や車中泊を想定するなら検討の価値はあります。
防災の基本|備蓄と見直しの考え方
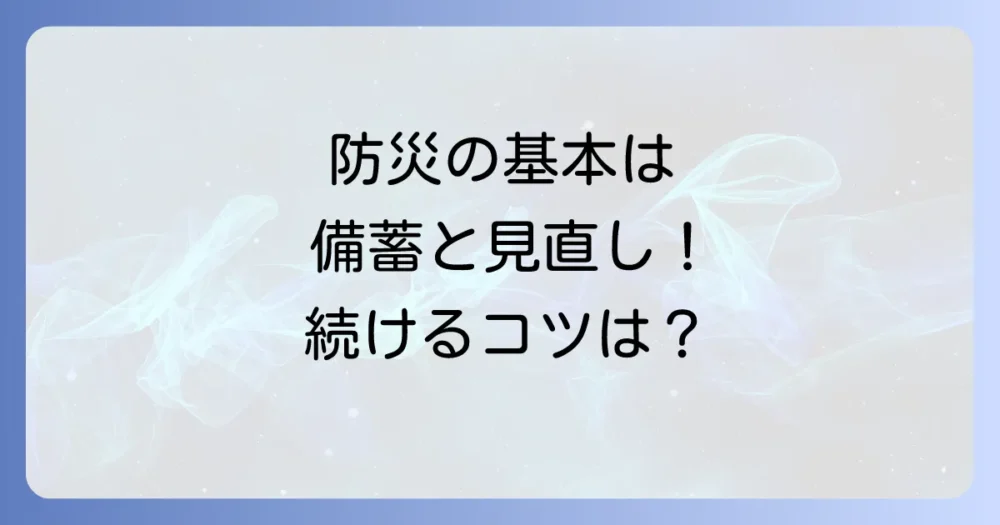
防災用品を一度揃えたら、それで終わりではありません。いざという時に本当に役立つようにするためには、日々の備蓄の習慣と、定期的な見直しが不可欠です。食料の賞味期限が切れていたり、電池が液漏れしていたりしては、せっかくの備えも無駄になってしまいます。ここでは、無理なく続けられる備蓄の方法から、適切な収納場所、そして見直しのタイミングとポイントまで、防災対策を万全にするための基本を解説します。
この章では、防災の基本となる以下の項目について詳しく説明します。
- 「ローリングストック法」で無理なく備蓄しよう
- 防災用品の収納場所と保管方法
- 最低でも年に1回!見直しのタイミングとポイント
「ローリングストック法」で無理なく備蓄しよう
「ローリングストック法」とは、普段の生活で使う食料品や日用品を少し多めに備蓄し、古いものから消費して、使った分を買い足していく方法です。この方法の最大のメリットは、特別な非常食を準備しなくても、普段から食べ慣れた味を災害時にも食べられること、そして賞味期限の管理がしやすいことです。
ローリングストックを始めるための簡単なステップは以下の通りです。
- 備蓄リストを作る: まずは、缶詰、レトルト食品、パスタ、カップ麺、飲料水など、日持ちする食品の中から、家族が普段よく食べるものをリストアップします。
- 少し多めに購入する: いつもの買い物で、リストアップした商品を「+1個」多く購入します。例えば、いつも2パック買うレトルトカレーを3パック買う、といった具合です。
- 古いものから使う: 備蓄品を使う際は、必ず賞味期限が近い古いものから消費します。収納する際に、手前に古いもの、奥に新しいものを置くようにすると管理しやすくなります。
- 使った分を補充する: 備蓄品を使ったら、次回の買い物で必ずその分を買い足し、常に一定量をキープするように心がけましょう。
このサイクルを繰り返すことで、無理なく、無駄なく、常に新しい備蓄品を維持することができます。
防災用品の収納場所と保管方法
防災用品は、必要な時にすぐに取り出せる場所に保管しておくことが何よりも重要です。災害の種類や状況によって、どこから避難するかが変わるため、一か所にまとめず、分散して保管するのがポイントです。
おすすめの収納場所は以下の通りです。
- 玄関: 非常持ち出し袋(一次避難用)の最も基本的な置き場所です。靴箱の中や、すぐに持ち出せるクローゼットなどが適しています。
- 寝室: 就寝中に災害が発生した場合に備え、枕元に懐中電灯、スリッパ(ガラス片などから足を守るため)、ホイッスルなどを置いた小さな防災セットを準備しておくと安心です。
- リビング・キッチン(パントリー): 在宅避難用の備蓄品(食料、水、カセットコンロなど)は、ローリングストックを実践しやすいキッチン周りやパントリーに保管するのが効率的です。
- 車の中: 車で避難する可能性や、車中泊をすることも想定し、車内にも防災セットを積んでおきましょう。飲料水、携帯トイレ、ブランケット、モバイルバッテリーなどを入れておくと役立ちます。ただし、夏場の車内は高温になるため、食料やスプレー缶などの保管には注意が必要です。
- 物置・屋外倉庫: 家が倒壊しても取り出しやすい可能性があるため、スコップやバールなどの工具類を保管しておくのに適しています。
最低でも年に1回!見直しのタイミングとポイント
防災用品は、一度準備したら終わりではありません。定期的な見直しを怠ると、いざという時に使えないという事態になりかねません。最低でも年に1回、できれば半年に1回は見直しを行い、常に万全の状態を保ちましょう。見直しの日を「防災の日(9月1日)」や家族の誕生日などに決めておくと、忘れにくくなります。
見直しの際にチェックすべきポイントは以下の通りです。
- 食料・飲料水の賞味期限: 期限が近いものは普段の食事で消費し、新しいものと入れ替えましょう。ローリングストック法を実践していれば、この手間は大幅に軽減されます。
- 医薬品の使用期限: 常備薬や救急セットの中身も忘れずにチェック。
- 電池の確認: 懐中電灯やラジオに入れてある電池は、液漏れしていないか確認し、定期的に新しいものに交換しましょう。予備電池の使用推奨期限もチェックします。
- 衣類のサイズ: お子さんの成長に合わせて、衣類や靴のサイズが合っているか確認し、必要であれば入れ替えます。
- 季節に合わせた調整: 夏前には冷却シートや携帯扇風機、冬前にはカイロや防寒具を追加するなど、季節に応じた見直しも重要です。
- 家族構成の変化: 家族が増えたり、高齢の親と同居を始めたりした場合など、家族の状況変化に合わせて中身を見直しましょう。
見直しの際には、実際にリュックを背負ってみて重さを確認したり、ラジオやライトが正常に作動するかをテストしたりすることも大切です。
よくある質問
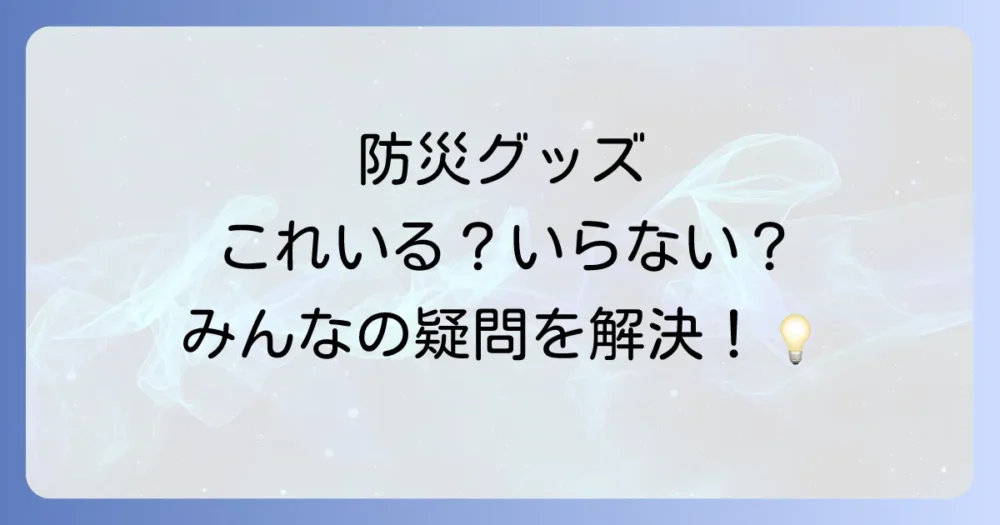
防災リュックの中身は何が必要ですか?
防災リュック(非常持ち出し袋)には、避難時に命を守るための最低限のものを入れます。具体的には、飲料水、すぐに食べられる非常食、携帯ラジオ、ライト、モバイルバッテリー、現金、常備薬、衛生用品(マスク、携帯トイレ、除菌シートなど)、軍手、タオルなどが挙げられます。 両手が使えるリュックに、重すぎない程度(男性15kg、女性10kgが目安)にまとめるのがポイントです。
防災グッズで本当に必要なものは何ですか?
被災経験者の声などから、本当に必要とされるものは、「水と食料」「トイレ用品」「情報収集手段」「明かり」の4つに集約されます。具体的には、最低3日分の飲料水と調理不要の食料、携帯トイレやトイレットペーパー、スマートフォンを充電するためのモバイルバッテリーや携帯ラジオ、そして停電時に必須のLEDライトやヘッドライトです。これらは命に直結するため、最優先で準備しましょう。
防災グッズは何日分必要ですか?
一般的に、災害発生後の人命救助が優先される最初の72時間(3日間)を自力で乗り切るための備えが必要とされています。 そのため、非常持ち出し袋には最低1日分、自宅の備蓄品としては最低3日分の水や食料を用意するのが基本です。 しかし、南海トラフ巨大地震などの大規模災害を想定すると、支援が届くまでに1週間以上かかる可能性も指摘されており、可能であれば1週間分の備蓄があるとより安心です。
防災グッズでいらないものは何ですか?
「絶対に不要」というものはありませんが、被災経験者から「あまり役に立たなかった」という声が挙がるものもあります。 例えば、専門知識がないと扱えないロープ、スマホで代用できるコンパス、火災の危険があるろうそく、調理に貴重な水を使うカップ麺などです。 自分の状況やスキルに合わせて、本当に必要かを見極めることが大切です。
防災セットはどこで買うのがおすすめですか?
防災セットは、ホームセンター、家電量販店、アウトドアショップ、防災用品専門店、インターネット通販などで購入できます。 品揃えが豊富なのはホームセンターや専門店です。家電量販店ではラジオやバッテリーなどの防災家電が充実しています。 ネット通販は種類が豊富で、防災士が監修したセットや、特定のニーズ(女性向けなど)に特化した商品を見つけやすいのがメリットです。 購入する際は、中身をしっかり確認し、レビューを参考に自分に合ったものを選びましょう。
まとめ
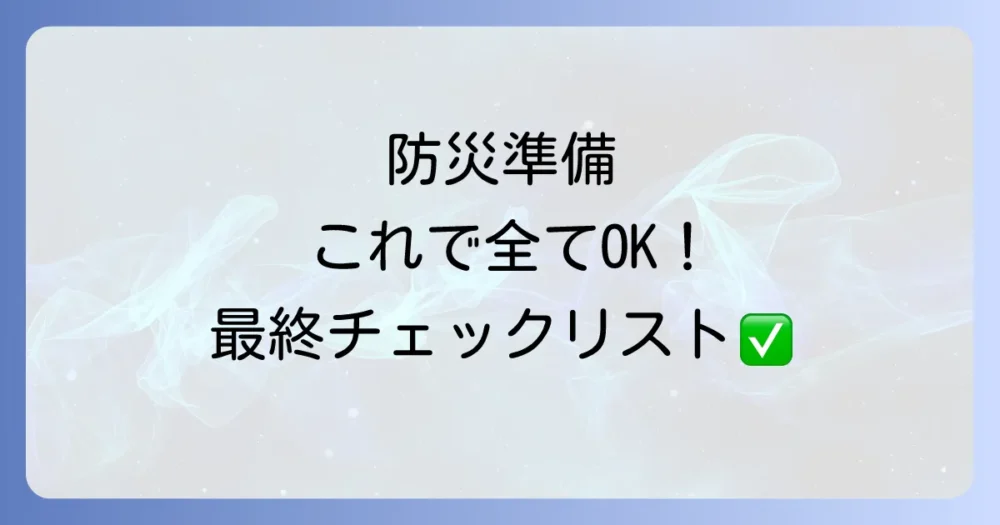
- 防災の基本は「非常持ち出し袋」と「備蓄品」の2段階で考える。
- 非常持ち出し袋は、命を守る最低限のものを厳選する。
- 備蓄品は最低3日分、できれば1週間分を目標に準備する。
- 無理なく備蓄を続けるには「ローリングストック法」がおすすめ。
- 家族構成(子供、高齢者、ペット)に合わせた追加アイテムを忘れない。
- 女性は衛生用品や防犯グッズなど、特有の視点での準備が大切。
- 100円ショップも活用し、賢くコストを抑えて揃える。
- 防災セットは中身を吟味し、自分に必要なものを追加する。
- ロープやコンパスなど、人によっては不要なものもあるので見極める。
- 防災用品は玄関、寝室、車内などに分散して保管する。
- 年に1回は必ず中身を見直し、賞味期限や状態をチェックする。
- 見直しの際は、季節や家族構成の変化も考慮する。
- 本当に必要なものは「水・食料」「トイレ」「情報」「明かり」。
- 防災対策は「備えて、見直す」ことの繰り返しが重要。
- 今日からできる小さな一歩が、いざという時に自分と家族を守る。
新着記事